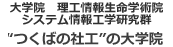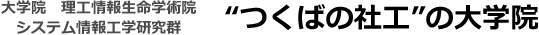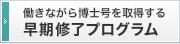2025年度 地域未来創生教育コース(社会工学学位プログラム)のカリキュラムポリシー
社会工学学位プログラム博士前期(修士)課程のカリキュラムを基本に、アクティブラーニングを通じて、実践的にプロジェクトを推進する能力の習得を重視した教育をおこないます。
地域未来創生教育コースの履修モデル
科目名はシラバスにリンクされています。#今年度開講せず
| 科目区分 | 科目 | 単位数 | 履修 モデル1 |
履修 モデル2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院共通科目 学術院共通専門基盤科目 |
専門基礎科目 | 選択科目 (2単位以上) |
(大学院共通科目 学術院共通専門基盤科目) | ● | ● | ||
| 社会工学関連科目以外 | |||||||
| 研究群 共通科目群 |
専門基礎科目 | 選択科目 (6単位以上) |
社会工学のための数学 | 2 | |||
| ミクロ経済学 | 2 | ||||||
| 社会シミュレーション | 2 | ● | |||||
| ゲーム理論 | 2 | ● | |||||
| 統計分析 | 2 | ● | |||||
| 企業評価論 | 2 | ● | |||||
| 制度・政策決定論 | 2 | ● | |||||
| 都市と環境 | 2 | ● | |||||
| 空間情報科学 | 2 | ||||||
| モビリティ・イノベーションの社会応用 | 2 | ● | ● | ||||
| ブロックチェーン技術と地域未来創生 | 2 | ● | ● | ||||
| 専門 科目 |
選択 科目 (0単位以上) |
資産・資源/ 空間・環境のデザイン |
都市・地域解析学 | 2 | |||
| 空間・環境/ 組織・行動のデザイン |
都市開発プロジェクト・マネジメント/地域経営論 | 2 | ● | ||||
| 経済・政策分析 | 2 | ● | |||||
| 組織・行動/ 資産・資源のデザイン |
ビジネス戦略:理論と実践 | 2 | ● | ||||
| 情報セキュリティ | 2 | ● | |||||
| ファイナンス:理論と実践(野村證券講座) | 2 | ||||||
| 資産・資源のデザイン | 資産評価論 | 2 | |||||
| 離散数理 | 2 | ||||||
| 数理最適化理論 | 2 | ||||||
| 空間・環境のデザイン | 地域科学 | 2 | |||||
| 都市形成史 | 2 | ● | |||||
| 住環境計画論 | 2 | ● | |||||
| 組織・行動のデザイン | ミクロ計量分析 | 2 | |||||
| オペレーション管理 | 2 | ● | |||||
| 社会工学特別講義I # | 2 | ||||||
| 社会工学特別講義Ⅱ | 2 | ||||||
| 社会工学特別講義III | 1 | ||||||
| 社会工学特別講義IV | 1 | ||||||
| 学位プログラム科目群 | 専門基礎科目 | 選択科目 (2単位以上) |
社会工学ワークショップⅠ | 1 | ● | ||
| 社会工学ワークショップⅡ | 1 | ● | |||||
| 社会工学インターンシップ | 2 | ● | |||||
| 地域未来創生アクティブラーニングI | 2 | ● | ● | ||||
| 地域未来創生アクティブラーニングII | 2 | ● | ● | ||||
| 地域未来創生アクティブラーニングIII | 2 | ● | ● | ||||
| 必修科目 (2単位) |
地域未来創生概論I | 1 | ● | ● | |||
| 地域未来創生概論II | 1 | ● | ● | ||||
| 専門科目 | 選択科目 (0単位以上) |
社会工学ファシリテーター育成プレプログラムⅠ | 1 | ● | |||
| 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムⅡ | 1 | ||||||
| 社会工学ファシリテーター育成プログラムⅠ | 2 | ● | |||||
| 社会工学ファシリテーター育成プログラムⅡ | 2 | ||||||
| 必修科目 (12単位) |
社会工学修士基礎演習I | 2 | ● | ● | |||
| 社会工学修士基礎演習II | 2 | ● | ● | ||||
| 社会工学修士特別演習I | 2 | ● | ● | ||||
| 社会工学修士特別演習II | 2 | ● | ● | ||||
| 社会工学修士特別研究I | 2 | ● | ● | ||||
| 社会工学修士特別研究II | 2 | ● | ● | ||||
| 合計 | 36 | 36 | |||||
履修モデル1:
まちづくりコーディネーター計36単位を履修し研究を行った結果、まちづくりにIoT技術を利用する能力を身につけ、まちづくり現場でのコーディネーター業務を行う専門家となる
履修モデル2:
IoTを活用した政策・制度の構築にかかわる自治体職員計36単位を履修し研究を行った結果、メカニズムデザインなど制度設計で重要となる理論などを学び、自治体におけるIoTを導入した新しい政策や制度の構築に積極的に関与できる高度な専門知識をもつ職員となる。