一 .序論
1.土浦市の概要
2.計画人口
3.JICASTRADAによる分析
二.基本理念
三.基本構想
四 .計画人口
五 .基本計画
1 新市庁舎
2 空き店舗の有効活用
3 りんりんロードの拡充
4 コミュニティバス
5 シニアアーバン計画
六.おわりに
1.自転車道整備の目的
・環境負荷の低減
土浦中心市街地の慢性的な渋滞に対して、自転車利用の促進はその改善策となり、渋滞緩和は環境負荷の低減につながる。
・土浦市内での自転車交通の優位性
自転車は都市内交通手段として、5km程度までの移動において、電車や自動車などに比べて移動時間が短い。土浦市の都市の規模を考えたときに、自転車での移動は効率的な移動手段となり得る。
・自転車利用の促進のための環境
土浦市には、すでに筑波鉄道の線路後を利用した大規模自転車専用道つくばりんりんロードという自転車道整備の中心となるものがある。また、市の重要な財産である霞ヶ浦湖畔や桜川河川敷といった水際線が多く存在し、これらの整備は自転車利用促進のための大きな要素となる。
2.自転車利用についての問題と対策
自転車は、自動車や歩行者に比べて、通行位置や通行方法があいまいになっている。
そのため、歩行者や車道での自動車とのトラブルが発生したり、自転車が段差や障害物に悩まされたりすることがある。 また、駐輪場も問題となっていて、違法駐輪による歩行の妨害なども解決しなくてはいけない問題である。
そこで、現在の道路空間において、自転車、歩行者、自動車の3者が安全・快適に利用できるような改善を行う。歩道等において、自転車と歩行者の通行位置や通行方法を明確にすることで、問題の解決を図り、快適な走行空間をつくることができると考える。具体的には、
€カラー舗装による自転車・歩行者空間の視覚的分離、
植栽帯による自転車・歩行者空間の分離、
¡道路空間の再配分(幅員構成の見直し)などについて、土浦市の現在の道路状況などから検討した。
3.方針
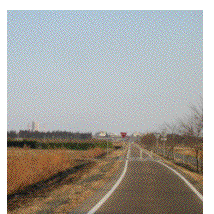 |
| つくばりんりんロード |
つくばりんりんロード、桜川河川敷、霞ヶ浦湖畔はレクリエーション用の専用道の整備を行い、それを軸にして、駅周辺の市街地へも乗り入れられるような自転車道を考えた。
施設としては、駅、商店街、自転車利用者が多い高等学校、市役所予定地などへのアクセスを考えた。基本的には、りんりんロードがカラーの舗装がなされているので、一体感ということを考えてもカラー舗装による自転車・歩行者空間の分離が効果的かと思われる。モール505に関しては、すでに、広くて、歩行空間が整備されているので、植栽帯などによって分離する必要がある。駅西口の線路沿いの道には駐輪場が集中しているので、そこも整備が必要だ。レクリエーション以外の利用が考えられる場所には、街灯の設置も必要になる。
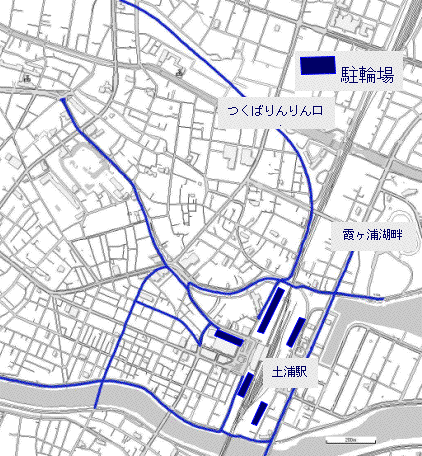 |
| 図9.りんりんロード拡充の概略図 |