社会的ジレンマ班 第三エリア 学生食堂 混雑改善計画 ~混雑とは、避けられるもの~
都市計画実習2010
1社会的ジレンマについて
社会的ジレンマの説明 藤井聡先生の本を参考に・・・
3掲示・配布したもの
私たちが、3A棟内に掲示したものの紹介☆
実験の効果計測結果
1.学食調査
1-1-1.レジ通過人数計測の狙い
時系列に沿って時間単位あたりのレジ通過人数を計測することで、①実験前・実験中に何人の人が昼食時に3学食堂を利用しているのかを判明させ、②どの時間帯にどれほどの人数が利用したのかが判明させることを狙いとした。
1-1-2.レジ通過人数結果
総利用者数は実験前は128人,実験中は185人だった。
1-1-3.レジ通過人数の分析(図1)
縦軸に(2分ごとのレジ通過人数)/(全体の利用者)とした割合の%をとり、横軸に2分ごとの時系列を置いた。図1からも解るとおり、実験前(青色のグラフ)では11:15から11:30(ピーク時間と呼ぶ)に利用者が極端に集中しており、われわれが実験中に利用するように促した非ピーク時間(11:45から12:00)では利用者が極端に減っていることがわかる。また、11:15から11:16と11:54から12:00の2回にわたって利用者のピークが集中している。しかし実験中(桃色のグラフ)ではどの時間においても均等に利用者がカウントされ、われわれが利用を促した非ピーク時間においても利用者が増えていること(協力行動者が増大したこと)がわかる。
1-2-1.扉の通行人数計測のねらい
3学食堂の出入りに利用される扉を開放することで、開閉を手動で行った実験前と実験中で通過の時間にどれほどの変化が起きたのかを判明させる。また、ポスターによってピーク時間の通行を抑制するように訴えた心理的方略の効果も観測する。時系列に沿って利用者のカウントをすることで前述の非ピーク時間の利用(協力行動)を行う人間がどれだけの人数の増加も同時にカウントする。
1-2-2.扉の通過人数カウントの方法
実験前と実験中とで3学食堂内の扉の前に固定ビデオカメラを11:15から12:00の間設置し、撮影。時系列に沿って録画された映像を班員で検証・時間計測し、一人当たりの通過時間を計測する。通行時間ついてはドアを開けて通行するまでの時間を計測し、通行者に関しては時間ごとの通行者を単純計測する。
1-2-3.扉の通過人数カウントの計測結果
①通行時間の変化(図2)
実験前(青色のグラフ)では扉を自らの手で開け、通るという時間をカウントしたところ、一人あたり約8秒強の時間を費やしていたことがわかった。しかし、この扉を手で開けるという作業を省略させた実験中(桃色のグラフ)の扉開の機能改善では一人当たり約6秒の時間に短縮され、約3秒近い通過時間の短縮に成功した。
②通行時間帯の変化(図3)
実験前と実験中とでの通行者の割合を時系列に沿ってカウントすると実験前(青色のグラフ)では11:30から11:40の通行者が大幅な割合を占めていたが、実験中(桃色のグラフ)では11:20から通行者が増え始め、ピーク時間(11:30から11:45)にもある程度の利用者が集中してしまっているものの、通行者は若干減り、その通行時間はピーク時間(11:30から11:45)から若干早いものとなっており協力行動が行われていることがわかる。また非ピーク時間(11:45から12:00)にも若干ではあるが通行者増えたことがわかった。これに関しても扉の通行時間帯での協力行動がこの時間に起きたことがわかった。
2.機能改善
2-1.機能改善の評価のアンケートによる実施の狙い
今回行われた実施した機能改善に関して食堂利用者にどの機能改善を今後も続けるべきかを実験後の事後アンケートで回答してもらうことで、機能改善の貢献の程度を測る。
2-2.機能改善の評価のアンケートによる実施の方法
事後アンケートの質問項目のなかで「今後も続けるべきと思う機能改善はどれか」という質問で調査を行う。扉開放、机レイアウト変更、トレー置き場の変更、ショーケースの撤去、床にテープを張ることで注文内容ごとの誘導、mapの配置、配膳時のトレーのおき場所の指示の7つについて続けるべきものには「はい」、そうでないものには「いいえ」で回答してもらった。
2-3.機能改善の評価のアンケートによる実施の結果(図4)
縦軸に「はい」と答えた人数、横軸に各項目を置いた。グラフからもわかった通り、扉の開放がもっとも機能改善で評価されたことがわかる。
3.事後アンケート
3-1.事後アンケート分析の目的
心理的方略による協力行動誘発のための情報提供と学食内での利用のしやすさと混雑回避のための機能改善の2つを行った実験期間の後、事後アンケートの分析によってそれらの我々が行った協力行動誘発行動がどれほど認知されたのか、食堂の利用時間の変化や協力行動・行動意図といった実際の協力行動の有無、実験期間を経て食堂利用者は本当に混雑の緩和を感じたのかを中心とした設問により食堂利用者にアンケートを実施する。また、今回もアンケート回答者の学籍番号を記入してもらうことで事前アンケートの回答者が事後アンケートを答える機会があればその学籍番号を照合することで同一人物と決め、実験期間をへての方略による食堂混雑意識の変化や協力行動意欲への変化を測ることをねらいとする。
3-2.アンケート対象者
対象: 筑波大学学群生
日時: 6月9日(水)~6月11日(金)
実験群(チラシによる情報提供を行った)対象:
場所: 都市解析・数学科指導法・経済原論の3授業
人数: 85人 (男: 68人 ・ 女: 17人)
制御群(チラシによる情報提供を行わない)対象:
場所:数理解析
人数:29人(男:22人、女:7人)
以上の合計124名を対象として行った。対象となる実験群は、事前アンケートと同様の対象者に事後アンケートも行うことで前述のとおり、実験前後の心理的方略と機能改善による食堂混雑意識の変化や協力行動意欲への変化を測ることをねらいとした。また、新たにチラシ(協力行動を誘発するリーフレット)を配布しない制御群を加えた。事前アンケートを行った対象と同様の条件で最も3学食堂を昼休みに最も利用すると考えられる筑波大学の理工学群の生徒という条件から対象を理工学群の生徒とし、アンケートの実施が行いやすい社会工学類の生徒がもっとも履修している数理解析の講義を受講している生徒に行った。この事後アンケートでは事前事後の意識変化に焦点を置くものでなく、単純にチラシを使った情報提供を行わなかった対象者は協力行動者の数と協力行動をしようという意欲(行動意図)にどれだけ変化をもたらしたのかを測ることを目的とした。
3-3.アンケートの分析
(1) 情報提供が本当に協力行動の誘発に貢献したのか
3-3-1. アンケート分析の概容
今回われわれが行った心理的方略では対象者に「食堂の混雑時間を知らせることでその時間帯に食堂を利用すれば比較的、すいた時間で快適に食堂を利用することができる」という食堂利用時間の集中回避を促す情報をポスターとチラシ、食堂のテーブル上に設置する三角柱広告で行い、「食堂の利用時間を短くすることで多くの人が食堂を利用できる」という回転率上昇を誘発するポスターを設置した。これらの協力行動を誘発する情報はそれにどの程度影響したのかを分析する。
今回我々は情報提供という心理的方略による協力行動誘発と協力行動の発生プロセスとの関係を求めるために図5のモデルを仮定した。図5で示すとおり「ピーク時間に学食へ行くのを実際にずらした」という協力行動に至るために「ピーク時間に学食へ行くのをずらそうと思う」という行動意図が実際の協力行動に働きかけて協力行動を誘発させるものとし、その行動意図の発生のために心理的方略が機能するとした。また、心理的方略は行動意図の形成に影響しない場合においても直接にも実際の協力行動の誘発に影響するという可能性も考えられる。
まず、心理的方略のチラシ、ポスター、三角柱広告の3つが行動意図の形成への影響を求めるためにそれぞれの情報を「じっくり読んだ」「さっと目をとおした」「読んでいない」の3つの読了経験としてカウントすることでアンケート回答者の読了経験を把握するものとした。また、このアンケート項目に関して、3つの情報提供のうち存在は認知しているが読んでいないという条件の回答者には「読んでいない」と回答してもらい、存在を認知していないという回答者には無回答にしてもらった。
3-3-2. 重回帰分析によるモデルの導出
心理的方略の3つの情報提供が行動意図の形成への影響を求めるために我々は従属変数y1を行動意図、独立変数x1,x2,x3をそれぞれポスター、チラシ、広告と設定し、y1=a1x1+a2x2+a3x3という回帰直線を仮定した。そこで、独立変数の係数設定のための読了経験の数値化のために各情報の読了経験の程度「じっくり読んだ」「さっと目をとおした」の2つを値:1とし、「読んでいない」を値:0とした。(図6)
3-3-3. 実験群の重回帰分析による行動意図形成モデルの出力
3-3-2設定した重回帰分析を実験群の回答で行うと図7のような出力結果を得た。図7の出力結果から実験群においてleaflet(チラシ)係数:.214の値を有意確立:.022(t値:2.321においてp<0.05)で出力している。
よって、この結果から行動意図の形成には心理的方略のチラシによる情報提供が大きな要素となっていることがわかる。
3-3-4. 実験群の重回帰分析による協力行動形成モデルの導出
3-3-2で記したように「ピーク時間に学食へ行くのを実際にずらした」という協力行動に至るために「ピーク時間に学食へ行くのをずらそうと思う」という行動意図が実際の協力行動に働きかけて協力行動を誘発させるものとし、その行動意図の発生のために心理的方略が機能する。また、心理的方略は行動意図の形成に影響しない場合においても直接にも実際の協力行動の誘発に影響するという可能性も考えられる。という見解によって得られた行動意図に直接働きかける心理的方略の影響を測るために、3-3-3での実験群の重回帰分析による行動意図形成モデルをベースに係数設定のための読了経験数値化の方法は変更せず、新たな回帰直線を定義する。まず、(協力)行動をy2とし、行動意図形成モデルと同様に独立変数x1,x2,x3をそれぞれポスター、チラシ、広告と割り振り、あらたな独立変数に3-3-3で求めた行動意図y1を与えることで実験群の重回帰分析による協力行動形成モデルにy2=a1x1+a2x2+a3x3+a4y1を仮定した。
3-3-5. 実験群の重回帰分析による協力行動形成モデルの出力
3-3-4で設定した重回帰分析を出力すると以下のような結果が得られた。出力結果を見ると、行動誘発には三角柱(ad_tria)による情報提供と時間をずらそうと思ったという2つの変数がそれぞれ係数:.140(有意確立.047、t値:2.004のときp<0.05)と.683(有意確立.000、t値:9.870のときp<0.001)で出力している。このことから協力行動の誘発には三角柱広告による情報提供と行動意図に影響があることが考えられる。3-3-3、3-3-5の2つで得られた出力結果を図として表示すると図9のようなモデルが得られた。
3-3-6. 制御群の重回帰分析による行動意図形成モデルの導出
実験群の重回帰分析による行動意図形成モデルの出力と同様の方法で回帰直線を求める。
3-3-7. 制御群の重回帰分析による行動意図形成モデルの出力
3-3-6で設定した重回帰分析を出力すると以下のような結果が得られた。図10の出力結果からわかるように、制御群において行動意図の形成のために各心理的方略の情報提供は影響していないことがわかる。
3-3-8. 制御群の重回帰分析による協力行動形成モデルの導出
こちらも実験群の重回帰分析による協力行動形成モデルの導出と同様の方法で回帰直線を求める。
3-3-9. 制御群の重回帰分析による協力行動形成モデルの出力
3-3-8で設定した重回帰分析を出力すると図11のような結果が得られた。図11の出力結果からわかるように、制御群において協力行動誘発のために各心理的方略の情報提供と行動意図は実際の協力行動へと影響していないことがわかる。 3-3-7と3-3-9で得られた出力結果を図として表示すると図12のようなモデルが得られた。
3-3-10. 制御群と実験群での協力行動の差異の考察
今回、情報提供を数値化することで情報提供が行動意図を形成するプロセスと情報提供と行動意図の2つの数値化による2要素が協力行動に働きかけるプロセスを重回帰分析によって数式化することで求めた。この2つの出力結果から、実験群においては行動意図の形成のためにはチラシによる情報の提供が協力行動の誘発に統計的に有意であるということがわかった。この結果から、チラシをもらった授業直後に食堂の利用時間をずらす協力行動に移しやすい2限の授業の2つにチラシを配ったことと、食堂をもっとも利用する一年生の授業にチラシを配布したことが今回の行動意図の出力結果をもたらしたことが推測できる。このことから午前中の昼食に近い時間帯で行われる授業の食堂利用頻度が高い対象に情報提供を行うことができれば協力行動意図の形成に大きな成果が得られることがわかった。加えて、実験群の重回帰分析による協力行動形成モデルの出力から実際の協力行動誘発のためには三角柱広告と行動意図が統計的に有意であることがわかる。この結果から三角柱広告は食堂の食事を行うテーブル上に設置していることから、読了経験があるということは、すなわち、実験期間に食堂に足を運んだということになる。このことから、実際に自分の目で食堂の混雑を見て混雑を体験している人間は「利用時間をずらすことで食堂の混雑していない時間に食事ができる」という自分にとって有益な情報を受けて協力行動に移したということがわかる。また、三角柱広告以上に強い影響を持つ行動意図が存在していることから協力行動の誘発のためにはジレンマによって発生している問題を実際に対象者に体験させて、そこで比較的協力行動を起こしやすくも、協力者に有益な情報をあたえることが重要であることがわかる。
次に、制御群の心理的方略の協力行動誘発に対する影響を測るモデルからよみとれるように制御群では情報提供が協力行動意図と協力行動の二つともに影響していないことがわかる。このことからチラシなどの情報提供を与えられていない人間は食堂の混雑緩和のための協力行動に対する関心を持ちにくく協力行動をするとは考えにくいことがわかる。また、協力行動にあたる行為を行ったとしても、情報提供によって起こした故意の協力行動とは考えにくく、今後も協力行動をするとは考えにくい。このことから、自然発生的な協力行動は継続して起きるとは考えにくく、対象者が協力行動の重要性・有益さに気づくには時間がかかることがわかる。
(2)事前事後でピーク時間存在の認知は変わったのか
3-3-1'. 実験前後のピーク時間認知の変化の計測のねらい
心理的方略によって与えていた「ピーク時間の存在」の情報の認知を測る。この認知度が高いことがわかればピーク時間の食堂の混雑時間での食事を避けるために協力行動をする人間が増えることがわかる。
3-3-2'. 実験前後のピーク時間認知の変化の計測の方法
事前事後でアンケートを行った際に記述された学籍番号を同じ番号のもの照合して事前事後での変化を測る。設問に「ピーク時間があることを知っていますか。」という問いに対して「はい」「いいえ」の2選択で解答欄を設けて、ピーク時間の認知変化を測る。
3-3-3'. 実験前後のピーク時間認知の変化の計測の結果・分析
事前事後のピーク時間の認知変化を単純集計して図13 図14に記す。図13・図14から事前事後で大幅にピーク時間の認知が増えていることがわかる。この事前事後アンケートを行った対象群はチラシによるピーク時間の情報を与えたことから、この大幅なピーク時間の認知上昇はチラシによるところが大きいとわかる。この認知変化の上昇が統計的に有意かどうかを分析する。統計分析の方法としてこの「事前事後」と「認知しているか否か」でクロス表を作ることで、カイ二乗検定を行う。そして、図15 図16に出力結果を示す。この出力結果からすべての有意確率がp<0.001で有意であることがわかる。よって統計的に有意であることがわかる。
(3)事前事後で協力行動をした人間は食堂を混んでいると思ったか
3-3-1". 事前事後で協力行動をした人間の混雑意識の変化を読み取ることのねらい
心理的方略による情報提供によって協力行動を行った協力者が実際に食堂の混雑の緩和を感じたかを測ることで今後も協力者が協力行動をすることが見込めると同時に、実際に観測データで混雑の緩和は観測できたことからこの観測データを裏打ちするデータとなる。
3-3-2". 事前事後で協力行動をした人間の混雑意識の変化の計測方法
事前事後でアンケートを行った際に記述された学籍番号を同じ番号のもの照合して事前事後での変化を測る。設問に「この二週間食堂が混雑していると感じましたか。」という問いに対して「まったく感じない」から「とても感じる」のまでの5段階尺度で解答欄を設けて、その平均値がどの程度下がったかを出力することで混雑意識の変化を測る。
3-3-3". 事前事後で協力行動をした人間の混雑意識の変化の結果・分析
事前事後の食堂の混雑意識の変化を単純集計して図17に示す。この出力結果から、混雑意識に対する平均が下がっている。すなわち、食堂の混雑意識は下がっていることがわかる。この平均値の低下が統計的に裏打ちされたものか分析する。この2つを「対応のある2平均」とし「対応のあるサンプルのt検定」を行う。そしてそのt検定の結果を図18に示す。この出力結果が示すように事前事後でt=4.952のとき有意確率.000(p<0.001)で統計的に有意であることがわかる。
4.ヒアリング調査
4-1.ヒアリング調査の内容
3学食堂で働く従業員の方にヒアリング調査を実施した。
4-2.ヒアリング調査の結果
①ショーケースの撤去について
・利用者が通りやすくなった
・人がたまらなくなった
・無くなって淋しいかも
・ワンパターン食品サンプルの陳列よりも良い
②机のレイアウト変更
・通りやすくなった
③PIT SYSTEM
・以前に比べてよく流れている
・結構守らない人もいた
④お盆カート移動
・ピーク時間以外も、実験中の場所でよい
・お盆がおきづらい
⑤扉の開放
・危なくなくてよい
・通りやすくて、混んでいるときは特によい
・冷暖房をつけているときはどうなるのか
という、機能改善によるよいという評価だけでなく、働いている従業員の人々にしかわからない意見も聞けた。
グラフ・図表
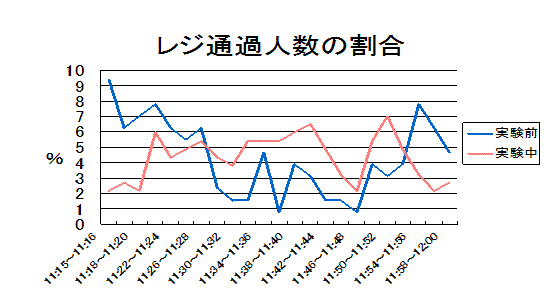
図1 レジ通過人数計測
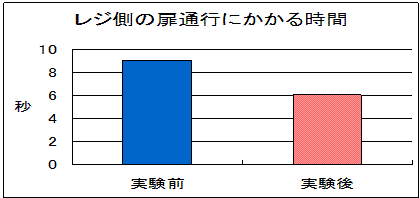
図2 扉の通行時間
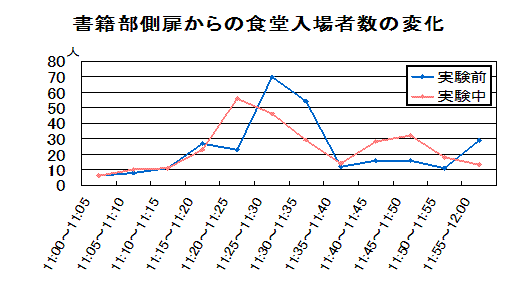
図3 書籍部側からの入場者数
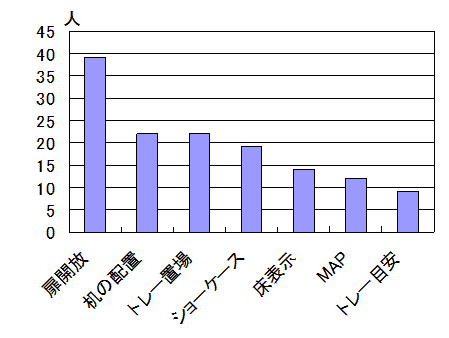
図4 機能改善評価
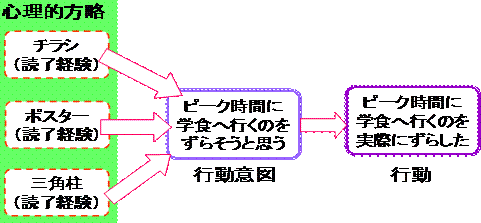
図5 協力行動発生プロセス
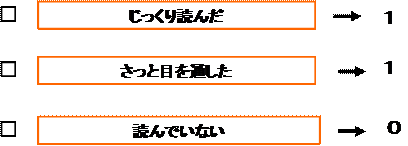
図6 読了経験の数値化
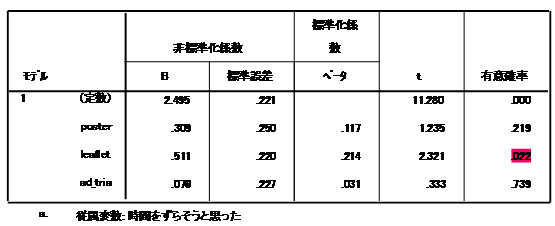 *ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
*ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
図7 実験群の情報提供への行動意図影響を測る重回帰直線出力結果
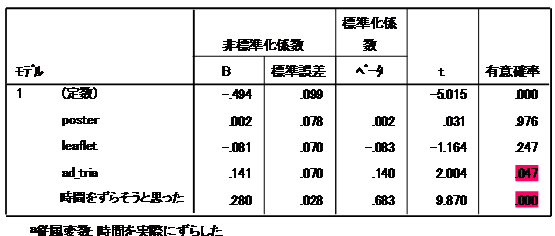
*ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
図8 実験群の情報提供への協力行動への影響を測る重回帰直線出力結果
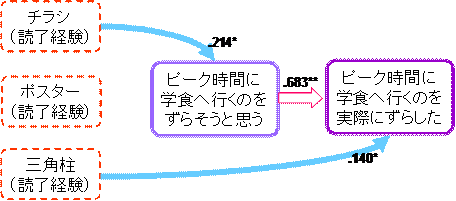
図9 実験群の心理的方略の協力行動誘発に対する影響を測るモデル
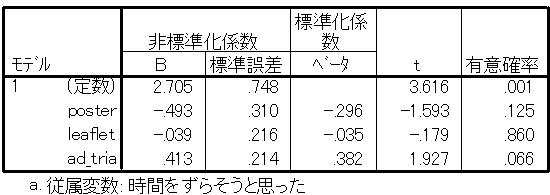 *ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
*ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
図10 制御群の重回帰分析による行動意図形成モデルの出力結果
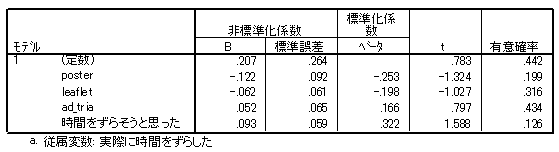 *ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
*ad_tria=三角柱、leaflet=チラシ、poster=ポスター
図11 制御群の重回帰分析による協力行動形成モデルの出力結果
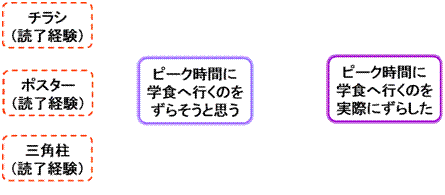
図12 制御群の心理的方略の協力行動誘発に対する影響を測るモデル
ピーク時間があることを知っていますか |
||
|
事前 |
事後 |
はい |
23 |
79 |
いいえ |
63 |
6 |
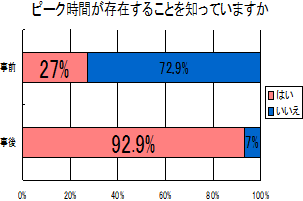
図14 事前事後のピーク時間の認知変化 グラフ
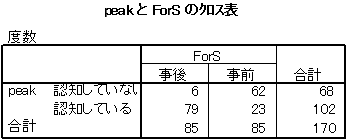
図15 ピーク認知のクロス表
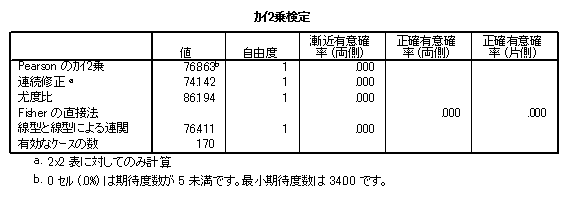
図16 事前事後ピーク時間認知カイ二乗分析出力結果
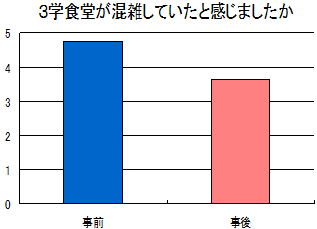
図17 事前事後で協力行動をした人間の混雑意識の変化の結果
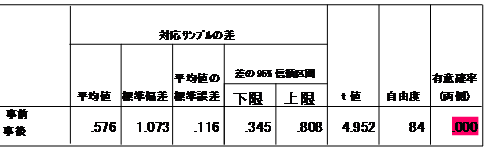
図18 事前事後で協力行動をした人間の混雑意識の変化の平均値のt検定