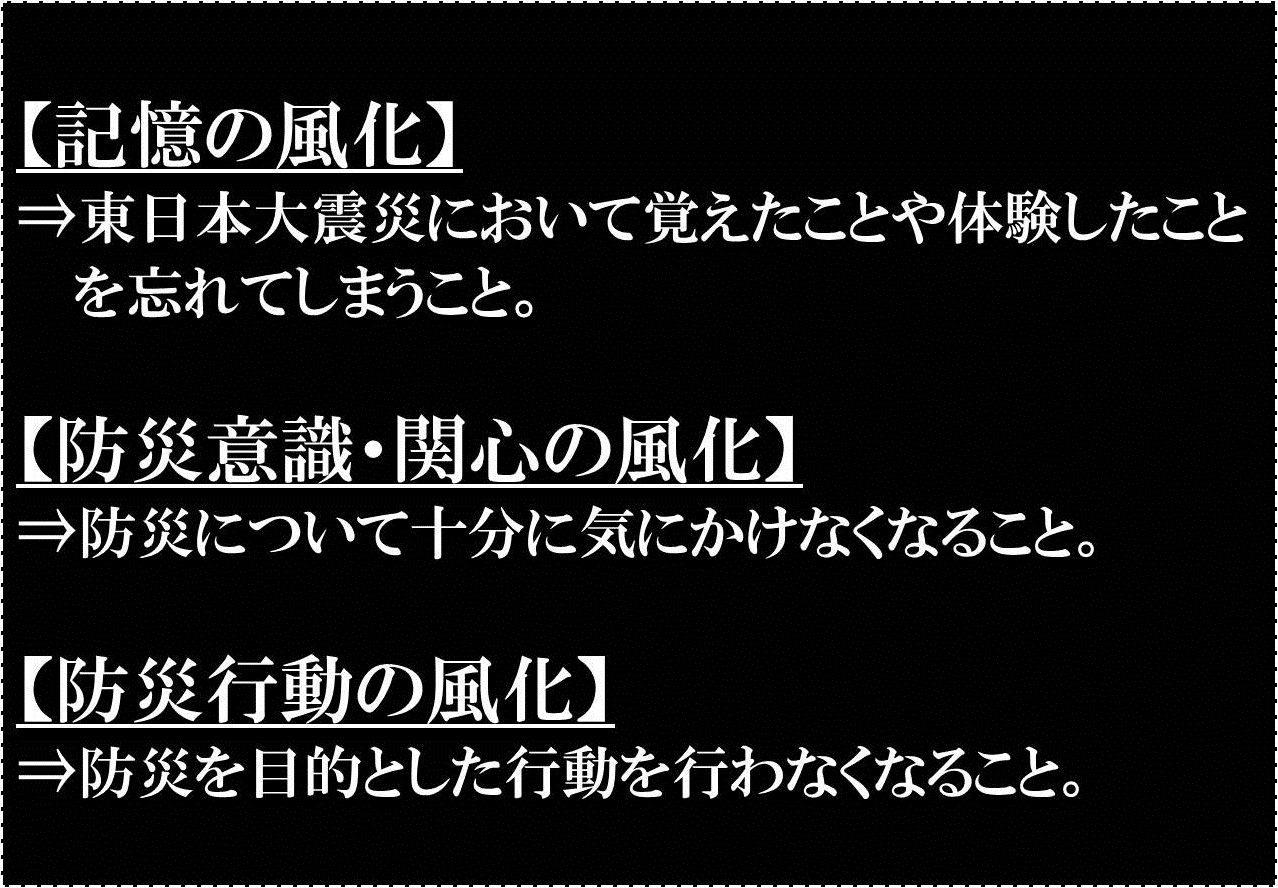2012年度都市計画実習防災班 |

序論
2011年3月11日の東日本大震災発生により、つくば市でも震度6 弱を記録、建物の損壊やライフラインの停止など人々の生活に深刻な影響を及ぼした。近年稀に見る大震災は人々の記憶に深く刻み込まれたと推測するが、1年が経過した現在、震災ボランティアの減少や震災瓦礫の受け入れの難航など、復旧支援が当時ほど積極的に行われていないのが現状である。その様な問題が発生する要因として「震災当時の記憶の薄れ」が関係しているのではないかと私たちは考えた。実際に災害に対する住民の記憶は時間の経過と共に希薄になっていくことが各研究で指摘されている。しかし、震災の記憶の薄れの実態や、防災意識・行動の実態に関する研究はあるが、それらが薄れる要因を深く研究しているものは少ない。そうした事情から、記憶の薄れの根本的要因や、そこから来る防災意識や防災行動の変化について深く興味を持ち、今回の都市計画実習にて調査するに至った。
そもそも、「風化」の本来の意味は「徳によって教化すること」であり、人々の共通知・当たり前のこととして語られなくなることを意味する。しかしながら広く一般の意味では、忘却の意味で使われることが多い。
そこで、私たちは震災における「風化」を「震災に関する記憶や防災意識・行動の時間経過による衰退」と定義し、防災意識や防災行動に支障をきたす要因と考えた。
ではなぜ、風化することを問題視する必要があるのだろうか。私たちは震災に関することが「風化」することで、被災地においては、震災ボランティアの減少や震災瓦礫の受け入れの難航により、被災地の震災からの復旧・復興の遅延が、比較的被害の小さかったつくば市においては、震災の記憶の薄れ、防災意識・行動の低下により地域防災力の低下が引き起こされると考えた。
そこで今回の研究を通してつくば市の風化実態を把握、そこから風化の要因を解明し、それに対し対策・改善策の提案を行い、住民の意識向上をはかる。そして、「地域防災力向上につなげるための風化抑止」を本研究の目的として研究を進めていく。

風化の定義
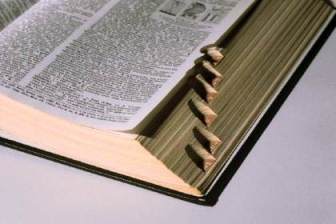
ふう―か【風化】
1.徳によって教化すること
2.地表及びその近くの岩石が・・・
出展:広辞苑第五版
前述した様に「風化」の本来の意味は「徳によって教化すること」であり、人々の共通知・当たり前のこととして語られなくなることを意味する。しかしながら広く一般の意味では、忘却の意味で使われることが多い。
そこで、私たちは震災における「風化」を以下の様に定義し、防災意識や防災行動に支障をきたす要因、または震災発生時の対応の遅れとなる要因の一つと解釈した。