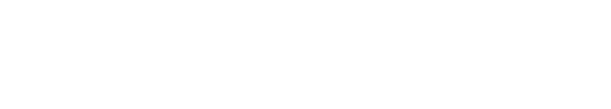提案の改善
改善➀:ペデストリアンデッキの歩行者専用化に関する提案の補強
・利便性の確保
1. 東西の移動の充実
この提案によって自転車の東西の移動が制限されるので、自転車利用者の教室付近へのアクセスをしやすくするためには、ループ道路の内側の移動需要が多い場所において、既存の道路の拡張や新設をすることが必要であると考える。
2. 駐輪場の位置の工夫
ペデストリアンデッキ沿いの駐輪場の利用を禁止し、その他の既存の駐輪場に利用が集中し感染リスクが高まることや容量の不足が懸念される。利便性の確保も同時に満たすために、徒歩3分以内(80m/分)で駐輪場から教室まで到達できる場所に設置することが必要であると考える。(3分の基準は班員のWillingness to walk)
・感染症対策
課題は授業開始前や終了後の発生集中交通による混雑である。発生集中交通量を確実に緩和させるためには、交通制度やデザインだけでは不十分であり、大学の講義形態の面からも考える必要性を感じ、以下の提案をする。
1. 講義のオンライン化(交通量の減少)
2. 休み時間の延長(集中の緩和)
改善➁:バスに関する提案の補強
アンケート調査での各提案の評価を踏まえ、段階的な提案を行う。
フェーズ1:初期投資が低いソフト面の提案
・バスロケーションシステム
バスの位置情報に、乗車率がチェックできる機能を追加する。混雑時を避けて利用したい人・時間に融通が付けられる人を分散することが可能になり、感染症対策としても有用性があると考える。
・既存路線と連携した利用者の分散
定員制と臨時バスの提案においては、感染症対策としての評価は高かったが、利便性の評価は低かった。そこで、大学循環バスの利用者を制限するのではなく、大学内を通過する他の既存路線への誘導を試みることで、利便性の確保と感染症対策の両立が可能になると考えた。
また定員制を導入する際には、通勤・通学時や雨天予報の日等の混雑が予想される日時においては、予め増便や臨時バスの待機による利便性確保を行うことを考慮する。それ以外の時間帯においては、利用者にバスロケーションシステムによる定員の空き状況の確認をしてもらうことで、臨時バスの利用や待機を最小限に抑えた、定員制の運用を考えている。
フェーズ2:ハード面の変更
・降車ボタンのIC化
バスの利用者からは利便性について批判的な傾向が見られたので、ヒアリングなどを行い、改善策を考えてからの提案が必要である。また、ゾーン制運賃でも非接触決済が可能であるため、これらの代替案も含めたより詳しい調査が必要である。
・連接バスの導入
フェーズ1で分散しきれない場合に導入を検討している。しかし、コストが大きいことは否めない。
フェーズ3:交通の枠を越えた提案
・時間制運賃
時差出勤やテレワークなど、働き方改革と連携する。慣習の変化には時間がかかると考えたため、これをフェーズ3として長期目線での提案を行う。