事前調査
背景・目的を踏まえ,以下の事項について把握するための事前調査を行った。
- つくば市の落書きの現状
- 落書きによって生じる問題
- 落書きが行なわれる理由
- 落書きに対する既存の対応策とその効果
1.現地調査
今後の調査方法を検討するために,つくば市内の落書きの実態をおおまかに把握する目的で,筑波大学及びつくば駅周辺にて現地調査を行った。
 調査概要
調査概要
日程:2014年4月18日~21日
方法:班員全員によって市内を観察し,落書きの状況や特徴を調査する。
 調査結果
調査結果
落書きは交通量の多い道路沿いや,ループ道路沿い案内板など通行者からよく見える目立つ場所に集中していた。 落書きは一定の範囲に複数が集中しているケースが多く,そのような場所ではゴミのポイ捨てなども見られた。 落書きの内容はほとんどがアルファベットを模したような絵柄であった。 同じ絵柄の落書きが複数箇所にされている例が多く,同一犯または同一のグループが複数の落書き被害に関わっていると推定された。
 ◀ 筑波大学構内の落書き
◀ 筑波大学構内の落書き
2.文献・資料による調査
犯罪に関する文献・論文とつくば市の発行する資料から,落書きに関する基礎的知識を以下にまとめる。
1) 防犯環境設計(CPTED)について
CPTEDとは,環境の適切なデザインが犯罪に対する不安感と犯罪を減少させ,生活の質の向上を導くことができるという考え方である。 繁華街には不特定多数の人が集まるので,匿名性の高さに起因する公共空間のマナーの低下が見られることが多いが, ハード面の改善策(監視性の確保,領域性の強化,接近の制御,被害対象の強化), およびソフト面の活動展開(防犯パトロール,落書き消し・清掃活動など)による「ミクロな視点」の防犯対策が有効であると考えられる。
2) 落書きがされる理由
落書きは,犯人の自己顕示欲の表れである。よって,よく人目につくところは標的にされやすい。 また,すでに落書きのある場所では,連鎖反応によって新たな落書きがされることが多い。
3) 落書きの分類と特徴
落書きにはいくつかの種類があり,その種類によっても目的が異なるとされる。下図にその分類を示した。
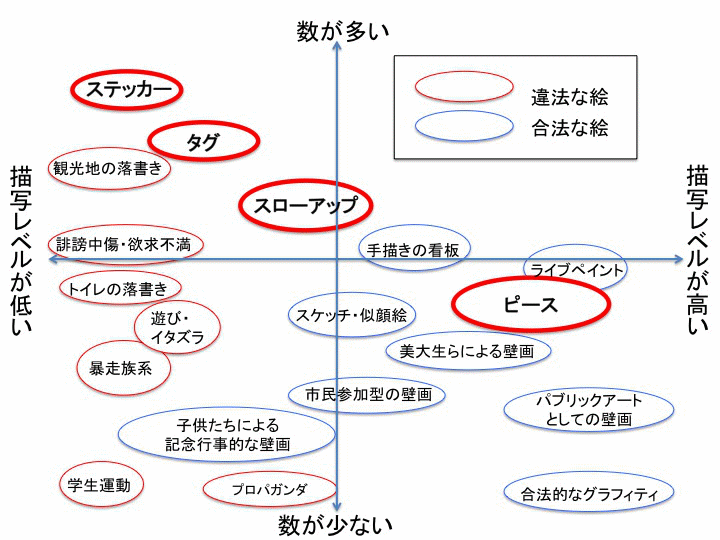
▲ 落書きの種類 (出典:小林茂雄(2009)『街に描く―落書きを消して合法的なアートをつくろう』)
今回調査の対象とするのはグラフィティと呼ばれるもので,図中に太線で囲った4種類に大きく分類される。 それぞれのグラフィティの特徴は以下のとおりである。
①タグ(タギング)
グループ名や個人名を表すマークを単色のスプレーやペンなどで書いたもの。
グループの縄張りを示す目的で,非常に短時間で書かれる。
②ステッカー
タグに用いられるマークをシールにしたもので,これも縄張りを示す目的で貼られる。
③スローアップ
アルファベットなどの文字に丸みをつけた図形を,一色以上のスプレーで比較的短時間に書いたもの。
④ピース
マスターピースの略で,最低でも3色は含まれる芸術性の高いグラフィティ。
時間をかけて書かれ,作成者のメッセージや純粋な創作意欲が表現されていることが多い。
4) 落書きへの対応策とその効果
⑴消去活動
最も基本的なボランティアによる落書きへの対応策である。
しかし落書きは再発率が非常に高く,消去してもすぐに同じ場所に書かれることが多い。
⑵リーガルウォール
一部のグラフィティが純粋な創作意欲の現れであることを考慮して,合法的に落書きができる壁のこと。
この方策は短期的には機能しても,リーガルウォールが埋まるとむしろ周辺に落書きが増加し,
長期的な対策にはならないことが先行研究で明らかになっている。
⑶壁画・啓発ポスター
再発を防ぐ方策としては,落書きの多発している箇所へあらかじめ壁画を描いたり,
啓発ポスターを貼って余白を無くし,書かれにくくするなどがある。
東京の町田市では市内数カ所で壁画の制作,多摩市では啓発ポスターの掲示などを行い,再発防止に成功している。
3.インタビュー・ヒアリング調査
これまでの調査を踏まえ,今後の落書き対策に必要な情報を収集するため,インタビューやヒアリングによる4つの現状調査を行った。
 調査概要
調査概要
1.インタビュー調査
対象:筑波大学生54人
日時:2014年5月2日(金)11:30~13:00
場所:筑波大学2学エリア,3学エリア,中央図書館
目的:つくば市で生活をする人の落書きに対する関心調査
2.ヒアリング調査
⒜
対象:つくば市役所 環境生活部環境保全課 御田寺義朗氏,柳田奈苗氏
日時:2014年5月2日(金)16:00~17:00
場所:つくば市役所
目的:落書き消去活動に対する行政による対応の現状調査
⒝
対象:柴原不動産
日程:2014年5月11日(日)
方法:電話によるヒアリング
⒞
対象:つくば市きれいなまちづくり実行委員会
日時:2014年5月13日(火)18:30〜19:30
場所:Right-on つくば本社
目的:落書き消去活動の現状調査
方法:きれいなまちづくり実行委員会会議に参加,環境美化推進委員長の五十嵐氏より書面による回答
⒟
対象:つくば警察署
日時:2014年5月21日(水)
目的:落書きに対する警察側の対応を調査
方法:電話によるヒアリング
 調査結果
調査結果
これらの調査でわかったことを以下にまとめる。
- 筑波大生の落書きに対する意識は低く,約9割の人は落書きの清掃活動があることを知らない。
- 市では,公共物への落書きのうち,目立つものを優先的に清掃している。再発への対策としては,上から書かれにくいペンキを使用している。
- つくば市・つくば青年会議所・ライトオンが協力して運営する清掃活動団体であるきれいなまちづくり実行委員会では年に 数回落書きの消去活動を行っているが,活動には1回で30~50万円の費用がかかる。
- 市の落書き消去に対する再発率は,平成24年度,25年度において100%だった。
- 使われていない建物は落書きがされやすく,消去してもすぐにまた書かれてしまう。
- 市や委員会では再発ポイントに周辺の学校と連携して壁画を制作する案が出ているが,万が一その上に落書きが再発した場合, 小中学生にはショックが大きいという問題がある。その問題に対応し,小学生による落書き防止のポスター掲示も検討している。
- 警察では被害届の出たものにしか対応できないため,市内の落書きに逐一対応することは出来ない。