1−1 計画人口
土浦市の人口は着実に増加しつづけ、昭和40年代後半に10万人をこえ
、平成9年では住民基本台帳による人口は13万4107人である。今後
は自然増加の他に、中心市街地や周辺部での住宅開発、土地の有効利用、
周辺部の都市的土地利用の進行により今後も人口が増加していくことが見
込まれ、2010年における計画人口は15万人と想定する。
1−2 人口推計
今回の推計では、コーホート要因法を用いて土浦市の将来人口を推計し
た。使用したデータは、基準人口は土浦市の1997年の住民基本台帳に
よる人口を用い、出生率・生残率・移動率は厚生省人口問題研究所により
推計された茨城県のデータを用いた。この方法により、過去のトレンドか
ら現在の状態を基に将来の人口が推計される。推計結果は以下の表のよう
になり、2010年における人口は約14万7000人と推計された。土
浦市は住宅開発、土地の有効利用、周辺部の都市的土地利用が進行してい
るため人口の増加が続き、厚生省人口問題研究所の中位推計によると全国
の人口は2011年頃がピークであると推計されているのに対して、土浦
市の人口は2020年頃がピークであると推計された。しかし、ピーク時
の人口は約15万1000人と推計され、2010年の推計人口の約14
万7000人から少しの増加にとどまっている。目標年次である2010
年頃までが人口が急増する期間である。したがって、長期的にも対応でき
る都市基盤の整備を考えると、2010年の将来像を考える上で、人口フ
レームは計画人口を15万人とすることが適当であるとした。なお推計方
法の詳細は資料編を参照。
表2−1 総人口の推移
| 年 |
1997年 |
2000年 |
2005年 |
2010年 |
| 総人口(人) |
134,107 |
137,224 |
142,615 |
147,222 |
1997年は実測値
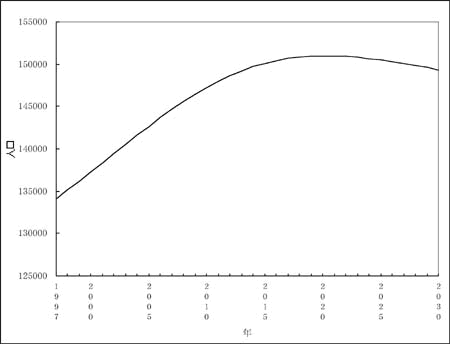 図2−2 土浦市総人口予測
図2−2 土浦市総人口予測
1−3 年齢3階層別人口
年齢3階層別人口の推計結果と構成比は以下の表のように推計された。新
規の住宅地開発による40歳代以下の人口流入が多いと思われるため、1
5〜64歳の構成比は2010年までを通して全国よりも高くなっている
。逆に、65歳以上の割合全国水準と比べて1〜2%ほど低くなっている
。この傾向は将来も続き、土浦市は全国水準に比べて高齢者の割合が低い
都市である。しかし、1997年に13.6%であった65歳以上の構成
比が2010年には19.6%になると推計され急激な高齢化が進むと予
想される。さらに2020年代、2030年代は24.0%程度になると
推計される。2010年には5人に1人、さらに将来には4人に1人が高
齢者という時代が来ると予想されるので、十分な高齢化対策が要求されて
いる。15〜49歳の各歳の出生率を合計した合計特殊出生率は、199
7年で約1.505であり1.5以下まで低下した後、2010年には1
.612まで高まる。これは、女性が一生の間に何人の子供を産むかを示
す指標であり、人口を維持するには2.08以上が必要であるとされてい
る。したがって、今後は少子化が進むことが予想され、総人口は推計によ
ると2020年頃をピークに減少していくであろうと予想される。移動率
は10歳代でマイナスがあり10歳代は流出が多いが、その他はプラスで
あり全体としては流入している。生残率は男女ともに65歳以上の高齢者
で2010年までにおよそ0.02〜0.06高くなっていて、今後長寿
化が進むものと予測される。
表2−3 年齢別3階層別人口と構成比
| 年 |
1997年 |
2000年 |
2005年 |
2010年 |
0〜14歳 人口(人)
構成比(%) |
20,697
15.4 |
20,601
15.0 |
22,003
15.4 |
23,528
16.0 |
15〜64歳 人口(人)
構成比(%) |
95,162
71.0 |
96,512
70.3 |
96,949
68.0 |
95,404
64.8 |
65歳以上 人口(人)
構成比(%) |
18,248
13.6 |
20,111
14.7 |
23,662
16.6 |
28,290
19.2 |
| 総人口(人) |
134,107 |
137,224 |
142,615 |
147,222 |
1997年は実測値
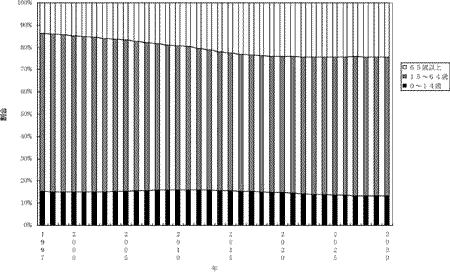 図2−4 土浦市年齢3階層別人口予測
図2−4 土浦市年齢3階層別人口予測
1−4 世帯数
平成7年の世帯数は約4万5000世帯で、1世帯当たり人数は2.89
人である。今後、合計特殊出生率はわずかに上昇することが見込まれるが、
核家族化が進むものと予想され、2010年における世帯数は約5万200
0世帯と予想される。
表2−5 世帯数
| 年 |
1995年 |
2000年 |
2005年 |
2010年 |
| 総人口(人) |
132,246 |
137,224 |
142,615 |
147,222 |
| 世帯数(世帯) |
45,744 |
48,149 |
50,753 |
52,206 |
| 世帯人員数(人) |
2.89 |
2.85 |
2.81 |
2.82 |
1995年は実測値、資料:国勢調査
|