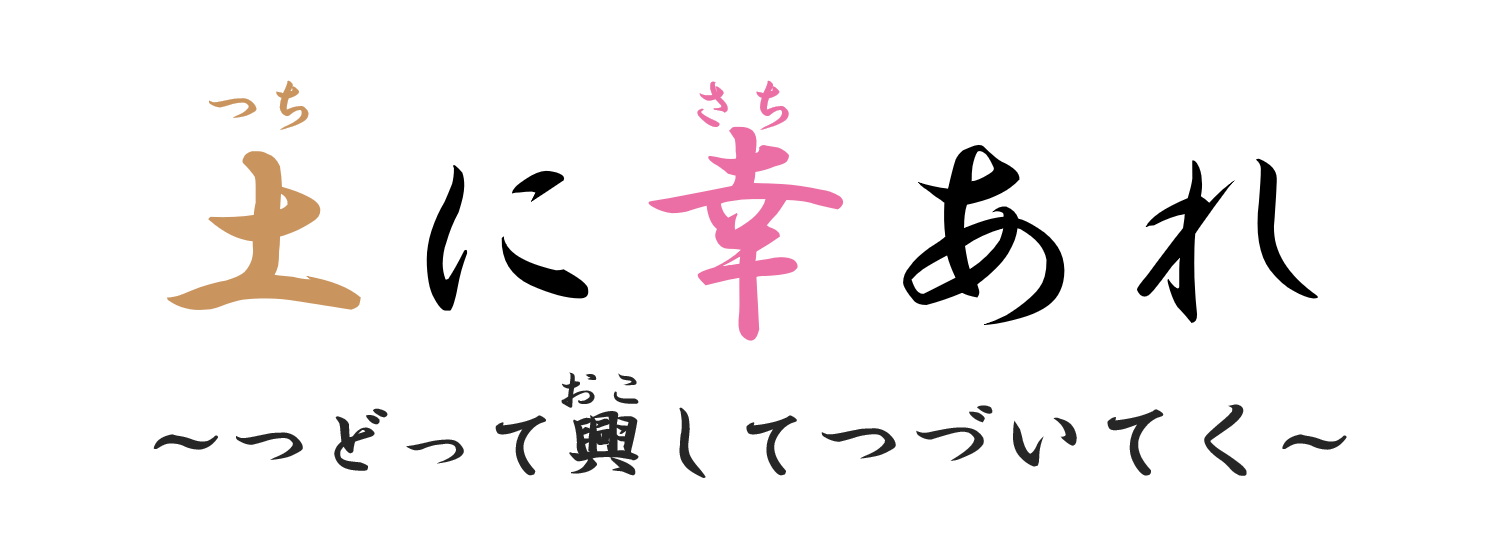部門別構想
基本構想を実施した際に、課題班で取り上げた各課題に対しどのように対応するかを述べていきます。
人口・財政
CMAを導入することで、土浦市内の財政問題は、土浦市民の声を十分に反映した形で財政健全化を達成することが可能になります。
また、中心部での魅力化を行うことで中心部の地価が上昇することや、CMAの活動により、土浦市内の地区の地価が上昇する可能性もあります。 こうした地価の上昇もまた、財政の健全化の一助になります。
さらに、人口に関してもCMAによって地域愛着が創出され、人口流出に歯止めをかけることが可能になります。 流失の歯止めは魅力化によって土浦が魅力的になることでも可能です。
そして、財政に余裕が出始めれば土浦市として保育や教育に投資を行うことが可能になり、より子育てがしやすい状況を生み出すことも可能になります。 子育てがしやすい環境が整えば、土浦市内での子育て世代が増え、人口減少に歯止めを打てる可能性もあります。
交通・都市構造
CMAの導入によって、財政が健全化されれば、市が提供する公共交通サービスに関しては今後も持続的に行うことが可能になります。
各CMA単位で年間の乗車人数を決め、あらかじめその人数が乗車したと考え、費用をあらかじめバス会社に支払うことで、住民は年間バスを定額で乗り放題にでき、公共交通を使うインセンティブが作りやすくなります。
また、交通不便地域のCMAでは例えば乗り合いタクシーを集落単位で乗車し、移動のロスを減らすなど独自の使いやすくなるようなサービスの形を提案することで、より利便性を向上させることが可能です。
一方で、現在進められているようなコンパクトシティのような空間の再編成を大きい単位で行う必要がなくなります。
CMA地域内でコンパクトすることも、拡散して費用を負担し維持していくことも可能です。
そのため、市民に強制的に負担を強いることなく、住民自身が判断してくことで、土浦市を持続させて行くことが可能になります。
さらに、中央部でのトランジットモールにより公共交通の利便性や必要性が上昇し、利用促進につながります。 加えて、トランジットモールは駅前空間の渋滞も緩和します。
最後に、駅前空間から始まる中心地の利用促進は、中心部の空洞化を抑制できます。 中心部の魅力化は回遊性の上昇も伴うので滞留空間の確保にもつながります。
住環境
住環境に関してはCMAを導入することによって、住民自身が自分たちの手で一定水準は維持することが求められます。
これは住民にしかわからないような問題を解決できることを示しており、これまで行政が満足に行えてなった公園整備や二次林の整備など、住民自身が関わって行うことで臨機応変な対応が可能になります。
また、公私住環境に関する活動を通して地域内のコミュニティの強化をすることも可能です。
工業・商業・観光
中心地での魅力化の一つのステップである駅前駐車場の活用を行うことで、様々な形の商業を呼び込めます。
商業の誘致の効果として、にぎわいだけでなく、雇用の創出も可能になります。
また、駅前駐車場の活用は、魅力化されていく駅前への居住のニーズへの受け皿ともなります。
さらに、CMAから発せられる独自ニーズに対応したサービスを提供する企業の受け皿となることも可能です。 一連のプロジェクトを行うことで中心の高密化のみならず、雇用の創出から、土浦を潤すことが可能になります。
防災・環境・農業
防災のような広域事業に関しては、行政主体でこれまでのように対応していきます。
防災に関してはハードの整備よりもソフトの整備を今後は重点的に行っていく必要があります。
CMAの導入によってまちづくりを行っていくうえで居住地区の危機度を改めて認識することで、自助の促進ができると考えられます。
さらに、コミュニティの強化により、共助の促進も図ることが可能になります。
また、液状化や洪水氾濫危険域である中心部に関しては、駐車場の活用の際に立つビルに避難場所とすることが可能な空間を作ること及び、保存食の備蓄を義務化することで一定程度対策していくことが可能です。
環境問題に関しては現在行われている宍塚での環境教育を、自然資産が豊かな新治地区のCMAが市内向けに新たに行い、その貢献度に応じて、費用削減目標を緩和するなどの策をとることで広く環境教育を行うことが可能になります。 また、こうした環境教育はグリーンツーリズムとしてCMAが独自に展開し、利益を得ることで、自分たちの地域への資金とすることも可能です。
農業に関しては、複数のCMAが協力し、耕作放棄地をまとめ、6次産業拠点の整備を行うことなどが考えられます。 また、CMAが耕作放棄地などを使い、身近な緑としてコモンガーデンを運営し、農業従事者の育成等ができます。
公共施設再編・インフラアセットマネジメント
インフラに関しては上下水道といった広域性が高く、一定水準以上の技術力が求められるものは行政が継続して提供していきます。
公共施設や児童館といった施設はCMAが選択して削減できる項目として計上したため、地域にて機能が重複しているこれら文化施設に関しては、CMA地域内で複合化等により、負担金の削減が行われると想定されます。
また、公園の整備などはすでに記述した通り、CMAが整備運営などを行うこととします。
さらに、消防や、警察、教育といったサービスやセーフティネットとしての役割がある公共住宅に関しても財政が健全化したことによって市が継続して行うことができるようになります。 継続する際にはCMA同士の連携、CMAと市の連携を考慮し施設の再配置を決定していくこととします。
まとめ

「つどって」の部分を達成するCMAによるまちづくりを行うことで、土浦市の財政問題が解消され、安心して「住める土浦」になり、20年後、その先もずっと土浦が続いていける頑丈な土壌を作り上げることができます。
そして、「興して」の部分を達成するまちなかの魅力化によって、土浦市の中心地が土浦市民からだけではなく、他の地域からも来たくなるような魅力と活力あふれた全市民にとっての「住みたい土浦」を作ることができます。
そして、土浦市で、この「つどって」「興して」の2つを実現することで、持続力があり、人の活力と場所の魅力を生かし切れる「つづいてく」土浦が実現できるのです。