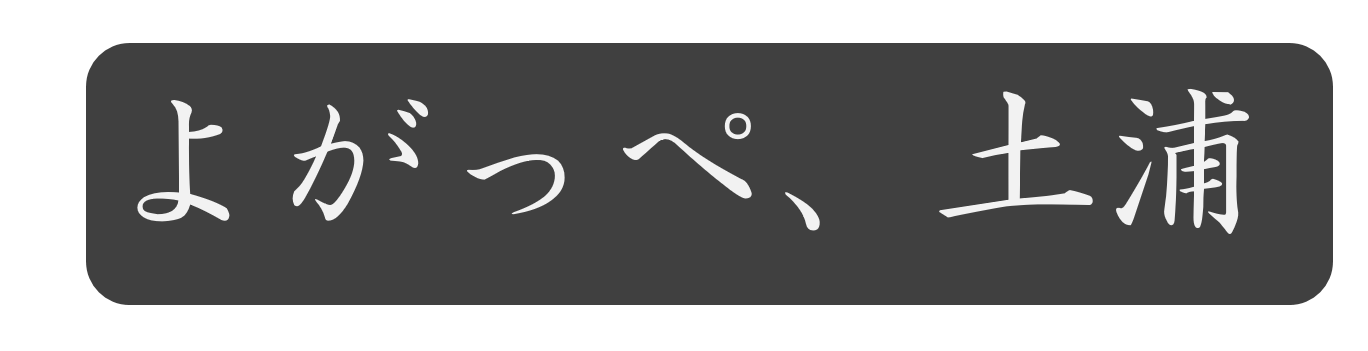地区別構想
土浦市全体を、中学校区などをもとに下図のように4つの地区に分ける。JR 常磐線の駅を拠点に、神立駅やおおつ野地区を中心とする「北部地区」、土浦駅を中心とする「中央地区」、荒川沖駅を中心とする「南部地区」の 3 つの地区に分けた。そして、旧新治村の「新治地区」を加えた 4 つの地区とした。

中央地区
中央地区は JR 常磐線土浦駅や市役所を有している。また、土浦花火が開催される地であるなど、中央地区は土浦の中心として機能する地域である。駅周辺には図書館や市役所など、行政サービスが集積している。
城下町として古くから県南地域の中心としての役割を担ってきた。しかし、近年は郊外ショッピングモールの開発やつくば市の発展により、車でアクセスしやすい郊外の大型ショッピングモールへ顧客が流出してしまっている。その結果、中心市街地で空き店舗が目立ち、人口が減少し住宅地においても空き家が増加している。また、霞ケ浦や桜川の水資源に恵まれている地域だが、水辺への市民の馴染みが浅いと考えられるため、空間の有効利用による活性化が必要である。
問題1
土浦駅周辺の大規模店舗の撤退が相次ぎ、中心地としての賑わいが失われている。
解決の方向性
中心市街地エリアにあるモール 505 を大規模改修し地元の住民が利用しやすい店舗を配置することで、改修後のモールに自然と人が集まる施設にし、活性化を図る。
問題2
土浦市洪水ハザードマップにおける浸水域に土浦市役所、土浦駅が位置している。
解決の方向性
市民への防災意識向上のために防災教育を行う。
問題3
市民一人当たりの公園面積が不足している。
解決の方向性
モール 505 を改修し、公園広場を整備する。
問題4
観光客は日帰り観光がメインで、市外からの観光で外貨を稼げていない。
解決の方向性
中城通りを活性化させ、宿泊客を呼び込む。
モール 505 や中城通りなどの商業施設の発展、そして中央地区の中心市街地としてにぎわいのある地区を目指す。モール 505 の改修後には広場を整備することにより、ゆとりのある空間にマルシェや屋台が出店されベントが開かれ、市民の憩いの場となることを目標とする。
北部地区
土浦市北東に位置する北部地域は、北はかすみがうら市、南は霞ケ浦に位置し、JR 常磐線神立駅を含む土浦市の北部拠点を形成している。霞ケ浦湖畔の広大なレンコン畑ではレンコン栽培が盛んにおこなわれ、その生産量は日本一を誇り、市の特産品を代表する農作物となっている。
おおつ野地区では新興住宅地の開発や企業誘致により発展し、今後も人口増加が見込まれる地域である。土浦協同病院は茨城県内で最大級の病院であり、おおつ野地区の「メディカルタウン」としての発展が予想される。
おおつ野ヒルズに 2 区画の空きがあるため、ここに医療系オフィスを誘致する。
おおつ野ヒルズでは医療系オフィスの誘致によるメディカルタウンとしての更なる発展を目指す。北部地域の耕作放棄された田やレンコン畑について市が農地空き家バンク制度により適正に管理し、農業の活性を目指す。
南部地区
市の南部に位置し、JR 常磐線荒川沖駅が地区の拠点となっている。東は阿見町、西はつくば市、南は牛久市との市境になっており、三方が他市町と隣接している。荒川沖駅は市内 3 駅のうち最も東京方面に近いため、常磐線を利用して東京方面に通勤通学する人は必ず通過し、市内と東京方面との中継地点となっている。荒川沖駅周辺には住宅地が多く存在しており、家族世代が多く居住している。
荒川沖駅周辺は道が細く入り組んでいて、2008 年 3 月19 日と 23 日に連続殺傷事件が起きたように、犯罪の発生につながってしまう恐れがある。
駅周辺には幹線道路が交差しており、小中学校や公民館など、地域の拠点となる施設が大通りに隣接しているため、安全面への課題があげられる。
一戸一灯運動とゾーン 30 の導入により、事件・事故が起こりにくい環境にし、安心安全なまちづくりを目指す。
新治地区
市の北西に位置し、2006 年に土浦市に編入された地区である。地区北部には小町の館、朝峠展望公園など、地区の自然を活かした観光施設が立地している。平地は広く農地として利用され、良質な水田を活かした稲作のほかに、畑作による野菜や花き類の栽培、果樹の栽培もおこなわれている。市内で特に高齢化率が高い地域であり、農家の高齢化や後継ぎ不足により農業離れが進んでおり、耕作放棄地が年々増加している。
問題1
新治地区では、藤沢小学校、とりで小学校、山ノ荘小学校が閉校になり、跡地の活用について課題となっている。
解決の方向性
山ノ荘小学校を改修し、宿泊施設にする。
問題2
耕作放棄地があり、管理不全による景観の悪化、雑草や病害虫の発生などの問題がある。
解決の方向性
農地空き家バンクにより適正に管理する。
問題3
公共バスの利用方法が複雑で、利用率が低い。
解決の方向性
きららちゃんバスの利用促進を行う。
新治地区では、地区の主要産業である農業を中心としたまちづくりを実施する。農家数・後継者数の減少や高齢化の進行により取り巻く環境は年々悪化している。国や市により新規就農者を増やすための取り組みは行われているが、土浦市全体で 1 年間に新規就農者は 10 名程度しかおらず、あまりうまくいっているとは言えない状況であり、このままの体制で農後を続けていくのは非常に厳しい状況であると言える。そこで、先ほど提案した農地空き家バンクの導入により、耕作放棄地の減少、新規参入者の増加を目標とする。
また、公共交通網の制度を変更し周知を行うことで交通弱者にとっても便利な交通により安心なまちづくりを行う。
農業が盛んである地域性を活かし、旧山の荘小学校跡の校舎を改修し、農業体験が可能な宿泊施設を設置する。施設の効果として、新治の観光客の増加や土浦産の特産物の周知などが挙げられる。