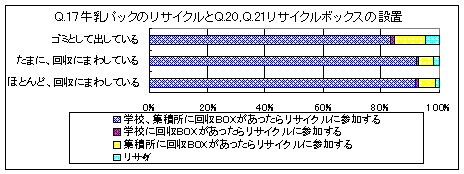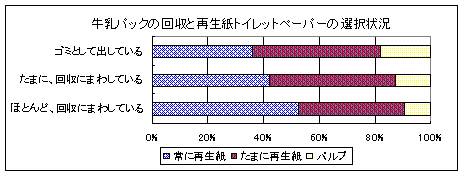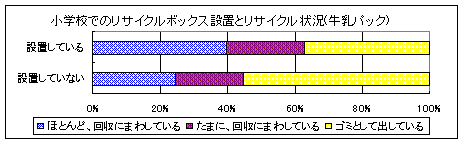�����Ύs�̐����ۑS�Ɗ�����ɑ����ā�
��R�� ��������ɂ������ā�
����
�ڎ���
3-1 �ړI�y�ѕ��@
���Ύs�́A�u�������s�s�v���������Ă��邪�A�s���ɑ��Ă̊�����
PR�����Ȃ��B�܂��AISO14001��F���ꂽ�����̂̏��w�Z�͊����炪�i��ł��邱�Ƃ�������A
�����ł����Ύs�̎��g�ݏɋ^����������B�����ŁA���̎��K�ł͂��Ύs��ISO�F�؍�
�̎����̂ɂ�����A�s������w�Z���s���Ă��������ɂ��Ă��ꂼ�꒲������Ɠ����ɁA��
�����炪�Z���ɗ^����e���ɂ��Ă����ׁA�s���E�����ɑ��ēK�Ȋ�����̎�i�ɂ���
�l�@����B
3-2 �s�����s��������ɂ���
(1) �����ΏۂƂ���ISO�F�؍ς݂̎�����
��t�����䒬�A�V������z�s�A�啪�����c�s
�����̂R�����̂́A�h�r�n�P�S�O�O�P����{�̒n�������̂̒��ŁA�����ɔF���ꂽ��
����ł���B�����̎����̂̊�����ɂ��Ē��ׁA���Ύs�̌���ɂ��čl����B
(2) �s���ɑ��Ă̊�����̓��e
�h�r�n�P�S�O�O�P�������ɔF���ꂽ�R�����̂̎s���ɑ��������̓��e�ɂ́A���L��
�悤�Ȃ��̂���������B
- ���R�ώ@����J�Â���(�N4��) �F ���䒬
- �����p���̌��w�K����J�Â���(�N4��) �F ���䒬
- ��Ȃ�قǍs���u���(������)�ɂ��u�����s��(����) �F ���䒬
- ���e�i�������ɂ��āA��炵�ƃS�~�ɂ��āA�S�~�̃��T�C�N���ɂ��āA�S�~��
���ʍ��ɂ��āA�n�����ɗD���������ɂ��āA�͐�ɂ��āA�n�������ɂ��āA
�h�C�c�̊��ɂ��āA���j
- �����ق�ʂ��ď��w�����W���A�u�������������v�����{����B �F ���c�s
- (���e�F�s���̉͐�ŁA�����������ɋy�ڂ��e���Ȃ�тɐ��������ɂ��Ċw�K����B)
- ���w���Ƃ��̕ی�҂�ΏۂɁu�e�q�S�~�w�K�c�A�[�v�����{����B �F ���c�s
- (���e�F�S�~�X�e�[�V������A�s�@�����ꏊ���тɃS�~�ɊW����{�ݏ�����s���A�S�~
�̌��ʂɂ��Ĉӎ��̍��g��}��B)
- �s�̍L��Ŋ��W�̋L�����f�ڂ��A�s���Ɋ��ӎ��̌[�����s���B �F ���䒬�E���c�s
- ����̔��s�B �F ��z�s
- ������֏o�����A���ۑS�̂��߂̐�������s���B �F ���䒬�E���c�s
- ���Ɋւ���u����̎��{�B �F ��z�s
- �o���u���̒��Ɋ�����Ɋ֘A������̂��܂߂�B �F ���c�s
���̑��A�����̐E���ɑ��Ă̊�����Ƃ��āA�u���P��C�s�E���ɂ��
���匤�C�O���[�v���A���Ɋւ���e�[�}��ݒ肵�āA���_���s���B�i���c�s�j�v�Ƃ������̂�A
�����̐����̈ꕔ�Ƃ��āu�엧�Ċw�K�Ŕ̐ݒu(�N1����)�i���䒬�j�v�Ƃ������̂�����B
(3) �w�Z�̊�����Ɋւ��Ă̑Ή�
�h�r�n�P�S�O�O�P�������ɔF���ꂽ�R�����̂̊w�Z�̊�����Ɋւ��Ă̑Ή����܂Ƃ߂�ƁA���L�̂悤�ɂȂ�B
- ���ނ̍쐬
- �����G�r���ɂ�鐅�������̏���������������w���p���� �F ���䒬
- ���ݏ����̂������ɂ��Ă܂Ƃ߂����w4�N���p�Љ�ȕ��ǖ{ �F ���c�s
- �w�Z�ŁC�����̗̂��O����R�����炵�ɐ������s�s��̎��H�𐄐i �F ���䒬
- (���H��F���݂̌��ʉ��C�ȃG�l���M�[�C�Đ����̗��p�C�n���������S�~�[����A
�w�Z�ō͔|�����Ԃ�n��ɏ��颉Ԃ����ς��^���)
- ���N�C���w�Z�Q�Z�E���w�Z�P�Z����ʉ�����_���f���Z�Ɏw�肵�A�����E���k�ɂ���@�@
���ʉ�����s���A��ʂ̃|�C�̂Ėh�~�ȂǏ����w���̃������̌���ɓw�߂�B�F���䒬
- �s���̏������Z���R���s���[�^�[�l�b�g���[�N�Ō��сA��̎��R�x�ɂ��Ē�������B �F ��z�s
- �����̎��@�����˂��h���w�K���s�Ȃ��B �F ��z�s
- ������œ������e���|�X�^�[��`���V�ɂ܂Ƃ߂āA�ƒ��n��ɓ���������B�F��z�s
���̒��ŁA���ɢ�ʉ�����_���f���Z��̎��Ƃ́A�ړI��������w���̃�
�����̌��㣂Ƃ������Ƃ�����A�e�w�Z�̊�����ɑ�����g�݂̈ӎ����������Ƃ��킩�����B
(4) ���Ύs�̌���
(4.1) �s���ɑ��Ă̊�����̓��e
- �s�ł́A������磂̖��̉��ł̊����́A���ݍs���Ă��Ȃ��B
- �s���u���̒��ŁA�A�[�X�f�[�ɎQ�������l�X�����S�ƂȂ��āA���ɐe���ޓ��̊�����
������B
- ���݁A�s����w������\�z������A���̒��Ŋ�����Ɋ֘A���鍀�ڂ��܂߂邱�Ƃ�
�\�ł���B
(4.2) �w�Z�̊�����Ɋւ��Ă̑Ή�
- �U�N�O�ɢ���t�H�[������̎��{���s���S�����w�Z�Ɉ˗��B
- 2002�N����̐V�w���v�̂ɂ����频����I�Ȋw�K��̎��ԂŊ���������グ�邱�Ƃ�
�\�Ȃ̂ŁA�e�Z�����@�̍ۂɁA������ɑ��Ď��g�݂̒Ⴂ�w�Z�ɑ��A���g�݂�
�����w�Z�̗l�q���Љ�B
ISO�F�̎����̂Ɣ�r����ƁA���Ύs�̏��w�Z�͊����炪�܂��M�S�ɍs���Ă��Ȃ�
�Ǝv����B�����ŋ���ψ���Ɍ�����q�A�����O�ɍs�����Ƃ���A���Ύs�ł�1993�N�ɢ��
���t�H�[������̎��{���s���S�����w�Z�Ɉ˗������ق��A�e�Z�����@�̍ۂɁA������ɑ���
�̎��g�݂����Ȃ��w�Z�ɑ��āA���g�݂̍����w�Z�̗l�q���Љ�Ă���Ƃ������Ƃł���B
�����Ď��ɁA���ɔM�S�Ɋ�������s���Ă���Ƃ������؏��w�Z�ɁA�q�A����
�O�ɍs�����B
���؏��w�Z�ł͢�Ԏ���̐���������A�R���s���[�^�[�l�b�g���[�N�𗘗p���Ă̊��w�K�A���T
�C�N���{�b�N�X�̐ݒu�����Ă�����ƁA���Ύs�ɂ�������ɔM�S�Ɏ��g��ł���w�Z����
�邱�Ƃ����������B
����ɁA96�N�x�̓s�s�v����K�ŁA�������ǂ͒n��ɂ��Z���̈ӎ��̈Ⴂ
�ɂ��Ē��ׂĂ��邪�A���̒��ŁA���ӊJ���n��̏Z���͌����w���s�s�n��̏Z����������
�ׂ�^���Ă���Ƃ������_���o�Ă���B
�����ŁA�u�S�̓I�ɂ��Ύs���̏��w�Z�ł̎��g�݂́AISO�擾�����̂ɂ͋y
���A���w�Z�̊�����̎��{�ɂ͑傫�ȍ�������B���T�C�N���ɂ����ẮA�s�s���̕����͂��
��Ă���B�t�Ɏ��R�Ƃ̂ӂꂠ���Ɋւ��ẮA���ӊJ���n��̕����͂����Ă���B�v�Ƃ�������
�𗧂āA�s���̑��̏��w�Z�̌���͂ǂ��Ȃ̂��A�s���̑S���w�Z�Ƀq�A�����O���������{���A����
�ɒn��Z���ɑ��ăA���P�[�g���������{���邱�Ƃɂ����B
�������@
�E�q�A�����O����
���Ύs���S���w�Z�Ɋ�����Ɋւ���q�A�����O������\�����݁A���̎�ꂽ�w�Z�ɑ�
�Ď��{�B���̎��Ȃ��w�Z�̂���FAX�ɂ�钲���ɋ��͂ł���Ƃ����w�Z�ɂ��ẮA�q�A����
�O�����Ɠ��l�̓��e��FAX�ɂ�莿���𑗂�A���Ă��炤�B
�E�A���P�[�g����
�w�Z�̊�����Ƃ̊֘A�ׂ鍀�ڂ�����s����A�q�A�����O�������s�����w�Z�̂����A
�A���P�[�g���{�̋�����ꂽ�w�Z�̎����̕ی�҂ɑ��Ď��{�B����́A���w�Z6�N���܂���
5�N���̎����̕ی�҂�Ώۂɍs�����B
3-3 ���Ύs���e���w�Z�ł̃q�A�����O��������
(1) �����
���Ύs�S���w�Z(�R�U�Z)�̂����̂Q�V�Z(�w���s�s�n��U�Z�A���ӊJ���n��Q�P�Z)
[������ꂽ���w�Z : �h�̗��A���s�� ]
�c���R �쉪 ���� �c�� �}�g��� ����
���� �R�� �O�� �g�� ���� �^�� ��d
���� �k�� �㋽ ���� �h ��]�� �|����
��̋{ ��� ���ؓ� �J�c�� �I�� �J�c����
���c
(2) ���t�H�[�����E������̎��{�ɂ���
- ����,���t�H�[�����C�����狤�Ɏ��{���Ă���c�V�Z
- ����,���t�H�[�����ɂ��Ă͌���������,������ɂ��Ă͎��{���Ă���c�V�Z
- ����,������͎��{���Ă��邪,���t�H�[�����̎��{�ɂ��Ă͗\�肪�����c�X�Z
- ����,���t�H�[�����ɂ��Ă͌���������,������͎��{���Ă��Ȃ��c�S�Z
�R�U�Z�Ƀq�A�����O���s�����Ƃ���A���w�Z�ɂ����e�͈قȂ邪�A����
���̌`�Ŋ�������s���Ă��鏬�w�Z���Q�R�Z�i�W�T���j�Ƒ������Ƃ��킩�����B���̂���
����AFAX���̂T�Z�Ƃ����͂̂��������Ȃ������S�Z�ɂ��Ă���������s���Ă����
�ł͂Ȃ����Ɨ\�z�����B���ہA�̓����Ȃ��������w�Z�̒��ɂ��A������ɔM�S��
�Ƌ���ψ���猾��ꂽ���؏��w�Z�Ƌ������ĉԎ���̐������������{������A�C���^�[
�l�b�g�Ō𗬂������肵�Ă��鏬�w�Z������Ƃ����b�����B
(3) ���ݎ��{����Ă��������̓��e
�m���R�ɐG���n�i�w���s�s�S�Z�C���Ӓn��P�P�Z�j
- ���Ԃ͔̍|�i�w���Ԓd�C��͔̍|,��l�ꔫ�^���Ȃǁj
- �T�c�}�C���E�ő��͔̍|
- �W���K�C����T�c�}�C���͔̍|
- ���_���͔̍|
- �������̎���
- �u�����炵�āA�������ꂢ�ɂ��邱�Ƃ̕K�v����������B
- �~�~�Y�����炵�āA�y��������邱�Ƃ�������B
- ���_�J�̎���
- �I�I�����T�L���ώ@����B
- �����T�Ԃ̐��i
- �����̋G�߂̈ڂ�ς�������B
- �w�Z���ӂ̓��A���̊ώ@
- �����t��p���āA�͔�����B
- �~�̎��̎��n���s���A�~�W���[�X������B
- �~���[�W�A���p�[�N�i���C���s�j�����w����B
- �����A�������w
- �e�qPTA�����ŃI���G���e�[�����O
- �}�g�R�𒆐S�ɁC�g�߂Ȏ��R��m��B
�m�S�~��襎����̃��T�C�N���ɂ��ān�i�w���s�s�Q�Z�C���Ӓn��R�Z�j
- �N���[���Z���^�[���w�i�R,�S�N�j
- ��,����������C�N���[���Z���^�[���w�i�S�N�j
- �w�Z�ł̎�������C���T�C�N���̎��{
- ���T�C�N��������p������i�����
- �R���|�X�g�̐ݒu
�m���w�K�n�i�w���s�s�R�Z�C���Ӓn��P�Z�j
- �S�~���ɂ��Ē��ׂ�i�S�N�j
- �Ζ������A���ݏ������ɂ��đ��̍��̗l�q�ׁA���{�̌���Ɣ�r�i�T�N�j
- �����̒r�̐��̉����ɂ��Ē��ׂ�i�T�N�j
- �Ԏ���̐�������
- ���Q�A��C�����ɂ��Ē��ׁA�m�n������A���������̍s���i�T�N�j
�m���͂̊������ɂ��ān�i�w���s�s�S�Z�C���Ӓn��P�P�Z�j
- �N���[���^���A�n��̐��|�i��ʏE���A������ƁA�w�Z���ӂ̑|���j
- �o�Z���Ȃ���̃S�~�E��
- ���ۑS�̃|�X�^�[�A�`���V���
[���̑�]
�w���s�s�n��̎����́A���ӊJ���n��̎����Ɣ�ׂāA�S�~���E�����
�ɂ��Ă̊w�K������@��͑������A���R�Ƃӂꂠ���@����Ȃ����Ƃ����������B�܂��A��
�ӊJ���n��̂���w�Z�̐搶�̃R�����g�Ƃ��āA�u�s�s���ȊO�̒n��ł̃S�~�̕s�@��������
���Ă���B���������������S�~����菜���Ă��A�܂������ɕs�@�������o�Ă���B���̂��ƂɁA
�����̎������^��������Ă���B�v�Ƃ������̂��������B
�N���[�������́A�q�A�����O���s�����Q�V�Z�̂��������ȏ�̂P�T�Z���s���Ă���B������
�����A�A���͔̍|�A�����Ȃǂ����A���������悵�Ăł���g�߂Ȃ��Ƃ���n�߂�Ƃ������l
�q���ǂݎ���B�܂��A�~���[�W�A���p�[�N��N���[���Z���^�[�Ɍ��w���s�����Ƃɂ��A����
��ڂŌ��Ċw�K���Ă��鏬�w�Z�������݂���B�e���w�Z�ɃR���s���[�^�[���ݒu����鍡�N��
�H�ȍ~����́A������̕����L����������A���e�����X�ɏ[���������̂ɂȂ��Ă����Ɨ\�z��
���B
�Ȃ��A��������s���ړI�Ƃ��Ď��̂悤�ȓ��e��������w�Z���������B
- ��w�N�F�g�߂ȓ��A���Ƃ̂ӂꂠ����ʂ��āA���R�▽�̑���ɋC�t���B
- ���w�N:�g�߂Ȋ��Ɛl�Ƃ̊ւ���m��B
- ���w�N�F�g�߂Ȋ����ɊS�������A���悢���ɉ��P���悤�Ƃ���B
(4) ������Ɏg�p���鎞��
- ��Ƃ�̎��ԁi�w�Z�ٗʂ̎��ԁj�c10�Z
- �w�������̎��ԁc�V�Z
- ���Ǝ��Ԃ̈ꕔ�i�Љ綾��ȥ����j�c�V�Z
- �����̎��ԁc�U�Z
- �i���Ǝ��ԊO�c�W�Z�j
�N�Ԃ̎g�p���ԂƂ��ẮA�Œ�łQ���ԁA�����Ƃ���łQ�T���Ԓ��x�Ƃ�����
�������A�N�ԂP�O���Ԓ��x�Ƃ���������8�Z�ƍł����������B
��Ƃ��w���A�����Ȃǂ��g�p���A�ʏ�̎��ƉȖڈȊO�ōs���A���Ƃɉe����
�Ȃ��悤�ɔz�����Ă���w�Z�����������B���Ǝ��Ԃ̈ꕔ���g���w�Z�ł��A���Ɋ֘A�̂��镪��
���o�Ă������ɍ��킹�čs���`������Ă���B�܂��A�ċx�݂̒��w�K�Ƃ��Ď��ƊO�ɍs���Ă�
��w�Z������A�e�Z�H�v��������l�q������������B
(5) �w�Z����ƒ�ւ̔z�z���ɂ����������̌f�ڏ�
- �f�ڂȂ��c�V�Z
- �f�ڂ���c�P�S�Z
�i���e�j- �T�P��A�N���[���^���ɂ��Ă̕i�����̐��Ȃǁj
- �w���P�`�Q����x�A������Ɋւ��銈���̕�
- �w���P�`�Q����x�A���W����W
- �N�ɐ���A�S�~�E���̗l�q��u�̎�����
- �N�ɐ���A�������e�̈ē�
- �N�ɐ���A��������̋��͂��f�ڂ���
- �N�ɐ���A���_���͔̍|�ɂ��ĕ���
- �Z���N���[���^���̎�`���̗v���E��
�����ȏ�̊w�Z�����炩�̔z�z���ŕی�҂ɑ��āA��Ƃ��čs���Ă��銈��
�̕����˔z�z����z�z���Ă���B�����A�z�z�͂܂��܂��ł������B����ɁA�z�z���Ă�
�Ȃ��w�Z��7�Z����A�Ȃ��ɂ͊�����A���t�H�[�����ɂ��čs���Ă���w�Z������A�z�z
�������Ă������̂ł͂Ȃ����Ɗ������B
(6) ������ɑ��鎙���̊S�x
- ���t�����S�ƂȂ�,�������w�����Ă���c�P�P�Z
- ���������S�ƂȂ�,���t���⏕���Ă���c�W�Z
- ��ʂɂ����,���t�����S�ƂȂ����莙�������S�ƂȂ����肷��c�R�Z
���������S�ƂȂ��Ċ��ۑS�������s���̂́A���w���Ƃ����N���l���Ă�
������Ƃł���Ǝv���邪�A�P�W�Z���V�Z���������S�ł���Ƃ����͓̂��M���ׂ����ʂł�
��Ǝv����B���̂��Ƃ���A������ɑ�����Ύs�̎����̊S�͔�r�I�����Ƃ�����B
(7) ��������s�������Ƃɂ�鎙���̐����ԓx�̕ω�
- �S�~�̌��ʉ��A���ʉ������H����悤�ɂȂ����B�i�X�Z�j
- �S�~�̗ʂ��������B����ʂ��̂Ă��l�ɋ^������悤�ɂȂ����B
- ���ɂ��čl����悤�ɂȂ����B�i�R�Z�j
- �����ɑ��Ă̎������N���悤�ɂȂ����B�i�R�Z�j
- �����p�b�N�̉���ɔM�S�ɂȂ����B
- �S�~���ɋ��������悤�ɂȂ���.�B
- ���T�C�N���ɊS�����悤�ɂȂ����B
- �S�~���E���悤�ɂȂ����B
- �ʂ̃|�C�̂Ă�����l�Ԃɋ^������悤�ɂȂ����B
- ����I�Ȕ��������֎��g�ނ悤�ɂȂ����B
- �����t�|���|���ɐi��ŎQ������悤�ɂȂ����B
- ���͓I���������܂����B
- ���ɑ��鋻�������悤�ɂȂ����B�i�d�q���[���̎g�p��w�N�̘g�����������Z
�Ƃ̋��́j
���̑��A�����̊��ɑ��闝���͐[�܂������A���퐶���̒��Ŏ��H������
�ƂȂ�Ɠ���Ƃ��������������B
������̐��ʂƂ��Ċ��ɑ���m���Ɨ����ɂ��Ă͐[�܂������A����
�����ɂ����Ă̎��H�ƂȂ�ƁA�S�~�̕��ʁE���ʒ��x�̎��H�ɂƂǂ��܂��Ă���A���T�C�N��
�ȂǂƂȂ�Ƃ܂����H����Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B����̓��T�C�N���̋@���ꏊ�̕s����
�����ƍl������B
(8) ���v�撆�̓��e�Ƃ��̎��{����
- �ԂƗ̂܂��Â���
- ���Ԃ���Ă�
- �̊G
- �Ȋw�o�O���N�`���[�ɂ����t�H�[����
- �ی�҂��Ă�ł̊��t�H�[����
- �������W��̎��{
- �w�Z�S�̂Ŋ����e�[�}�Ɋe�w�N�Ŏ��g�މۑ�����߂āA���璲�ׂ�v��𗧂āA���ׁA
���\�������B
- ���������̒n��̊����l����
- ���y��n���m��
- ���Ɋւ���A���P�[�g���{
- ���T�C�N���̉ƒ��i����
�V���ɏo�Ă������̂Ƃ��āA�̊G��`���A�Ȋw�o�O���N�`���[�ɂ���
�t�H�[�����A���o�Ă����B���̒��ŁA�o�O���N�`���[�ɂ��ẮAISO�F�ؓs�s�Ɠ��l�Ȃ��Ƃ�
�s�Ȃ���̂ł͂Ȃ����B
(9) �����I�Ȋ�����ɂ���
(9.1) �����I�Ɋ������������闝�R
- ���݂̎����ɖ��ڂȖ��ł��邩��B
- �Q�O�O�Q�N����̐V�w���v�̂ɂ����鑍���I�Ȋw�K�ŁA������W�Ɏ��g�ޗ\��ł��邽�߁B
- �����I�Ȋw�K�̎��Ԃ���肢��邽�߁B
(9.2) �����w�K(2002�N�x����)�ɑ����
- �E���̍Z�����C�̃e�[�}�Ƃ��Čv��A���H���Ă����\��B
- �Z�����C���{�A��i�Z�̎��g�݂��B
- ������Ɋւ����ۑ���Ƃ��̒Nj��E��̓I���H
- �{�����e�B�A�����E�n��̗��j���w�ԋ@���݂���B
- ���ݍs�Ȃ��Ă��邱�ƂW�����Ă����B
(9.3) �����w�K�ɑ������
- ��������w�K�����芈��������o����ƍl���Ă���B
- ������̈Ӌ`��������������������Ă����ƍl���Ă���B
- �S�~���o���Ȃ��A�o�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��ƒ��n��ɂ��L�߂ė~�����B
- �������̂�����Ƃ����S�~���E���悤�Ȉӎ����o�Ă�������B
- ���R�E�̈���Ƃ��ė��p�����Ă�����Ă��闧��𗝉������A���܂������Ă����l������
��������(���ۑS)�B
- ��̓I�ȒT�������ւ̎��g�݂�����
- �w�т������e������I�����A���ׂ�ԓx
- �������ł̎����
- �g�̉��̊��ɖڂ������������B(�����ɂǂ�ȉe�����y�ڂ��Ă��邩�l��������@����
����)
- ������L����
- �����ɂ���p�A�S�~�̕��ʎ��W�̂������𗝉��ł���悤�ɂ���
����肪��肴�����������A�V�w���v�̂ɂ�����悤�Ɋ�����͂��ꂩ��̏d�v�ȋ���
�̈�ł��邽�߁A���w���̂��������{�I�E���ݓI�Ȋ��ɑ���m����ӎ�����Ă邱�Ƃ�
�K�v�B
(10) ���T�C�N���ւ̎��g�ݏɂ���
(10.1) ���T�C�N���{�b�N�X�̐ݒu��
- ���݁C���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă���c�P�X�Z�i�w���s�s�S�Z�C���Ӓn��P�T�Z�j
- ����,���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă��Ȃ��c�W�Z�i�w���s�s�Q�Z,���Ӓn��U�Z�����P�j
���P�c���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă��Ȃ��w�Z�̂����A���Ӓn��̊w�Z�Łu�{�����e�B
�A�ψ�������v�A�u���Ԃ�ݒ肵�Ăo�s�`������v�A�n�悮��݂Ŏ����S�~�̉���Ƃ�����
���������B
(10.2) ������Ă��鎑����,���̎g����
- �����p�b�N�i�P�W�Z)
- ���s�i�V���o�[�l�ރZ���^�[�̐E���j�̉���ɂ����B�i�P�T�Z�j
- ���A�ؔ��ɂ���B�i�P�Z�j
- ���Đ��͂��������B�i�P�Z�j
- �����������B
- �ʁi�V�Z�j�����|�H��֏o���B
- �y�b�g�{�g��
- ���A�ؔ��ɂ���A�^���p��i�_���x���j�ɂ���A���傤������A�����P�b�g
�̍ޗ��Ƃ���B�i�e�P�Z�j
- �����|�H��֏o���B
�� ���̑�,�_���{�[����e���z���J�[�h��r��Î���Õz�̉�����s���Ă���w�Z��������.
�� �����p�b�N�̉���ɂ��ẮC�Q�����Ƀ_���{�[���P�����x�Ƃ�������������.
(10.3) �����̉�����
- �w�Z�c�T�Z
- �o�s�`�c�Q�Z
- �q����c�Q�Z
- ������c�V�Z �c���R �㋽ ���c �O��
��]�� �|���� ����
�w�Z�ɂ����鎑������́A����ʂ◦���グ��Ƃ������ʂ����邱�ƂȂ���A
�����̃��T�C�N���ւ̊S�����߂�Ƃ����_�ňӖ����傫���B
������Ă��鎑���͋����p�b�N�������Ƃ����������B��27�Z��18�Z
�������p�b�N��������Ă����B�w�Z�ɏW�߂�ꂽ�̂��s�̃V���o�[�l�ރZ���^�[�̐E���ɉ��
����A�����Ǝ҂Ɉ����n����g�C���b�g�y�[�p�[�ȂǂɍĐ������B�����p�b�N�͎s�̃S�~��
���敪�ɂ͂Ȃ��̂ŁA����̋@���^����Ƃ������Ƃɂ����Ă��Ӗ�������B
��ʂ̉����7�Z�ł���A�N���[���Z���^�[�ɓn�����B��ʂ͎s�̃S�~����敪�ɂ���A
�����ς玙���ւ̊�����Ƃ������F�������Z���B���̃y�b�g�{�g����_���{�[���A�r�A
�Î��A�Õz�̉�����s���Ă���Ƃ���͏����ł���B���������������̉�������Ȃ��͉̂��
���w�Z�ł͂Ȃ����̎�̂ɂ���čs���Ă��邱�Ƃ��������߂Ǝv����B�n��̎q����⎩
����Ȃǂ��s���Ă���Ƃ������𑽐��������B
(11) �p�\�R���̓����ɂ���
(11.1) �p�\�R���̎�Ȏg�p��
- ���t���S:�Q�Z
- �������S�F�P�V�Z
- ���t������������x�g�p�F�W�Z
(11.2) �p�\�R���̐ݒu�ꏊ��䐔
�}�����F�Q�R�Z
- �Q��:�P�S�Z
- �W��:�P�Z
- �X��F�T�Z
- �P�O��:�R�Z
- �ݒu�䐔����:1�Z
�E�����F�Q�Z
�[����(���߭�����):�R�Z
�I�[�v���X�y�[�X:�P�Z
(11.3) �p�\�R���̎g�p�ړI
- �C���^�[�l�b�g����p���������W �F 22�Z
- ���Z�Ƃ̏����� �F 5�Z
- ���̊�b�̒蒅(���[�v���A�Q�[�����܂�) �F 2�Z
- �p�\�R����p������i���� �F 2�Z
- ���ۗ�������̐��i �F �P�Z
- �}���̌��� �F 1�Z
�����̊w�Z�ŁA���Ɋw���n��ł͑S�Z�ŁA�p�\�R����������̂Ɏg�p������
�Ɖ��Ă���A����ɃC���^�[�l�b�g�ł̏����W��������ȂǁA�����ւ̃p�\�R���̎g�p
���l���Ă��邱�Ƃ�������B�������A�l�b�g���[�N��������������ŁA���Z�Ƃ̌𗬂��l��
�Ă���w�Z�́A5�Z�Ə��Ȃ����ʂɂȂ��Ă���B
(12) ���_
���Ύs���̏��w�Z��ISO�F�؍ς݂̎����̂Ɣ�r����ƁA�w�Z�̘g�������������Ȃ��A�n��ւ̓����������s���Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ���A����Ύs���̏��w�Z�̎��g�݂́A�h�r�n�擾�����̂ɂ͋y�Ȃ��B��Ƃ��������͗����ꂽ�B�܂��A(2)���e���w�Z�̊ԂŁA������ɑ�����g�ݏɑ傫�ȍ������邱�Ƃ����������B
���ɁA���R�Ƃ̂ӂꂠ���ɂ��ẮA�w���s�s���ł͌����Ȃǂ̂���ꂽ���R������@��قƂ�ǂł��邱�Ƃ����������̂ŁA���ӊJ���n��̕������R�Ƃӂꂠ���@������A�Ƃ����������������Ƃ�����B����ŁA���T�C�N���ɂ��Ă͒n��ɂ�鍷���قƂ�nj���ꂸ�A���B�̗��Ă������͔ے肳�ꂽ�B�������A�s�S��ŕ��ϓI�Ɏ��g��ł��邱�Ƃ�������A����́A���T�C�N���ɑ�����g�݂��s�S��Ō��コ���Ă����K�v������B
3-4 �A���P�[�g�����Ɋւ��钲������
(1) ����
���B�́A���̂悤�ȉ���𗧂āA�A���P�[�g���������{���邱�Ƃɂ����B
- �����p�b�N������ɏo���Ă���������T�C�N���ɎQ������̂ł͂Ȃ����B
- �����p�b�N������ɏo���Ă���l�̕������ɔz�����A�g�C���b�g�y�[�p�[����ɍĐ����̂��̂��w������̂ł͂Ȃ����B
- ���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă���w�Z�̕ی�҂̕����A�ݒu���Ă��Ȃ��w�Z�̕ی�҂������T�C�N���ɊS������A����ɂ܂킵�Ă���̂ł͂Ȃ����B
- ���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă���w�Z�̕ی�҂̕����A�ݒu���Ă��Ȃ��w�Z�̕ی�҂������T�C�N���ɊS������A����ɂ܂킵�Ă���̂ł͂Ȃ����B
(2) �A���P�[�g���{��
�Ώ�: �q�A�����O�������s�����w�Z�̂����A�A���P�[�g���{�̋�����ꂽ�w�Z�̎����̕ی�҂ɑ��Ď��{�B����́A���w�Z6�N���܂���5�N���̎����̕ی�҂�ΏۂƂ����B
�z�z�����F1397��
�L�����F894�� (��64.0��)
(3) �A���P�[�g���ʂƂ��̓��e
�A���P�[�g����
|
|
����ԍ� |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| �� |
�@ |
724 |
58 |
13 |
162 |
64 |
50 |
498 |
197 |
515 |
375 |
301 |
565 |
380 |
67 |
379 |
490 |
302 |
105 |
200 |
776 |
835 |
| �� |
�A |
128 |
535 |
330 |
8 |
74 |
482 |
294 |
419 |
277 |
47 |
467 |
316 |
173 |
172 |
380 |
105 |
196 |
433 |
396 |
90 |
34 |
| �� |
�B |
26 |
287 |
535 |
684 |
651 |
173 |
66 |
95 |
73 |
418 |
109 |
�| |
319 |
643 |
121 |
285 |
376 |
347 |
88 |
�| |
�| |
| |
�C |
6 |
�| |
�| |
32 |
80 |
170 |
�| |
166 |
20 |
44 |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
| |
���� |
10 |
14 |
16 |
8 |
25 |
19 |
36 |
17 |
9 |
10 |
17 |
13 |
22 |
12 |
14 |
14 |
20 |
9 |
210 |
28 |
25 |
| |
�v |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
894 |
|
| �� |
�@ |
81.0 |
6.5 |
1.5 |
18.1 |
7.2 |
5.6 |
55.7 |
22.0 |
57.6 |
41.9 |
33.7 |
63.2 |
42.5 |
7.5 |
42.4 |
54.8 |
33.8 |
11.7 |
22.4 |
86.8 |
93.4 |
| �� |
�A |
14.3 |
59.8 |
36.9 |
0.9 |
8.3 |
53.9 |
32.9 |
46.9 |
31.0 |
5.3 |
52.2 |
35.3 |
19.4 |
19.2 |
42.5 |
11.7 |
21.9 |
48.4 |
44.3 |
10.1 |
3.8 |
| �� |
�B |
2.9 |
32.1 |
59.8 |
76.5 |
72.8 |
19.4 |
7.4 |
10.6 |
8.2 |
46.8 |
12.2 |
�| |
35.7 |
71.9 |
13.5 |
31.9 |
42.1 |
38.8 |
9.8 |
�| |
�| |
| �� |
�C |
0.7 |
�| |
�| |
3.6 |
8.9 |
19.0 |
�| |
18.6 |
2.2 |
4.9 |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
�| |
| |
���� |
1.1 |
1.6 |
1.8 |
0.9 |
2.8 |
2.1 |
4.0 |
1.9 |
1.0 |
1.1 |
1.9 |
1.5 |
2.5 |
1.3 |
1.6 |
1.6 |
2.2 |
1.0 |
23.5 |
3.1 |
2.8 |
�A���P�[�g���e
�ȉ��̊e���⎖���ɂ����āA�ł����ƒ�̏ɋ߂��I�����̔ԍ��P�Ɂ������ĉ������B
�p�P�D �S�~�̎̂ĕ���A�Ƃ̉��̔����ɂ��Ăǂ̂悤�ɂ��Ă��܂����B
�P�D �S�~���w�肳�ꂽ�j���ɏo���A�Ƃ̎���̔����ɂƂ߂Ă���B
�Q�D �S�~���w�肳�ꂽ�j���ɏo���A�Ƃ̎���̔����ɂ��Ă͂��܂�C�ɂ��Ă��Ȃ��B
�R�D �S�~�̂Ă̗j���ɂ��Ă͋C�ɂ��Ȃ����A�Ƃ̎���̔����ɂƂ߂Ă���B
�S�D �S�~�̂Ă̗j����A�Ƃ̎���̔����ɂ��Ă͂��܂�C�ɂ��Ă��Ȃ��B
�S�~���w�肳�ꂽ�j���ɏo�����Ƃ́C���߂��Ă���A�n��Z�����m�ł��Öق̗����̂悤�ł�����
�����Ă���ƒ낪95���ȏ�ł���B�܂��Ƃ̎���̔������A80���ȏ�̉ƒ�łƂ߂Ă���Ƃ���������ꂽ�B
�p�Q�D �G�R�}�[�N�̂������i�ɂ��Ăǂ��v���܂����B
�P�D �G�R�}�[�N�̂������i�ɊS������C��ɔ����悤�ɂ��Ă���B
�Q�D �G�R�}�[�N�̂������i�ɊS������C���܂ɂ͔����Ă���B
�R�D �G�R�}�[�N�̂������i�ɂ͂��܂�S���Ȃ��B
�G�R�}�[�N�̂��Ƃ����ԂŘb��ɂȂ��Ă��炩�Ȃ�̎��Ԃ��o�߂������A30���ȏ�̐l�����܂�S����
���Ɠ����Ă���B�܂��A��ɔ����悤�ɂ��Ă���l��6.5���ł��܂荂���Ȃ��B�ł������́A�S������A����
�ɔ����Ă���A��60���߂�����ꂽ���A���܂ɂƂ����̂��ǂꂭ�炢�̕p�x�Ȃ̂�������Ȃ����ߔ��f����̂��
�����A���K�I�Ȗʋy�я��i�̎�ނ̏��Ȃ����w��ɂ���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�p�R�D �������Ȃǂɂ́A�ǂ̂悤�Ȍ�ʎ�i�𗘗p���Ă��܂����B
�P�D ���Ɨp�Ԃ͗��p�����C��Ɏ��]�Ԃ�k���ł����B
�Q�D ���Ɨp�Ԃ����p���邪�C�߂������ł���Ύ��]�Ԃ�k���ł����B
�R�D ��Ɏ��Ɨp�Ԃ𗘗p���Ă���B
�����ł͂�͂�}�g�̓����Ƃ����ׂ����A��Ɏ��Ɨp�Ԃ𗘗p���Ă���Ƃ�������60�����߂Ă���B
��Ɏ��]�ԁE�k���Ƃ�����1.5���ł����Ȃ��A�g�������Ă���ƒ낪30���㔼�ł������B
�p�S�D �������̂������ɂ��āA���i�ǂ̂悤�ɂ��Ă��܂����B
1. �����������g���A�����o�����ςȂ��Ŗ����B
2. ���������͎g�킸�ɁA�����o�����ςȂ��Ŗ����B
3. �����������g���A���͕K�v���ɃR�b�v�ɂ��߂Ė����B
4. ���������͎g�킸�ɁA���͕K�v���ɃR�b�v�ɂ��߂Ė����B
�p�T�D �H��ɂ��āA���i�ǂ̂悤�ɂ��Ă��܂����B
1. ������܉t�ɂ��ׂĂ̐H����ꏏ�ɓ���ĐB���A�H���c�т����̂܂ܗ����B
2. �����͕����邪�A������܂ŐB���A�H���c�т������B
3. ����ɂ��H��ނ��A��܂��I��Ŏg���B�H���c�т̓R�[�i�[�Ɏ�B
4. ���O�ɖ���@�����A������Ă̂Ƃ��`�Ȃǂł��炤�B�H���c�т̓R�[�i�[�Ɏ�B
����ɂ��H��ނ��A�H���c�т̓R�[�i�[�Ɏ�Ƃ�����72.8���ƍł��������A�H���c�т����̂܂ܗ�
���Ƃ���������1�2���킹��15.5������A�H���c�т����������֗���Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�p�U�D ����̎d���ɂ��āA���i�ǂ̂悤�ɐ�܂��g���Ă��܂����B
1. �������n�̐�܂ڔ�����U�荞��Ŏg���B
2. �������n�̐�܂��v���Ďg���B
3. ��������g���B
4. ���C�̎c�蓒���g���A���A��������g���B
�������n�̐�܂��g�p���Ă���l��1�2���킹�Ė�6���ł��邪�A������̎g�p����4���ŁA���ɔz�����Ă���l
�����Ȃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��f����B�������A�ˑR�Ƃ��Ė������n�̎g�p�҂̕��������B
�p�V�D �V�����v�[�ɂ��ĕ��i�ǂ̂悤�Ȑ�܂��g���Ă��܂����B
1. �Ζ��n������܂̃V�����v�[������X���g���Ă���B
2. �Ό��A�܂��̓A�~�m�_�n�̃V�����v�[���g���Ă���B
3. ���̉���ɉ����āA�Ό���A�~�m�_�n�V�����v�[���g�������Ă���B
����ɂ��Ă�Q6���l�A�Ζ��n������܂��g�p����l��55.7���A�Ό����̓A�~�m�_�n�̎g�p�҂�32.9���ŁA�Ζ��n�̎g�p�҂̕��������B
�p�W�D �g�C����䏊�Ő�܂͂ǂ̂��炢�̗ʂ��g���Ă��܂����B
1. ��Ɋ�ʂɂ��������悤�ɂ��Ă���B
2. ��ʂ͒m���Ă��邪�C�����ɂ͂��������Ă��Ȃ��B
3. ��ʂł͉��ꗎ���������̂ŁC��ʂ������߂Ɏg���Ă���B
4. ��ʂɂ��Ă͒m��Ȃ��B
��ʂ�m��Ȃ��l��2������Ƃ������Ƃ͖�肪����悤�Ɏv���B�܂��A��ʂɂ��������Ă���l��2���������炸�A��ʂʼn��ꂪ�\�������邱�Ƃ�����ׂ��ł���B
�p�X�D �����܂͂ǂ̂��炢�̗ʂ��g���Ă��܂����B
1. ��Ɋ�ʂɂ��������悤�ɂ��Ă���B
2. ��ʂ͒m���Ă��邪�C�����ɂ͂��������Ă��Ȃ��B
3. ��ʂł͉��ꗎ���������̂ŁC��ʂ������߂Ɏg���Ă���B
4. ��ʂɂ��Ă͒m��Ȃ��B
�����܂ɂ��ẮA��ʂɂ��Ēm���Ă���l����97���ƍ����l���������B�������A��ʂ�m���Ă͂�����̂̎���Ă���l��58���ƈӎ��̒Ⴓ���f����B
�p�P�O�D ���ʼn��ꂽ�H���H�p���͂ǂ̂悤�ɏ������Ă��܂����B
1. �H��͕s�v�Ȏ���z�Ő@���Ƃ�A�H�p�����r�����ɗ����Ȃ��l�ɂ��Ă���B
2. �H��͕s�v�Ȏ���z�Ő@���Ƃ��Ă��邪�A�H�p���͔r�����ɗ����Ă���B
3. �H��͕s�v�Ȏ���z�Ő@���Ƃ��Ă��Ȃ����A�H�p���͔r�����ɗ����Ă��Ȃ��B
4. ���ʼn��ꂽ�H���H�p���̏����ɂ͂��܂�C�ɂ��Ă��Ȃ��B
����r�����ɗ����Ă��Ȃ��l��88���Ɖ��炩�̌`�ŏ������Ă���l�������A�ӎ��̍������f����B�������A���̏����ɂ��Ĉӎ����Ă��Ȃ��l��10���߂�����A����͒Ⴂ�l�Ƃ͌����������̂ŁA���̗^��������ׂɂ��Ă����ƒm���Ă��炤�K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B
�p�P�P�D �G�r���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɏ������Ă��܂����B
1. �Ϗ`�̎c��A���X�`�̎c��������̏����ɂ��Ă͂��܂�C�ɂ��Ă��Ȃ��B
2. �o���邾���c��`���o�Ȃ��l�ɍH�v����B
3. �ƒ�p�̂��߂܂��Ȃǂ�݂��A���Ə��������Ă���B
�G�r�����Ȃ�ׂ��o���Ȃ��悤�ɂ��Ă���l�Ǝ��Ə��������Ă���l�́A�S�̂�64�����߂Ă���B�����34���߂��̐l���ӎ������Ă��Ȃ��ȂǁA���Ɣ�ׂ�Ə����̈ӎ��͒Ⴂ���Ƃ��킩��B
�p�P�Q�D �O�p�R�[�i�[�ɐ���܂Ȃǂ��g�p���Ă��܂����B
1. �g�p������B
2. �g�p���Ă��Ȃ��B
�O�p�R�[�i�[�ɐ���܂��g�p���Ă���l��63���������B�������A�O�p�R�[�i�[�ɐ���܂͎g�p���Ă��Ȃ����A�r�����̖ԂŐH���̎c�肩�������̂Ă�Ƃ������悤�Ȃ����ŏ������Ă���l�������A���̎��₩��͈�T�ɂ͂�����Ƃ������_�͂����Ȃ��B
�p�P�R�D ���C�ɂ��āA�ǂ̂悤�ɑ|�������Ă��܂����B
1. ���ꂽ��Ζ��n������܂��g���đ|��������B
2. ���ꂽ��Ό��n��܂��g���đ|��������B
3. �����O�ɁA���܂߂ɃX�|���W�₽�킵�����g���ĐB
�����C�́A����Ă���|��������l����60���ŁA���̒��ł��Ζ��n������܂��g�p���Ă���l�̂ق��������A�ӎ��ɒႳ���킩��B�����͖����̂��ƂȂ̂ɁA�����O�ɂ��܂߂ɑ|��������l�����Ȃ������B
�p�P�S�D �����������鎞�A���������i�����ɓ���Ď����A���Ă��܂����B
1. ��ɁA������܂������Ă����A�X����܂������Ȃ��悤�ɂ��Ă���B
2. ���܂ɁA������܂������Ă����A�X����܂������Ȃ��悤�ɂ��Ă���B
3. �����X�ł��炦��܂𗘗p���Ă���B
�������̍ۂ̑܂͓X�ł��炤�Ƃ����l��7���ȏ�ł���A�����̑܂����Q����Ƃ����K���͂��܂���Ă��Ȃ��悤�ł���B�܂��A���B�̊����邱�ƂƂ��āA�X�[�p�[�����������i���ɑ��ĉߏ�ɑ܂�n���Ă���悤�Ɏv����B
�p�P�T�D �g�C���b�g�[�p�[�͂ǂ̂悤�ȑf�ނ̂��̂��g���Ă��܂����B
1. ��ɍĐ����̂��̂��g���Ă���B
2. ���܂ɍĐ����̂��̂��g���Ă���B
3. ��Ƀp���v100���̂��̂��g���Ă���B
�g�C���b�g�y�[�p�[�́A�Đ����g�p�̐l��1�2�����킹���8�����A�Đ������p�͐i��ł���Ƃ�����B�܂��A�Đ����̎��������ƌ��シ��Ύg�p����A�Ƃ����ӌ����������B
�p�P�U�D ��ʁA�r�̏����͂ǂ����Ă��܂����B
1. �قƂ�ǁA���T�C�N���ɂ܂킵�Ă���B
2. ���܂ɁC���T�C�N���ɂ܂킵�Ă���B
3. �S�~�Ƃ��ďo���Ă���B
��ʥ�r�́A���T�C�N�����i�̒��ł́A��r�I���T�C�N�����悢�Ƃ������Ƃ��A���̎���̉Ɣ�r����Ƃ킩��B����́A���[�J�[�̃��T�C�N���ɑ��銈���̐ϋɂ��������ł͂Ȃ����B
�p�P�V�D �����p�b�N�̏����͂ǂ����Ă��܂����B
1. �قƂ�ǁA����ɂ܂킵�Ă���B
2. ���܂ɁA����ɂ܂킵�Ă���B
3. �S�~�Ƃ��ďo���Ă���B
�����p�b�N�Ɋւ��ẮA��ʥ�r�Ɣ�ׂ�ƃ��T�C�N�����͒Ⴂ�B���̌����Ƃ��ẮAQ19�ł��ӂ�邪�A�u�����p�b�N�����ĕۊǂ���ꏊ���Ȃ��B�����p�b�N�𑼂̕��@�ōė��p���Ă���B�v���ł���B
�p�P�W�D �o�U�[�Ȃǂ̕s�p�i�̃��T�C�N���ɂ͎Q�����Ă��܂����B
1. �������T�C�N���ɎQ�����Ă���B
2. �����T�C�N���ɎQ���������Ƃ�����B
3. ���T�C�N���ɎQ���������Ƃ͂Ȃ��B
�s�v�i�̃��T�C�N���́A���T�C�N���̒��ł���ԃ��T�C�N�������Ⴂ�B����́A�s�v�i���T�C�N���̋@���ꏊ�������Ă��邽�߂ɁA�Q������Ƃ������Ƃ��A�����̈�ł���B
��̂p�P�V�A�p�P�W�łQ�D�܂��͂R�D��I�����ꂽ���ɂ��f�����܂��B
�p�P�X�D ���T�C�N���ɂ܂킳�Ȃ����R�͉��ł����B
1. ��Ԃ�������̂��ʓ|�ł��邩��B
2. ���̂悤�ȋ@������ꏊ���킩��Ȃ�����B
3. ���̑�
���T�C�N���ɂ܂킳�Ȃ����R�̑����́A���̂悤�ȋ@������ꏊ��������Ȃ��Ƃ������̂ł������B�]���āA�����̋@���ꏊ��݂���A���T�C�N���Q�����͂����Ƒ����Ȃ�Ɨ\�z�����B
�p�Q�O�D �����A���w�Z�Ƀ��T�C�N���a�n�w����݂���Ă�����A�ϋɓI�ɎQ�����܂����B
�P�D �Q������B
�Q�D �Q�����Ȃ��B
�p�Q�P�D �����A�S�~����ꏊ�Ƀ��T�C�N���a�n�w����݂���Ă�����A�ϋɓI�ɎQ�����܂����B
�P�D �Q������B
�Q�D �Q�����Ȃ��B
(4) ���_
�e����ɑ��āA���ꂼ�ꎟ�̂悤�Ȍ��_������ꂽ�B�܂��A�u�����p�b�N�������
�o���Ă���������T�C�N���ɎQ������̂ł͂Ȃ����B�v�Ƃ�������ɑ��ẮA����̒�
��A����ɏo�������̂���l�ƂȂ��l�ł͍����o���B�S�~�Ƃ��ďo���Ă���l���W�O����
��̐l�����T�N���ɎQ������Ɠ����Ă���̂ŁA���T�C�N���{�b�N�X�ݒu�͗L���ł����
�l������B
���ɁA�u�����p�b�N������ɏo���Ă���l�̕������ɔz�����A�g�C���b�g�y�[�p�[��
��ɍĐ����̂��̂��w������̂ł͂Ȃ����B�v�Ƃ�������ɂ��ẮA�O���t�����Ă�����
���Ȃ悤�ɋ����p�b�N������ɏo���Ă���l�͊��z���ւ̍s���̈ӎ��������A�g�C���b�g
�y�[�p�[���p���v���̂��̂ł͂Ȃ���ɍĐ������g���Ă���l��������50%�߂��܂�A����
�ɍĐ������g���l���܂߂��90%�߂��ɏ���Ă���B����Ď�Ԃ̂����鎖�ł��ƒ�ōs����
����l�́A�w���̍ۂɂ����ɔz�������s�����Ƃ��Ă��鎖���킩��B
�Ō�ɁA�u���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă���w�Z�̕ی�҂̕����A�ݒu���Ă��Ȃ��w
�Z�̕ی�҂������T�C�N���ɊS������A����ɂ܂킵�Ă���̂ł͂Ȃ����B�v�Ƃ���
����ɂ����ẮA����̒ʂ�A���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă���w�Z�̕ی�҂̕����A��
�u���Ă��Ȃ��w�Z�̕ی�҂�������ɂ܂킵�Ă��闦�������B���̂��Ƃ�����A���T�C�N
���{�b�N�X�ݒu�͗L���ł���ƍl������B
3-5 �܂Ƃ�
����̎��K��ʂ��Ď��B�́A���Ύs�̊�����𐄐i���Ă������߂Ɏ�
�̂Q�_�����B�܂��A���݁A���T�C�N���{�b�N�X��ݒu���Ă���w�Z�ł���Ȃ�̗ʂ�
����ł��Ă������ŁA�A���P�[�g�̌��ʂ��A�ǂ��Ń��T�C�N�����s���Ă���̂�������
�Ȃ��Ƃ����ӌ���A�w�Z�Ƀ��T�C�N���{�b�N�X���ݒu���ꂽ��Q������Ƃ���������������
���B�܂��A�S�~�W�Ϗ�Ƀ��T�C�N���{�b�N�X���ݒu����Ă��Q������Ƃ������������������A
���Ύs���̑S�S�~�W�Ϗ�ɐݒu����ƂȂ�ƁA���T�C�N���{�b�N�X�̐ݒu��p���c��Ȃ�
�̂ɂȂ�Ǝv����B�܂��A���T�C�N���̐��i������s�Ȃ�Ȃ��ŁA���T�C�N���{�b�N�X��
�݂��ݒu����Ă��Z���̎Q���͗\���ł��Ȃ��B�����ŁA���T�C�N���{�b�N�X�����Ύs
���S���w�Z�i36�Z�j�ɐݒu���邱�Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃ���A�܂��͎����ւ̃��T�C�N���ɑ���
�������N�������߂ɂ��A���T�C�N�����y�̑�������Ƃ��āA�s���̑S���w�Z�ɁA���T�C�N��
�{�b�N�X��ݒu���邱�Ƃ������߂�B
���ɁA�����������T�C�N���ɂ��āA���T�C�N�����s���Ă���{�݂�X�܁A
������������̎g�����Ȃǂɂ��ẮA�s�����L���m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̑��ɂ��A��
�Ύs�̊�����邽�߂ɂ́A�s����l��l�̓w�͂�������A���̂��߂ɂ́A���ی�ׂ̈�
�m���ƂȂ�悤�ȓ��e���s�����m�邱�Ƃ���ł���B���̂悤�ȓ��e�����Ύs�̑S�s����
�`���邽�߂̍œK�ȏ���i�́A���Ύs�̍L���B����āA�s�̍L�̒��Ŋ���T
�C�N���Ƃ��������e�Ɋւ���R�[�i�[��݂��邱�Ƃ����B
����
�ڎ���