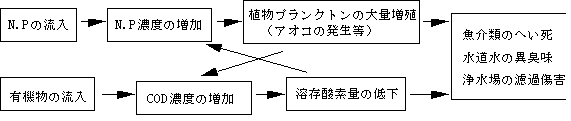 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�}2-1-1 �x�h�{�����ۂƗL�@�����̊T�O�}
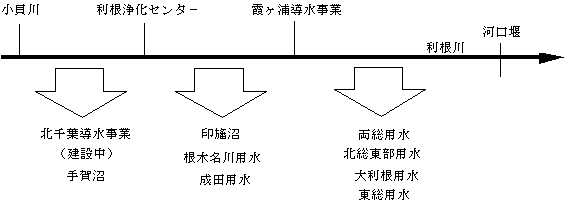
�}2-1-2 ��t���̗����삩��̓������Ɓi���v491���l�ɋ����F�g11.3���݁j
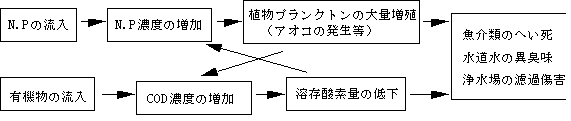 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�}2-1-1 �x�h�{�����ۂƗL�@�����̊T�O�}
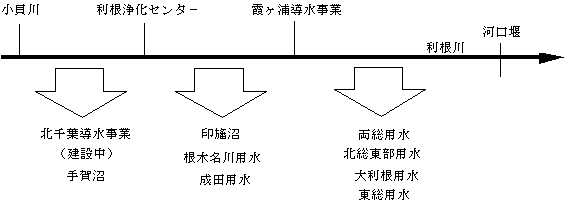
�}2-1-2 ��t���̗����삩��̓������Ɓi���v491���l�ɋ����F�g11.3���݁j
| �f�[�^ | ���� | �o�T | �f�[�^ | ���� | �o�T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �J�� | 265.7 | �C�ے� | 9 | ����(����V�c) | 89.9 | ���ݏ� | |
| 2 | ������ | 223.0 | ���v | 10 | �Ԏ��� | 11.6 | �V | |
| 3 | �Z���� | 223.0 | ���v | 11 | ���L��i���q | 742.8 | ���ݏ� | |
| 4 | �㐅�� | 20.9 | �����z���� | 12 | �i�����j | 744.0 | �V | |
| 5 | �H�Ɨp�� | 1.4 | �V���� | 13 | ������i�z��j | 5437.8 | �V | |
| 6 | �ȈՐ��� | 1.8 | �s�������v | 14 | �J�c�� | 43.3 | ���v | |
| 7 | ��p���� | 0.2 | �V | 15 | ����� | 1.3 | ���v | |
| 8 | �l���� | 2.0 | ���v | 16 | ������ | 32.3 | �����Z���^�[ |
���ɁA�e�f�[�^�̏ڍׂ������B
�i1�j�J�ʁ@
�J�ʂ͒}�g�R�ł̂��̂�p�����B�C���͓y�Y�s�ł̒l�����Ύs�̂��̂Ƃ���B�����ʂ̐���̍ۂɎg�����߁A�����ŕ\�������B�C���́��A�J�ʂ�mm�ł���B
| �� | �C�� | �J�� | �� | �C�� | �J�� | �� | �C�� | �J�� | �� | �C�� | �J�� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 14 | 4 | 13.6 | 104 | 7 | 24.9 | 131 | 10 | 16.5 | 12 |
| 2 | 5.0 | 18 | 5 | 17.5 | 155 | 8 | 25.5 | 71 | 11 | 12.3 | 101 |
| 3 | 8.7 | 68 | 6 | 21.5 | 138 | 9 | 21.5 | 177 | 12 | 6.8 | 35 |
�i2�j�����ʁ@
�����ʂ͓����Nj�C�ۑ�ł̂ݑ��肵�Ă���B���̒l����A�C���Ə����ʂƂ̊Ԃ̑��W����0.90�ł���C�������̑��ւ��������B�~���ʂƏ����ʂƂ̊�
�ł�0.72�ƁA�������ւ͂Ȃ������B���Ύs�̏����ʂ́A���Ύs�̋C���𓌋��s�̋C���Ə����ʂ̉�A���ɑ�����ċ��߂��B�\�͓����s�̋C���Ə����ʂł���B�C���́��A�J�ʂ�mm�ł���B
| �� | �C�� | ���� | �� | �C�� | ���� | �� | �C�� | ���� | �� | �C�� | ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8 | 26.8 | 4 | 15.2 | 99.1 | 7 | 26.6 | 143.9 | 10 | 21.5 | 93.5 |
| 2 | 7.0 | 13 | 5 | 19.2 | 91.4 | 8 | 27 | 130.6 | 11 | 102 | 61.7 |
| 3 | 10.5 | 86.9 | 6 | 22.7 | 108.5 | 9 | 22.9 | 85.3 | 12 | 46.5 | 37.2 |
�i3�j�Z���ʁ@
�����ʂƓ����Ƃ���B
���Ύs�̑��Z���� 868mm�~259km�Q ��265.7�~106 ���R
�i4�j�㐅���ʁ@
�N�ԗ��ʂ�20.85�~106���R �ł���B�i�o�T�F�����z����j
�i5�j�H�Ɨp���ʁ@
�N�ԗ��ʂ�1.4�~106���R �ł���B�i�o�T�F�V����j
�i6�j�ȈՐ����ʁ@
�N�ԗ��ʂ�1.81�~106���R �ł���B�i�o�T�F���Ύs�������v�j
�i7�j��p�����ʁ@
�N�ԗ��ʂ�0.17�~106���R �ł���B�i�o�T�F���Ύs�������v�j
�i8�j�l�����ʁ@
�����l�����ȈՁ{��p�����Ɠ������߂�1.98�~106 ���R �Ɛ��v�����B
�i9�j����i����V�c�j�@
���ʂ͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�N�Ԃ̑����ʂ�189.85�~106 ���R �ł������B
| �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �N����(106 ���R ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.35 | 4 | 13.98 | 7 | 9.59 | 10 | 7.73 | 189.85 | |
| 2 | 19.91 | 5 | 13.01 | 8 | 10.04 | 11 | 7.68 | ����(���R/s) | |
| 3 | 11.93 | 6 | 11.36 | 9 | 8.54 | 12 | 9.18 | 6.02 |
| �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �N����(106 ���R ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 4 | 1.00 | 7 | 1.27 | 10 | 0.60 | 11.56 | |
| 2 | 0.73 | 5 | 1.54 | 8 | 1.23 | 11 | 0.60 | ����(���R/s) | |
| 3 | 0.75 | 6 | 1.54 | 9 | 0.98 | 12 | 0.68 | 0.54 |
�i11�j���L��i���q�j�@
���ʂ͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�N�Ԃ̑����ʂ�742.80�~106���R �ł������B
| �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �N����(106 ���R ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.94 | 4 | 45.94 | 7 | 71.06 | 10 | 35.38 | 742.80 | |
| 2 | 21.04 | 5 | 144.73 | 8 | 93.97 | 11 | 33.46 | ����(���R/s) | |
| 3 | 21.64 | 6 | 120.99 | 9 | 82.52 | 12 | 43.13 | 23.55 |
�i12�j���L��i�����j
�N�Ԃ̗��ʂ�774.0�~106���R�ł������B
�i13�j������i�z��j
���ʂ͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�N�Ԃ̑����ʂ�5437.75�~106���R�ł������B
| �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | �N����(106���R ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237.09 | 4 | 397.98 | 7 | 474.67 | 10 | 373.37 | 5437.75 | |
| 2 | 177.62 | 5 | 680.81 | 8 | 635.48 | 11 | 265.08 | ����(���R/s) | |
| 3 | 194.83 | 6 | 759.79 | 9 | 910.26 | 12 | 344.20 | 172.43 |
�i14�j�J�c��@
�J�c��̗��ʂ͎s���N4���ԑ��肵�Ă���B�ȉ��̎��ŔN�Ԃ̗��ʂ𐄌v�����B
�J�c��̔N�ԗ��ʁ�0.5�i�J�c���4���Ԃ̗���/(�����4���Ԃ̗���/����̔N�Ԃ̗���)�j�@
�{0.5�i�J�c���4���Ԃ̗���/�i�Ԏ����4���Ԃ̗���/�Ԏ���̔N�Ԃ̗���)�j�@
��0.5�~�i0.329/�i1.225/189.9�j�{0.5�i0.329/�i0.106/11.56�j
��43.43
| �̐��� | �J�c��̗��� | ����̗��� | �Ԏ���̗��� |
|---|---|---|---|
| �g9. 5/29 | 0.113 | 0.387 | 0.032 |
| �g9. 7/30 | 0.138 | 0.316 | 0.036 |
| �g9. 9/24 | 0.054 | 0.280 | 0.023 |
| �g9. 11/25 | 0.024 | 0.242 | 0.015 |
| �N4������ | 0.329 | 1.225 | 0.106 |
| �N�ԑ����� | 43.43 | 189.9 | 11.56 |
�i15�j�����@
�����̗��ʂ͎s���N4���ԑ��肵�Ă���B�ȉ��̎��ŔN�ԗ��ʂ𐄌v�����B
�����̔N�ԗ��ʁ�0.5�i������4���Ԃ̗���/(�����4���Ԃ̗���/����̔N�Ԃ̗���)�j�@
�{0.5�i������4���Ԃ̗���/�i�Ԏ����4���Ԃ̗���/�Ԏ���̔N�Ԃ̗���)�j�@
��0.5�~�i0.01/�i1.225/189.9�j�{0.5�i0.01/�i0.106/11.56�j
��1.32
| �̐��� | �����̗��� | ����̗��� | �Ԏ���̗��� |
|---|---|---|---|
| �g9. 5/29 | 0.001 | 0.387 | 0.032 |
| �g9. 7/30 | 0.001 | 0.316 | 0.036 |
| �g9. 9/24 | 0.003 | 0.280 | 0.023 |
| �g9. 11/25 | 0.005 | 0.242 | 0.015 |
| �N4������ | 0.010 | 1.225 | 0.106 |
| �N�ԑ����� | 1.320 | 189.900 | 11.560 |
�i16�j�������ʁ@
�����Z���^�|�ł�7�s���̔r�����������Ă���B���v�����ʂ�32.3�~106���R
�ł���B�������Ύs�̕��S��17.2�~106���R�ł���B�ȉ���7�s���̉������ʂ�\������B
| �����̖� | �N�ԗ��� | �����̖� | �N�ԗ��� |
|---|---|---|---|
| ���Ύs | 17.22 | �͓��� | 0.035 |
| �s�蒬 | 2.53 | ������ | 1.37 |
| ���v�s | 5.90 | �V������ | 0.061 |
| ������s | 5.16 | 7�s�����v | 32.27 |
| ���� | ���� | �o�T | ���o | ���� | �o�T |
|---|---|---|---|---|---|
| �J�� | 265.7 | �C�ے� | ������ | 223.0 | ���v |
| �㐅�� | 20.9 | �����z���� | ������ | 17.2 | �Z���^�[ |
| �H�Ɨp�� | 1.4 | �V���� | �Ԏ��� | 11.6 | ��錧 |
| �ȈՐ��� | 1.8�s�������v | �J�c�� | 43.3 | ���v | |
| ��p���� | 0.2 | �V | ����� | 1.3 | �V |
| �l���� | 2.0 | ���v | |||
| ���E���L�� | 228.0 | ���v | �n���Z�� | 223.0 | ���v |
| ���v | 520 | 520 |
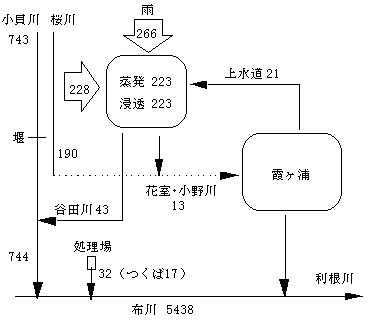
| �f�[�^ | �Z�x | �o�T | �f�[�^ | �Z�x | �o�T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �J�� | 0 | ���v | 9 | ����i����V�c�j | 3.1 | ���� |
| 2 | ������ | 0 | ���v | 10 | �Ԏ��� | 2.2 | �V |
| 3 | �Z���� | 2.3 | ���v | 11 | ���L��i�㗬�j | 2.6 | �V |
| 4 | �㐅�� | 0.4 | ���������v | 12 | �i�����j | 2.4 | �V |
| 5 | �H�Ɨp�� | 0.5 | �V���� | 13 | ������i�z��j | 3.4 | �V |
| 6 | �ȈՐ��� | 0.4 | �s�������v | 14 | �J�c�� | 2.5 | �V |
| 7 | ��p���� | 0.4 | �V | 15 | ����� | 2.2 | �V |
| 8 | �l���� | 4.8 | ���v | 16 | ������ | 15.3 | �����Z���^�[ |
���ɁA�e�f�[�^�̏ڍׂ������B
�i1�j�J�ʁA�i2�j�����ʁ@0.0(mg/l)�Ƃ���B
�i3�j�Z���ʁ@
�c�̑���l���Ƃ���2.3(mg/l)�Ƃ���B
�i4�j�㐅���@
��錧�������v���璂�f�Z�x��0.4(mg/l)�ł������B�ȉ��ɑ��茋�ʂ�����
�i�P�ʁFmg/l�j�B����i�V�F����3���j��0.4(mg/l)�ȉ��ł���B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x |
|---|---|---|---|
| �g9. 4/ 22 | 0.28 | �g9. 9/ 17 | 0.52 |
| �g9. 5/19 | 0.52 | �g9. 10/ 21 | 0.30 |
| �g9. 6/ 17 | 0.38 | �g9. 11/ 18 | 0.30 |
| �g9. 7/ 15 | 0.55 | �g9. 12/ 16 | 0.19 |
| �g9. 8/ 19 | 0.56 | ���� | 0.40 |
�i5�j�H�Ɨp���@
���f�Z�x��0.5(mg/l)�ł������B����i�W�F�H�Ɨp���j��1.0(mg/l)�ȉ��ł���B
�i6�j�ȈՐ����@
�s�̐������v�����Ƃ�0.4(mg/l�j�Ɛ��v�����B����i�V�F����3���j��0.4(mg/l)
�ȉ��ł���B
�i7�j��p�����@
�s�̐������v�����Ƃ�0.4(mg/l�j�Ɛ��v�����B����i�V�F����3���j��0.4(mg/l)
�ȉ��ł���B
�i8�j�l�����i�n�����j�@
�l�����̃f�[�^�͂��Ύs���ł�1�ӏ������Ȃ��������߁A����36�J���̒l�̕�
�ϒl���Ƃ����B1.0(mg/l)�ȉ��̒l�͕s���o�ƂȂ��Ă��邽��0.5(mg/l)�Ƃ��Čv�Z�����B�e�l
�͉��\�i�P�ʁFmg/l�j�̂Ƃ���ł���A���ς�4.8(mg/l)�ł������B
| �ԍ� | ���ݒn | ���f�Z�x | �ԍ� | ���ݒn | ���f�Z�x | �ԍ� | ���ݒn | ���f�Z�x | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ���ˎs | 2.6 | 13 | ��Ԓ� | 1.3 | 25 | �ʗ��� | 9.5 | ||
| 2 | �����s | 1.3 | 14 | �␣�� | 2.1 | 26 | ������ | 6.0 | ||
| 3 | ���َs | 2.1 | 15 | �߉ϒ� | 11.0 | 27 | �V����(1) | 3.8 | ||
| 4 | ���� | 13.0 | 16 | ���쑺 | �s���o | 28 | �V����(2) | �s���o | ||
| 5 | ���َs | �s���o | 17 | ���{�� | 2.8 | 29 | �V����(3) | �s���o | ||
| 6 | �헤���c�s | 1.9 | 18 | ������ | 7.1 | 30 | �ɓޒ� | �s���o | ||
| 7 | �����s | �s���o | 19 | ���� | 8.9 | 31 | ���a�� | 17.0 | ||
| 8 | �k���s | �s���o | 20 | �g�蒬 | 2.1 | 32 | ����㒬 | 11.0 | ||
| 9 | ���Ύs | �s���o | 21 | ������ | 7.9 | 33 | ����(1) | 2.2 | ||
| 10 | �Ђ����Ȃ��s | 4.4 | 22 | �k�Y�� | 24.0 | 34 | ����(2) | 4.2 | ||
| 11 | �����s | 4.9 | 23 | �͓��� | 2.1 | 35 | ������ | �s���o | ||
| 12 | ���엢�� | �s���o | 24 | ���쑺 | �s���o | 36 | ���v�s | 13.3 |
�i9�j����@
�{�����ł̑���l�́�3.1(mg/l)�ł������B�ȉ��A�Q�l�Ɏs�̑���l�������B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x | ���� |
|---|---|---|---|---|
| �g9. 5/30 | 2.0 | �g9. 11/25 | 1.8 | 2.3 |
| �g9. 8/4 | 1.4 | �g10. 1/26 | 3.2 | |
| �g9. 9/25 | 2.3 | �g10. 3/16 | 3.0 | |
| �g11. 6/4 | 3.1�� |
�i10�j�Ԏ���@
�{�����ł̑���l�́�2.2(mg/l)�ł������B�ȉ��A�Q�l�Ɏs�̑���l�������B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x | ���� |
|---|---|---|---|---|
| �g9. 5/29 | 1.7 | �g9. 11/25 | 1.3 | 1.8 |
| �g9. 7/30 | 1.4 | �g10. 1/26 | 2.7 | |
| �g9. 9/24 | 1.5 | �g10. 3/16 | 2.1 | |
| �g11. 6/4 | 2.2�� |
�i12�j���L��i�����j�@
�{�����ł̑���l�i�g11.5/28�j�́�2.4(mg/l)�ł������B
�i13�j������i�z��j�@
�{�����ł̑���l�i�g11.5/28�j�́�3.4(mg/l)�ł������B�@
�i14.1�j���J�c��@
�{�����ł̑���l�́�2.9(mg/l)�ł������B�ȉ��A�Q�l�Ɏs�̑���l�������B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x | ���� |
|---|---|---|---|---|
| �g9. 5/29 | 2.2 | �g9. 11/25 | 2.4 | 2.7 |
| �g9. 7/30 | 1.2 | �g10. 1/26 | 3.7 | |
| �g9. 9/24 | 2.6 | �g10. 3/16 | 3.8 | |
| �g11. 6/10 | 2.9�� |
�i14.2�j���J�c��@
�{�����ł̑���l�́�2.5(mg/l)�ł������B�ȉ��A�Q�l�Ɏs�̑���l�������B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x | ���� |
|---|---|---|---|---|
| �g9. 5/29 | 2.7 | �g9. 11/25 | 2.9 | 3.5 |
| �g9. 7/30 | 1.4 | �g10. 1/26 | 5.1 | |
| �g9. 9/24 | 3.1 | �g10. 3/16 | 5.6 | |
| �g11. 6/10 | 2.5�� |
�i15�j�����@
�{�����ł̑���l�́�2.2(mg/l)�ł������B�ȉ��A�Q�l�Ɏs�̑���l�������B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x | ���� |
|---|---|---|---|---|
| �g9. 5/29 | 1.7 | �g9. 11/25 | 3.5 | 3.6 |
| �g9. 7/30 | 0.9 | �g10. 1/26 | 5.7 | |
| �g9. 9/24 | 3.7 | �g10. 3/16 | 6.2 | |
| �g11. 6/10 | 2.2�� |
�i16�j�������@
���������̒��f�Z�x��15.3(mg/l)�ł������i�o�T�F�����Z���^�[�j�B
�i17�j�����Y�،��搅��@
��錧�������v���璂�f�Z�x��0.9(mg/l)�ł������B�ȉ��Ɍ��̑��茋�ʂ������i�P�ʁFmg/l�j�B
| �̐��� | ���f�Z�x | �̐��� | ���f�Z�x |
|---|---|---|---|
| �g9. 4/8 | 0.95 | �g9. 9/2 | 0.78 |
| �g9. 5/13 | 1.30 | �g9. 10/7 | 0.79 |
| �g9. 6/3 | 0.89 | �g9. 11/4 | 0.67 |
| �g9. 7/1 | 1.20 | �g9. 12/2 | 0.84 |
| �g9. 8/5 | 0.88�� | ���� | 0.93 |
�ȏ�̒l�ɁA���ʂ������Ă��Ύs�̔N�Ԃ̒��f�������̗���𖾂炩�ɂ����B���� �̖w�ǂ͍���E���L�삩��ł���A�㗬����̉����������ɂȂ��Ă���B���o�ʂ́A�n���� �Z�����邩�A�͐�ɗ���邩���Ă���B�������A�������̒��f�ʂ�263.2�g���ƍ����A�l�Ԃ� �ǂ̐���������������̉����ɉe�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
| ���� | ���f�� | �o�T | ���o | ���f�� | �o�T |
|---|---|---|---|---|---|
| �J�� | 0 | ���v | ������ | 0 | ���v |
| �㐅�� | 8.4 | �����z���� | ������ | 263.2 | �����Z���^�[ |
| �H�Ɨp�� | 0.7 | �V���� | �Ԏ��� | 25.5 | ���� |
| �ȈՐ��� | 0.8 | �s�������v | �J�c�� | 116.9 | �V |
| ��p���� | 0.1 | �V | ���͐� | 2.9 | �V |
| �l���� | 9.6 | ��錧 | |||
| ���E���L�� | 640.0 | ||||
| �_��Ȃ� | 4.8 | ���v | �n���Z�� | 500.0 | ���v |
| ���v | 664 | ���v | 909 (mg/l) |
���Ύs�ߕӂł̒��f�̗���͈ȉ��̐}�Ŗ��炩�ɂł���B���Ύs�̕����z���l�� ���Ƃ��A������̒��f�Z�x��}���邱�Ƃ��K�v�ł���B����ł́A�͐�̒��f�Z�x�͔�r�I�� ���A�p����������o�R����x�ɒl�͏㏸���Ă���i�Q�ƁF�Q�l����(1)�j�B
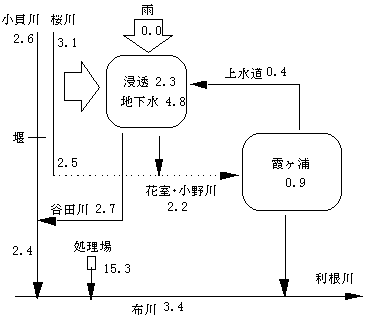
�@�@�@�@�@�@
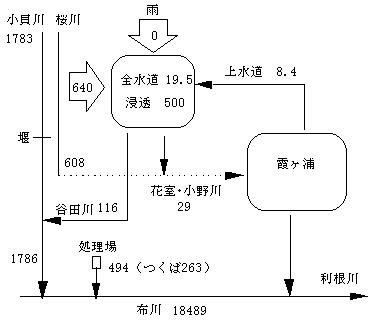
�}2-4-2 ���Ύs�ߕӂ̔N�Ԃ̒��f�̗���i�P�ʁF�g���j
���Ύs�ɗ������Ă��钂�f664�g���̖w�ǂ��A�͐삩��̂��̂ł���B���̂���500�g��
���n���ɐZ�����Ă���B�n�����̒��f�Z�x��4.8�img/l�j�ƁA�͐�̒��f�Z�x���������Ă�
�邱�Ƃ���A���f�������͒n���ɒ~�ς��Ă��鎖��������B����́A�l�ԈȊO�̐��������̉e
�����Ǝv����B�������p�҂̒��f�������̈��S���10.0(mg/l�j�ł��邪�A���f�Z�x�̂�
�����l����ƁA�l�����̗��p�҂͈��S�Ƃ͌����Ȃ��B�㐅���E�ȈՐ����̐����͕K�v�ł�
��B���Ύs�̒��f���חʂ�263.2�g���ł���A����͔p�������ꂩ��̗��o�ʂɓ�����B����
���Ƃ���A���f�������̗ʂ����炷���߂ɂ́A�p��������ł̒��f�������ł��L���Ȏ�i�ł�
��ƌ�����i�Q�ƁF�Q�l����(2)�j�B���݁A�����Z���^�[�ł͒��f�����͍s���Ă��Ȃ��B
���߂ł́A�����Z���^-�ł̒��f���������̂��߂̕��͂��s���B
�@�@�@
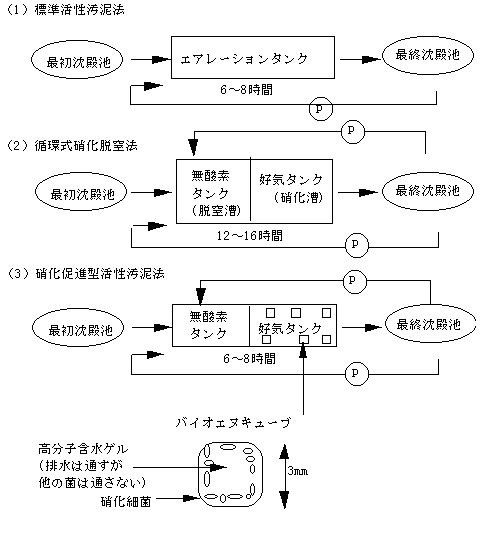
�}2-5-1 �p�������ݔ��̊T�v
�i2�j�y�K�T�X�ɂ�鏜�����̑���
���݂̗����Z���^�[�̒��f��������45.6���ł���B�y�K�T�X�����邱�ƂŁA
���������80���Ɍ���ł���B����ɂ��A���f�������̕����ʂ�494�g����216�g���ւ�
�팸�ł���B����́A�����쉺����̒��f��������1.6���ȏ�������ł��鎖�������Ă���B
�\2-5-1�Ƀy�K�T�X�����Ă���4�̏�����̏�������\������B�����Z���^�[�ł́A
�����ÏW���a�@�Ƌ}���h�ߖ@�����킹�čs���Ă��邽�߁A�ȉ��̐��l��菜�����͍��܂邱
�Ƃ��\�z�����B
�@�@�@�@
| �����ꖼ | ��������(�E/��) | ���� (mg/l) | ���o (mg/l) | ������ (%) |
|---|---|---|---|---|
| �@���I�������� | 11,300 | 40 | 10 | 75 |
| �F�ꍲ�R�Z���^�[ | 2,680 | 49 | 7 | 86 |
| ���O���c�Z���^�[ | 2,800 | 42 | 10 | 76 |
| Bellozanne����������(�p) | 77,760 | 55 | 10 | 82 |
| �����Z���^�[ | 88,000 | 28 | 15 | 46 |
�i3�j�y�K�T�X�̓�����
���ɐݔ������̍H����ɂ��ĕ\������B�����Z���^�[�̃G�A���[�V�����^���N
�ɂ̓T�C�Y��2��ނ���A���ꂼ���1�A��2�n���Ƃ���B��1�n���͌v�揈�����ʂ����
132,000���R�ł���A��2�n���͈��268,000���R �ł���B�H����̊T�Z�́A�J���E�{�H��
�s���Ă�������v�����g���݂Ɉ˗������B�ȉ��ɍH�����\������B�Ȃ��A����͋@�B�ݔ�
�݂̂ł���A�����ɂ͂���ɓd�C�ݔ��̔�p���v���X�����B
| �@�B���i�����^���N�ݔ�) | �`�� | ���� | ���i (��~) | ���l |
|---|---|---|---|---|
| �����Q�[�g | ���S���蓮���� | 24 | 0 | ���� |
| �����X�N���[�� | �������זڃX�N���[�� | 24 | 360,000 | |
| ���_�f�^���N�h�a�� | �����@�B���h�a���u | 72 | 525,600 | |
| ��Œ艻�S�� | 24 | 3,024,000 | �D�C�^���N�ݔ��ꎮ | |
| �D�C�^���N�ݔ� | �S�̕����X�N���[�� | 3A+3B�̕������i | ||
| �i�ɉ����i�^�j �U�C���u | ||||
| �z���H�ݔ� | ||||
| ���ʒ��ߕ� | �d���N�V���t�o�^�t���C�� | 24 | 60,000 | |
| ���ʌv �I���t�B�X�� | 24 | 19,200 | ||
| �@���v | 3,988,800 | |||
| �������� | 289,440 | (�@���?�ɉ����ݔ�)�~0.3 | ||
| ���ڍH���� | 4,278,240 | |||
| �ԐڍH���� | 797,760 | ���H��~0.2 | ||
| �H������ | 5,076,000 | |||
| ��ʊǗ��� | 913,680 | �H�������~0.18 | ||
| ���v | 5,989,680 |
�\2-5-3 ��2�n���̊T�Z�H����
| �@�B���i�����^���N�ݔ�) | �`�� | ���� | ���i (��~) | ���l |
|---|---|---|---|---|
| �����Q�[�g | ���S���蓮���� | 20 | 0 | ���� |
| �����X�N���[�� | �������זڃX�N���[�� | 20 | 400,000 | |
| ���_�f�^���N�h�a�� | �����@�B���h�a���u | 40 | 720,000 | |
| ��Œ艻�S�� | 20 | 5,780,000 | �D�C�^���N�ݔ��ꎮ | |
| �D�C�^���N�ݔ� | �S�̕����X�N���[�� | 3A+3B�̕������i | ||
| �i�ɉ����i�^�j �U�C���u | ||||
| �z���H�ݔ� | ||||
| ���ʒ��ߕ� | �d���N�V���t�o�^�t���C�� | 20 | 60,000 | |
| ���ʌv �I���t�B�X�� | 20 | 20,000 | ||
| �@���v | 6,980,000 | |||
| �������� | 360,000 | (�@���?�ɉ����ݔ�)�~0.3 | ||
| ���ڍH���� | 7,340,000 | |||
| �ԐڍH���� | 1,468,000 | ���H��~0.2 | ||
| �H������ | 8,808,000 | |||
| ��ʊǗ��� | 1,585,440 | �H�������~0.18 | ||
| ���v | 10,393,440 |
�����ŁA3�̈Ăɂ��Č�������B��1�͑�1�n���������A��2�͑�2�n���������A ��3�͑�3�n��������������̂ł���B��1�ł͑��z��59.90���~�A��2�ł�103.73���~�A ��3�ł�163.83���~�ƂȂ�B���݂̗����Z���^�|�̏������ʂ͈��88,000���R �ł��邩���1�n���݂̂̉����ł��قڑS�Ă̒��f�������������ł��邱�Ƃ�������B ���݂̗����Z���^�|�̔N�Ԃ̒��f���o�ʂ�494�g���ŁA���f��������45.6���ł���B �y�K�T�X������ƁA���������80.0���Ɍ��コ���A���f���o�ʂ�216�g���ɂ܂ʼn� �����鎖���ł���B���ɁA�y�K�T�X�������Ƃ��́A�e�s���̕ԍόv��ɂ��ĕ\������B
�i4�j�����̂̕ԍόv���
���݂̔p�������ɂ�����s�����S���́A�r��1���R ������50�~�ł���B���̑��z��
7�s���ŔN��16.06���~�i�\2-5-4�j�ł���B7�s���̉������g�p�����̑��z�́A�N��21.42
���~�i�\2-5-4�j�ł���B���̊z�ɁA���ݔ����悹����7�s���ŕ��S������̂Ƃ���B��
�ݔ�̂����A������̕⏕��55���x������邽�߁A�����̂̕��S�z��45���ł���B���̕�
�S�z���N�s���ĕԍς�����̂Ƃ���B�N�͗��q3����20�N�Ԃŕԍς���Ɖ��肷��B
�N�ԕԍϊz�́A�P����20�Ŋ��������̂Ƃ��A�ȉ��̕\�Ɋe�Ăł̕ԍόv����������B���ʂ�
���āA��1�ł͉�����������11.4���A��2�ł�19.7���A��3�ł�31.1���̑����ƂȂ�B��1�ł�
�قڑS�Ă̒��f�������ł��邽�߁A���_�Ƃ��āA��1���̗p����Η����Z���^�|����̒�
�f�������̕��o�ʂ��300�g���팸���邱�Ƃ��ł���B�����̂̕ԍόv���\2-5-5�Ɏ������B
| �p���������S�� | �g�p�������z | |
|---|---|---|
| ���Ύs | 861,000 | 648,000 |
| �s�蒬 | 127,000 | 200,000 |
| ���v�s | 295,000 | 523,000 |
| ������s | 258,000 | 596,000 |
| �͓��� | 1,800 | 4,200 |
| ������ | 69,000 | 164,000 |
| �V������ | 3,000 | 6,800 |
| ���v | 1,611,800 | 2,142,000 |
| ��1 | ��2 | ��3 | |
|---|---|---|---|
| �v�揈�����ʁE/�� | 132,000 | 268,000 | 400,000 |
| �T�Z�H���� | 5,989,680 | 10,393,440 | 16,383,120 |
| ���ɕ⏕ | 3,294,324 | 5,716,392 | 9,010,716 |
| �����̕��S�z | 2,695,356 | 4,677,048 | 7,372,404 |
| �ԍϑ��z | 4,868,112 | 8,447,268 | 13,315,381 |
| (���q3��20�N�ԍρj | |||
| �N�ԕԍϊz | 243,405 | 422,363 | 665,769 |
| �g9�N�x�������������z | 2,142,000 | 2,142,000 | 2,142,000 |
| �������������� | 11.4% | 19.7% | 31.1% |