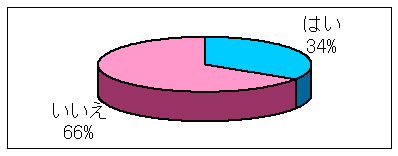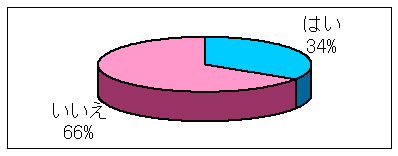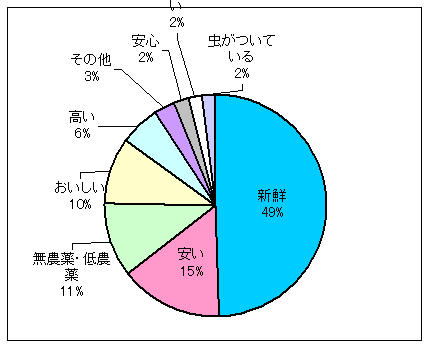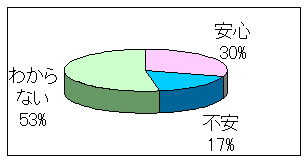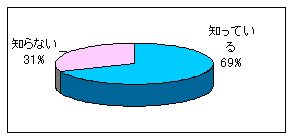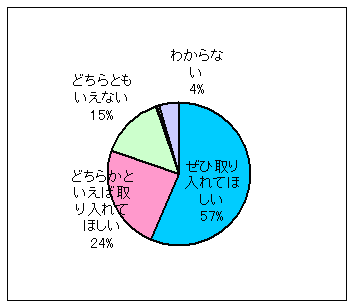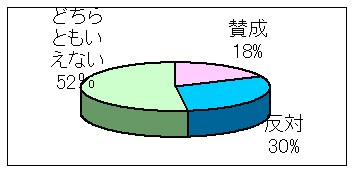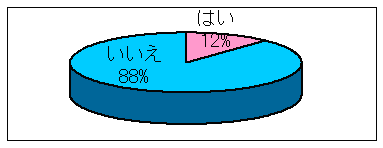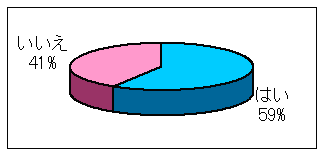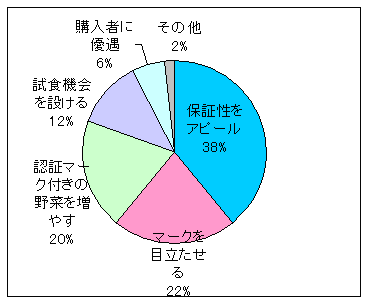課題
これらの調査から私たちは以下の課題を挙げます。
- 消費者と供給者の意識の差
- 学校給食への地場野菜導入
- 農業特区の活用方法
- 認証システムの可能性
- 霞ヶ浦における魚粉の堆肥化事業の可能性
課題に対する調査
①消費者アンケートより
- 『茨城産を意識して購入するか』
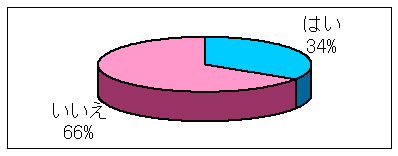
- 『地場野菜のイメージ』
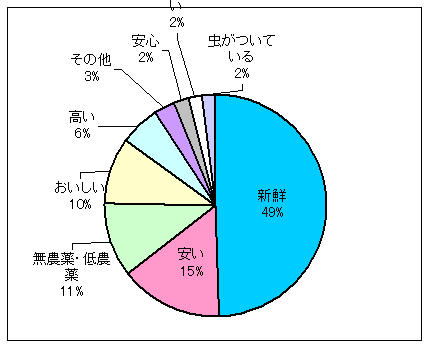
②The garden筑波西武店へのヒアリング
- 『地場野菜に対する意識』
- ・地場野菜コーナーが設けていて、5~10品目の野菜が置かれている。
地場野菜は野菜の売り上げ全体の5~10%を占めている。
・地場野菜は鮮度がよく、消費者の馴染みもある
- 『消費者の意識について』
- ・消費者は野菜購入に対して第一に鮮度、次に価格を重視していると考えている
・最近では「生産者の顔が見える安心・安全」、「少量・適量での使いきりサイズ」、「生産地へのこだわり」という点にも消費者のニーズが高まってきている
・「食品の鮮度感を大切にし、食の安心・安全を意識して自分のライフスタイルに合わせた食品を求めている消費者」を客層として意識している。
このページのトップへ
①消費者アンケートより
- 『給食の食材について』
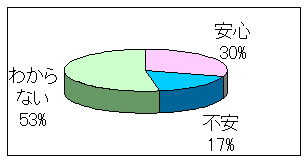
- 『給食に地場野菜が使用されていることの認知度』
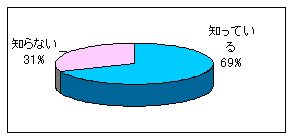
- 『地場野菜の給食への導入について』
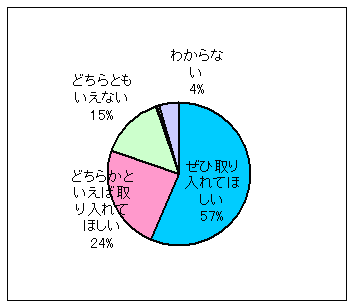
- 『地場野菜導入に伴う給食費の増加について』
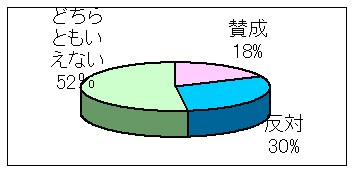
②つくば市学校給食課へのヒアリング
- 『給食で使用する野菜について』
- 給食費の関係もあり野菜を選別する最大の要因は価格である
- 『地元産野菜の使用について』
- 一部で導入しているが、地場野菜が多少高いため予算との兼ね合いのため導入は進んでいない
- 『安全性について』
- 子供たちが口にするものであるから気をつけてはいる
③先行事例の調査
長崎県大村市での地場野菜の給食への導入例
- 学校給食に地場の農産物がほとんど使われていない現状を調査し明らかにする。
- 自給率調査の結果を公表し、保護者に地場産、有機栽培の食材が欲しいかを尋ねる。
明確な数字を出すことで、行政に働きかけやすくなる。
- 給食で使っている食材の量、価格、時期などを正確に調査する。
給食の食材は安い、というイメージあるが、実際は市場での価格とあまり変わらない。
- 地元の農家の生産可能性、その地域の旬などを調べて、出荷量を確定する。
給食の食材の価格と量が提示され、栽培した農産物が確実に学校給食に使用されるという保証があれば栽培する農家は着実に増えていく。
- 既存の食材の給食への流通システムの変更は可能である。
そのために、現在給食に食材を納めている業者との利害調整は不可欠である。新たな流通の提案を行うことで、地場産給食の経済効果、教育効果が確実に高まる
このページのトップへ
- 地場野菜普及拡大の弱点
- 大量供給が保証できないこと
- 野菜の種類に関してバラエティの欠如していること
- 安定供給の保証がないこと
- それぞれの弱点の現状・対策
- 現在の農業構造では見合った利益がでないので農業促進が行われない
- 地場野菜のバラエティの欠如という点では肯定的。
- 安定供給を保証するには、不作に備えて消費量以上の農産物を生産する必要があり、それだけの費用負担を消費者が担うことによって可能
このページのトップへ
①みずほの村市場へのヒアリングより
②JAつくば市へのヒアリング
- 『野菜生産の安全管理』
- 農薬などの使用状況の過程記録を提示している
昨今の食の安全に対する問題のため、低農薬化が進んでいる
- 『認証システムについて』
- JA独自の基準を設けて、それを満たしたものが県の認証を取得している
③つくば市農業課
現在の流通システムの中で、市は茨城県が出した基準をクリアした野菜には
独自の認証シールを貼ることを許可している
④消費者アンケートより
- 『認証シールの認知度』
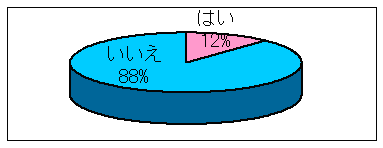
- 『今後の判断基準となるか』
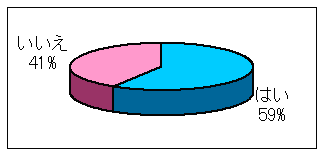
- 『認知度を上げる方法』
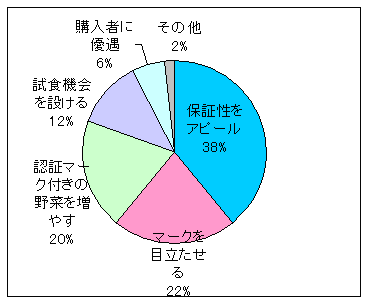
このページのトップへ
- 『魚粉を利用した有機栽培について』
- 有限会社ギルドの有機農家(70軒)に利用してもらう。
魚粉を利用した有機農業が農家経営においてプラスであるとわかれば、慣行農業農家も有機農業に変更しうる。
それにより有機野菜の生産量を増やすことが可能
- 『流通について』
- 現在西友と調整中
有機野菜の売上も前年比150%ずつ成長している
- 『ブランド化』
- 霞ヶ浦で取れた魚を利用した魚粉で作られた野菜であること、
そしてこの野菜を消費することで霞ヶ浦を綺麗にすることができるというブランドの構築
このページのトップへ
考察
1.地場野菜に対する意識の差
消費者は野菜購入時に第一に鮮度、次に価格を重視する。
供給者側の野菜販売の傾向としては、スーパーは価格重視とみられた。
直売所では価格、鮮度、品質など重視する点に様々な傾向がみられた。
店によって野菜販売の傾向に違いはあったが、販売者は消費者が野菜購入時に何を重視しているかについては認識している。
2.学校給食を利用した地場野菜普及の問題点
保護者は、学校給食での地場野菜の導入については肯定的であった。
しかし、導入に伴って給食費が値上げされることについては否定的であった。
給食費の値上げに反対と答えた保護者の中には学校給食へ地場野菜を導入することでなぜ給食費が上がるのかがわからないという意見もあった。
給食費が上がる理由を保護者が正しく認識すれば値上げに賛成する保護者も増えると考えられる。
従って現実的に学校給食へ地場野菜を導入するには、費用負担の面で保護者の理解を得ることが重要であると考える。
3.多品種安定生産のための農業特区の利用
現在農業特区を導入している地域の先行利用方法は、観光農園など客寄せを目的とする利用法が多かった。
特区で現在つくば市で生産量の低い野菜を生産し、地場野菜のバラエティさの欠如を補う手段として活用する必要があると考えられる。
4.認証システムの普及阻害要因と認知方法
現在、認証システムの存在は消費者にあまり知られていない。
またマークを見たことがあっても認証の意味を知っている消費者は少なかった。
認証システムを消費者の野菜購入時の判断基準となるようにするには、認証の意味を消費者が理解する必要がある。
認証をアピールすることで消費者が認証付野菜を意識するようになれば、認証付地場野菜の消費量が増えると考えられる。
提案には認証のアピール方法を提案する
5.霞ヶ浦における魚粉の堆肥化事業の可能性
霞ヶ浦起源の有機肥料を用いて野菜生産を行うことは可能である。
実際アサザ野菜を販売する西友では、有機野菜への需要は高く、現在では年50%の割合で売り上げが増えている。
有機野菜の名前と霞ヶ浦起源の肥料を使用するという点において、アサザ野菜のブランド化は有効であると考える。
食べて霞ヶ浦をきれいにするというキャッチフレーズを利用することも環境問題を意識する上でよい効果がある。
このページのトップへ 次 は提案