2.1 研究の方法
|
つくば市の公民館の現状を知るために、予備調査として文献調査、 公民館職員へのヒアリング調査を行う。さらに住民の意識をさぐるための手段として 公民館利用者及び周辺住民へのアンケート調査を実施する。 その結果を集計・分析することにより現状の公民館に対する不満な点、要望などを明らかにし、 それを考察することでつくば市の既存及びこれからの公民館のあり方を提言していく。 |
2.2 つくば市の公民館の現状(文献調査、ヒアリング調査)
|
つくば市の公民館の利用について文献調査を行ったところ公民館はつくば市に17館あり、 すべての公民館で開館時間は一律9時~22時となっている。 利用者においては1年間で全体の17館で延べ44万人もの利用客がおり、 人口15万5000人のつくば市民が1年間に平均約3回利用している計算になる。 公民館別で見てみると(表1)のように並木公民館の利用が最も多く 年間約66,000人もの人が利用している。 逆に最も利用されていない公民館は南公民館で年間1,100人の利用者しかいない。 南公民館は施設面でも大きく異なり、和室が2部屋しかなく無人であり他の公民館と少し様子が異なる。 また、二の宮、南公民館を除く全公民館では図書館が併設されており、図書の貸し出しも行われている。 そして、吉沼、桜、竹園、並木、広岡の各公民館では出張所が併設されており行政サービスとして、 住民票の発行や印鑑証明などの発行を行っている。 6月2日(金)に小野川、広岡、並木各公民館で公民館職員の方にヒアリング調査を行った。 ヒアリング調査によると、竹園や並木のように利用客の多い公民館では、 予約の受付の日に予約が殺到してホールなど需要の多い部屋はその日に予約で埋まってしまう日もある。 活動の内容としては、公民館主催のメイン事業としての「講座」は定員が全講座あわせて 4000人ほどしかいないこともあり少なくなっている。 趣味の共通した市民が「サークル」の場として利用しているのが現状である。 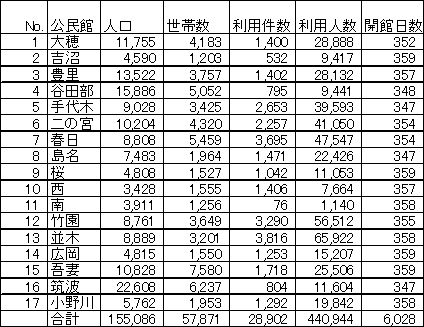
|
2.3 アンケート調査の概要
|
<調査期間> 6月9日(金)~6月14日(水) <調査対象> ①竹園公民館:計画的に整備されたつくば市の研究学園地区の中心にあり、 昭和53年8月開館の公民館 小野川公民館:周辺開発地区と研究学園地区との境界に位置し、両方の 利用客が予想される平成10年1月開館の公民館 ※それぞれの公民館で公民館へ来館された利用者の方々に直接記入式でア ンケートに答えて頂く。 ②公民館周辺の住民:各公民館から半径1km以内の住民を対象に、 訪問配布後、後日回収に伺う。 ※公民館に配布したアンケートは全員が公民館利用者としてアンケートに 答えてもらい、住宅に配布したアンケートでは公民館を利用する人、利 用しない人の両方の意見を聞いた。 ※配布数と回収率は表2の通りである。 <調査項目> 「属性」 性別/年齢/住所/職業/家族構成/居住年数 「利用状況」 利用頻度/交通手段/利用時間帯 「現状と満足度」 活動内容/満足度 「公民館に求めるもの」 アンケート調査の対象公民館を選んだ理由としてつくば市は 周辺開発地区と研究学園地区にわかれている。 2つの地域には年齢や職業の構成の異なった人が住んでいる。 この現状を踏まえ異なった属性の住民の公民館利用について調べようと思い 次の2つの公民館を選んだ。 1つは研究学園地区の中央に位置する竹園公民館である。 周辺が公務員住宅に囲まれていて人口密度が高い地域で、 公民館の利用人数は並木公民館についで多い。 もう1つの小野川公民館は研究学園地区と周辺開発地区の境界付近に立地するため 両方の利用者が予想される。また平成10年1月開館と、施設が新しく充実している。 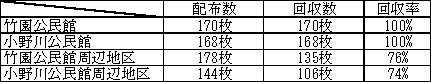
|
2.4アンケートの結果
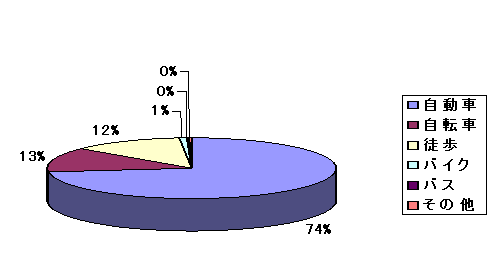 図2.1:公民館利用者の交通手段 上の図より公民館利用者の交通手段としては4分の3もの人が自動車を利用しており、 次頁の図2.1のグラフからも分かるように対象地区の住民の利用者はそれほど多くない。 また、下のグラフは、職業別の自宅からの距離の満足度であるが、 どの職業においても自宅からの距離にはあまり不満は見られないことが分かる。 以上のことより、公民館の講座、サークルに魅力があれば、例え公民館が遠かったとしても その活動を求めて利用者はやってくるということが言える。 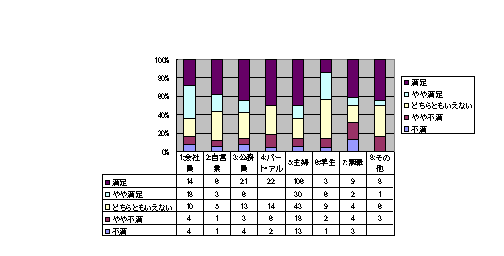 図2.2:満足度(自宅からの距離) また、竹園公民館と小野川公民館を選んだ理由として、 地域によっての住民の公民館に対する考え方の違いがあるのではないかと考えたためである。 そこで、下の2図(図2.3・図2.4)は小野川と竹園それぞれの公民館利用者と住民に聞いた 公民館に求めるものの違いであるが、下の図を見る限り、 年齢の違いによる公民館に求めるものの違いはあるものの、 小野川、竹園のそれぞれの地域においての違いは見られなかった。 よって、小野川と竹園の地域による違いは考えないことにし、 年齢や職業といった属性の違いによっての意識の違いを調べることにした。 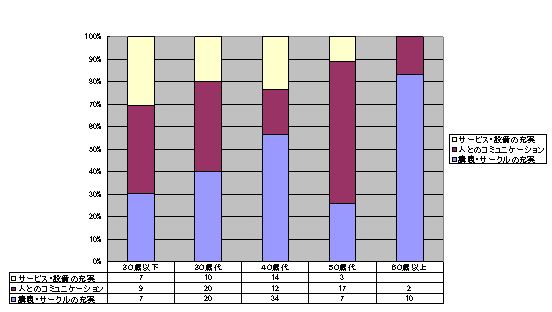 図2.3:年齢別による求めるものの違い(小野川) 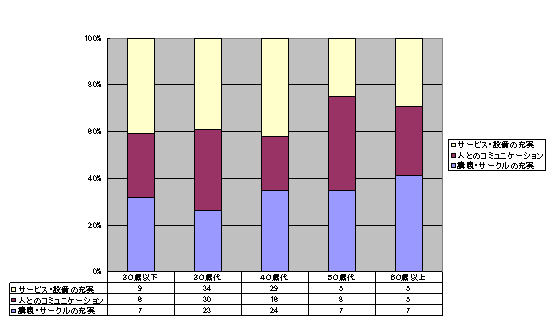 図2.4:年齢別による求めるものの違い(竹園) まず、公民館が「地域づくり」の場として実際に使用されているのかを分析した。 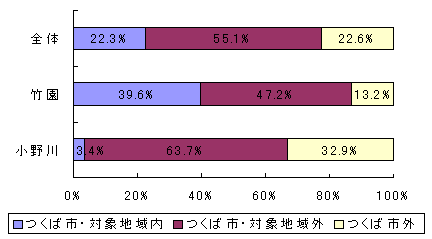 図2.5 公民館利用者の居住地域 図2.5は、それぞれの公民館を利用する人の居住地域を表わしたものである。 周囲が公務員住宅で人口密度の高い竹園公民館の利用者でさえ 対象地域内から来ている人は40%ほどとなっている。 半分以上は対象地域外に居住する人の利用ということになる。 周辺地区の小野川公民館に関しては、対象地域内に居住する人の利用率は3%しかおらず、 ほとんどの利用者は対象地域外に居住する人である。 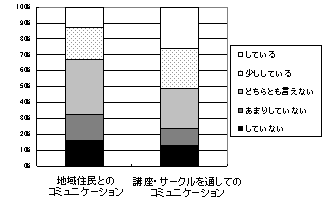 図2.6 公民館でのコミュニケーションの現状 図2.6は公民館で行われているコミュニケーションが、 講座・サークルを通しての仲間同士のコミュニケーションか、 地域住民とのコミュニケーションであるかを表わしたものである。 この図より、住民が公民館において地域住民のコミュニケーションよりも、 講座・サークルを通してのコミュニケーションを重視していることが分かる。 以上のことより、公民館は実際に「地域づくり」の場としては あまり利用されていない現状が明らかになった。 次に、年齢別、職業別に公民館の利用にどのような差があるのかを分析した。 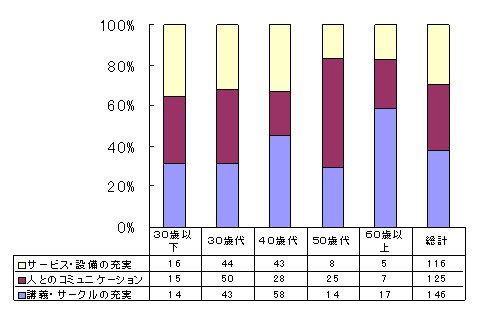 図2.7 年齢別の公民館に求めるものの違い 図2.7は公民館において、サービス・設備の充実、人とのコミュニケーション、 講座・サークルの充実とどの項目を最も重視すべきかを表わしたものである。 50代の人は、人とのコミュニケーションを最も重視していることが分かった。 これは子供が成長して子供を通じての親との交流がなくなったからではないかと考えられる。 60代の人は生涯学習などの講座・サークルの充実を重視していることが分かった。 これは老後の新たな趣味を持とうと考える人が多いからだと考えられる。 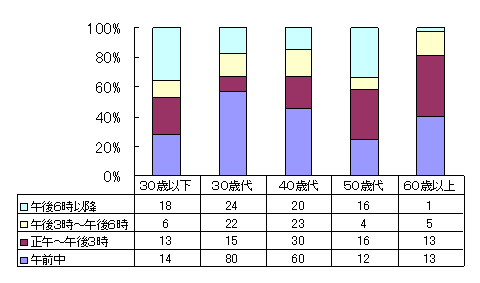 図2.8 年齢別の利用時間帯の違い 図2.8は年齢別の利用時間帯の違いを表わしたものである。 30代、40代は午前中の利用が多いと読み取れる。 また、20代、50代は他の年齢層に比べて夜間の利用が多くなっている。 これは、20代の人は家族を持っていない人も多く、 また働いている人も多いため夜しか活動できないと考えられる。 50代の人は子供が成長して、夜間にも自分の自由な時間が持てるようになったためだと考えられる。 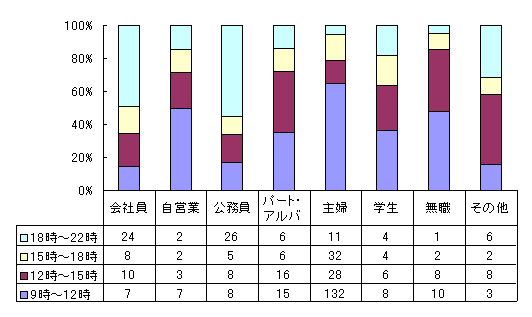 図2.9 職業別の利用時間帯の違い 図2.9は職業別に公民館の利用時間に差があるかを見たものである。 主婦と、自営業の人の午前中の利用率の高さが目立つ。 図4から分かったことも踏まえ、30代、40代の主婦の人の午前中の利用率はかなり高いといえる。 これは、子供がまだ小さいために子供が学校へ行っている間の午前中にしか、 自分の自由な時間を持てないからだと考えられる。 主婦の夜間の利用率が低いことは家族の食事の用意や片付けなど 家事をしなければならないからだと考えられる。 逆に、会社員、公務員の人の夜間の利用率が高くなっている。 土日以外は仕事のために夜間くらいしか活動できないのが原因だと考えられる。 このように年齢や、属性によって利用時間や公民館に求めるものに大きな違いがあることが分かった。 |
2.5 アンケートの考察
|
アンケートの結果によると、住民が公民館が求める行政サービス・設備の充実、 人とのコミュニケーション、講座・サークルの充実の3つに大きな差は見られないが、 講座・サークルを通じてのコミュニケーションを重視する傾向が強かった。 年齢別に見てみると、50代がコミュニケーションを重視するのに対し、 60代は生涯学習などの講座・サークルを重視する傾向が強い。利用時間帯においては、 職業別に大きく異なることが分かった。公務員や会社員といった働いている人の利用は夜間が多く、 主婦や自営業の人は午前中の利用率が高くなっている。このように属性によって公民館に求めるもの、 利用時間帯など大きく異なることが分かった。 行政の位置付けとしては公民館には対象地区が設定され、 公民館は「地域づくり」の場とされている。 しかし、アンケート調査の内容からも分かるように対象地区内からの利用者は 半分も占めていないのが現状である。また、地域住民とのコミュニケーションよりも、 講座、サークルを通してのコミュニケーションを重視していることからも、 公民館はいろいろな地域から来る趣味の合う仲間同士のコミュニケーションをはかるために 利用されているのが現状で、「地域づくり」としてあまり役割を果たしていないといえる。 そして、公民館が「地域づくり」の役割を果たしていないこと、 また、住民も公民館に地域住民のコミュニケーションをあまり求めていないことからも 公民館を「地域づくり」の場という位置付けに縛られることはないと考えた。 また、つくば市は研究学園都市として25年前に開発され、昔から人の住む周辺開発地区と、 新しく転入してきた人の住む研究学園地区には各属性に大きな偏りが見られる。 特に公務員住宅では、定期的に人が入れ替わるため常に若い人が居住しているのが特徴的である。 このようなつくば市特有の属性の偏りのある地域の公民館では、 求めるサークルも利用時間帯にも偏りが生じ、施設が手狭になっているところもある。 また、様々なソフト面、ハード面の要望にそれぞれの公民館ですべてに対応した完璧な公民館を 目指そうというのは物理的、経済的に難しいといえる。 |
←Back 目次へ戻る Next→