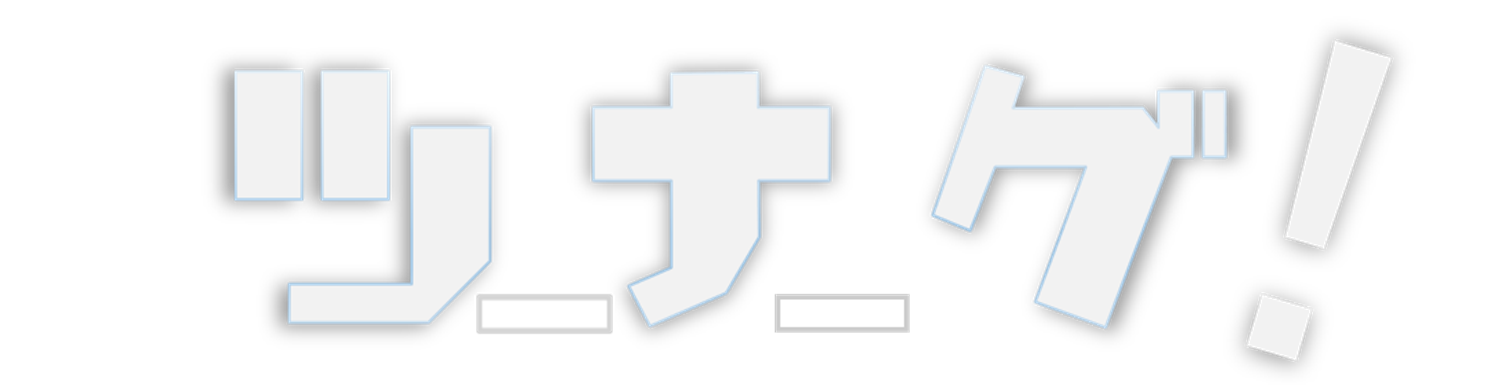授業目的
20世紀は経済成長と人口増加を背景とした都市拡大の時代でした。そこでは都市の効率性追求と、拡大する都市においていかに土地利用秩序を保持するかが都市計画に課せられた課題であったといえます。しかし21世紀は、少子高齢化・人口減少を背景として、都市の成熟化を模索する時代です。成長時代の都市計画とは全く異なり、都市のコンパクト化、都市生活の質的向上、減少する財政を前提とした健全な自治体経営が求められています。さらに環境問題への対処や頻発する自然災害への対応も都市の新たな課題として提示されています。また、地方分権が進み、市民協働、市民参加への社会的関心も高まるなど、都市計画を取り巻く状況は大きく変わっています。このような変化の中で、市町村が策定する市町村マスタープラン(都市計画MP)や総合計画は、その意義と真価が今まさに問われているといえます。
上記の問題意識のもと、本実習では土浦市を事例対象として都市計画MPの策定に取り組んでいきます。従前の都市計画MPでは20年後の将来都市像を展望し、10年程度で目標設定することを意図していました。しかし現在のように将来を見通すことが困難な時代にあっては、MPに求められる役割自体も変わってきています。不確定な将来に柔軟に対応するとともに、かつ現存する様々な課題を統合的に扱っていく必要があります。そのため、土地利用や交通だけでなく、福祉、教育や、地球環境、景観形成、防災、さらには中心市街地活性化、子育て環境、観光、国際化、バリアフリー、コミュニティ・ビジネスなどを包含し、限られた財政資源の中で各種施策を統合的に展開していける計画が求められているのです。本実習では先進的な分析・評価ツールを駆使しながら議論し、新たなMPの姿を具体化していく作業を通じて、「プランナー」として実社会をリードしていける人材の育成を目指しています。
全体スケジュール
以下の側面に重点を置く。
・客観性を確保するために、モデル分析を積極的に取り入れる。土地利用・交通相互作用モデル(CUET:応用都市経済モデル)、交通量推計モデル(JICA Strada)を中心に、GIS(Arc-GIS)、景観シミュレーション、費用対効果分析、コーホート分析、統計分析等を用いて計量的に検証する。
・見学、講演、ヒアリング、アンケート、土浦市での発表会を通して、現場に根ざした実践的まちづくりを体験する。各論にとらわれすぎず、バランスに配慮したプラン作りに努める。特に、土浦市関係者など行政、市民との情報交換により、実行可能性を検討する。
・合意形成を円滑にするため、視覚的手法やプレゼンテーションを重視する。
実習を5週単位で3分割し、以下の手順で進める。
第1部(10月~11月):課題の抽出,方針・定性的対策の提示(課題発見)
講義、見学、土浦関連資料から、「都市計画MP」の全体構造を学ぶ。将来人口推定等現況分析を通して、さらにはアンケート、ヒアリング、データ分析から新たな情報を収集し、土地利用、交通、景観などを部門別に、かつ地域別に課題を抽出し整理する。そして、これらの課題を踏まえて、マスタープランで議論すべき内容を検討する。
第2部(11月~12月):定量的評価方法の修得とプロジェクトの個人提案
CUET、JICA Stradaのモデル分析演習により習得する。現状及び将来の交通混雑や環境負荷を予測・計測し、目標都市像を実現するための各種施策の効果を分析する。同時に、地理情報システムや景観シミュレーション等を用いて視覚化する。
また、第1部において学んだこと、あるいはこれまで学習した知識を反映させ、土浦市において実施すべきプロジェクトを個々人(または小グループ)で考え、提案する。
第3部(12月~2月):計画案の作成(総合調整)
地域別構想を提示し、つくば市及び茨城県南、首都圏との広域連携を含めて周辺市町村計画や上位計画などと整合の取れた都市計画MPの核となる計画案を策定する。さらに、財政、合意形成、公平性、マネジメント(体制・組織、政策評価など)の観点から、実効性を検証する。また、都市計画MPのモニタリング方法も提示する。
また、10月11日(金)に土浦視察を行う。
なお、最終発表会は2月7日(金)に土浦市亀城プラザで実施する。
最終発表会には、土浦市長、土浦市職員、土浦市民、スペシャルコメンテータも参加する。
出席者の投票により、最優秀グループを選出する。