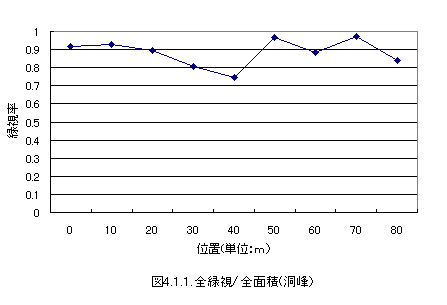
*ペデの緑地景観が通行者に与える不安感の検証*
4-1 洞峰地区の分析
4.1 洞峰地区の分析
最初にこの地点の景観の連続的な変化を見るために、ここを緑に覆われ視界が狭いことにより不安感を抱く区間、視界が広く不安感を抱かない区間に分類した。
*不安感を抱く区間 … 0〜20m、40〜70m
*不安感を抱かない区間 … 20〜30m
(緑量について)
まず、不安感を抱く→抱かないという景観の変化が、緑量によって説明できないか検討した。そこで各ポイントの写真の緑視率を算出した。
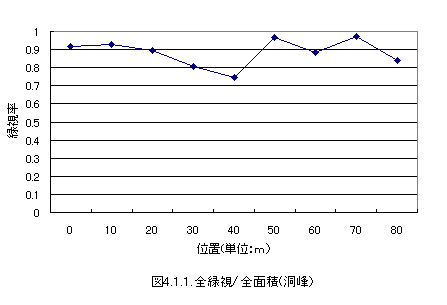
[図4.1.1]… 各区間の写真に占める緑視率
上の考察結果より、不安感を抱かない区間より抱く区間の方が、緑量が多いことが分かった。これは私たちが予測していた結果とほぼ一致していた。
なおこれ以降は、仮説の検証のために、視野の広がりに最も関係する目線の高さ(1.0〜2.5m)の緑に焦点を絞った。そして目線の高さの緑視率を算出し、上の図と比較した。
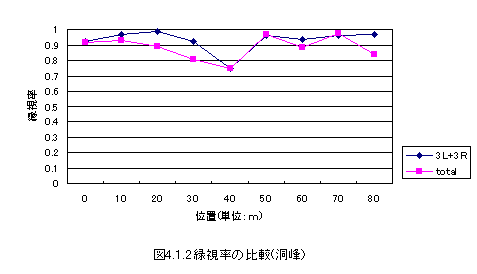
[図4.1.2]… 各区間の写真に占める緑視率とゾーン3全体の緑視率
〈考察〉
*ゾーン3全体の緑視率の変化は、写真全体の緑視率と変わらない
上の考察結果では、目線の高さの緑量が人に不安感を抱かせる要因になるかどうかはっきりしない。そこで私たちは、緑量によって受ける圧迫感が、道沿いの木々の緑によるものと、周辺の緑によるものとに分けられると考えた。よって各ゾーンの緑を次のように分けた。
*ペデ内部の緑:歩道から1.5メートル以内の緑
*ペデ外部の緑:歩道から1.5メートル以上離れている緑
そして、ゾーン3全体の緑視率とゾーン3のペデ内部の緑視率を算出した。
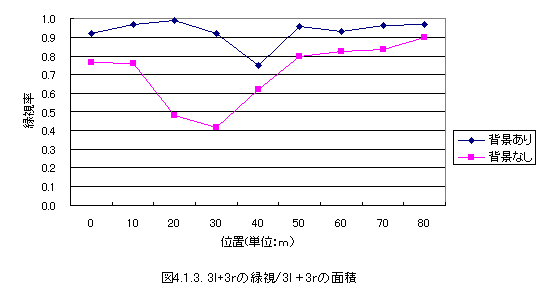
[図4.1.3]… ゾーン3のペデ内部の緑視率とゾーン全体の緑視率
〈考察〉
*不安感を抱く区間については、両者の緑視率にあまり差はない
*不安感を抱かない区間では、ゾーン全体の緑視率はわずかに減少しているが、ペデ内部の緑視率
はさらに大きく減少し、両者の緑視率の差は相対的に大きい
上の考察結果より、ペデ内部で目線の高さの緑量が相対的に少ないと、人は不安感を抱かないのではないかと考えられる。そこでさらに、ペデ内部の緑視率について、ゾーン3と他のゾーンを比較した。
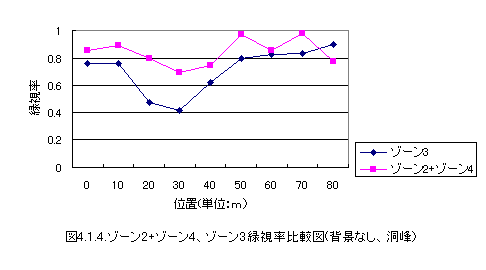
[図4.1.4] … ペデ内部のゾーン3の緑視率とゾーン2+ゾーン4の緑視率
〈考察〉
*不安感を抱く区間では、それぞれの緑視率に大きな差はない
*不安感を抱かない区間では、ゾーン3の緑視率の方が相対的に低い
以上の考察結果より、不安感を抱かない区間では、ペデ内部のゾーン3の緑量が特に少ないことが分かった。これはつまり、目線の高さの視界が他のゾーンより広く、不安感を構成する孤立感や圧迫感が解消されているといえる。
(道幅について)
次に、不安感を抱く→抱かないという景観の変化が、道幅によって説明できないか検討した。
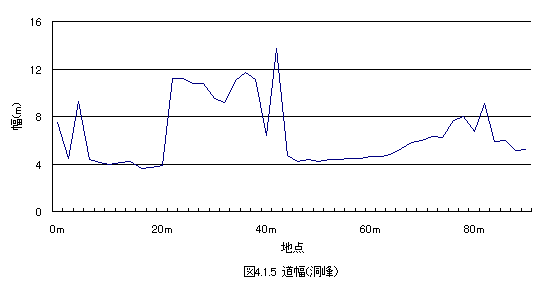
[図4.1.5] … 道幅(各ポイントを挟んだ木と木の距離)の変化
〈考察〉
*不安感を抱く区間の道幅は相対的に狭い
*不安感を抱かない区間の道幅は相対的に広い
上の考察結果は、不安感を抱く区間では、通行者と最も近い緑までの距離が近く、逆に抱かない区間では遠いことを表わしている。つまり、道幅の広さも人に不安感を抱かせる要因になるということができる。
以上の分析により次の結論を得た。
(結論)
4-2 センター地区の分析
4.2 センター地区の分析
このポイントでは、東京家政大学の広場の不安感を抱かない区間(0-10m)、道が狭まり不安感を抱く区間(20-50m)、エキスポセンターの前の開けた、不安感を抱かない区間(70-100m)と分類分けをした。
まず、各地点の写真全体に占める緑の割合(緑視率)であるが、図4.2.1を見ると、不安感を抱かない区間(0-10m)では低いが、不安感を抱く区間(20-50m)ではそれに比べて高くなっている。そしてエキスポセンターの前の不安感を抱かない区間(70-100m)で値はまた低くなっている。このことから緑量が何らかの形で通行者に影響を与えていることがわかる。
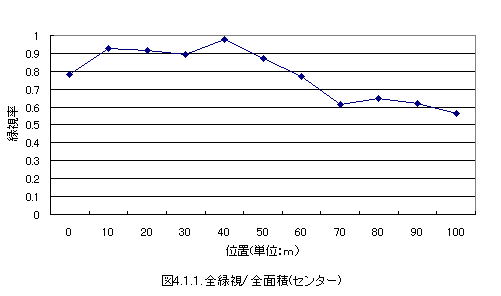
次に目線の高さにおける緑の中でもペデ内部の緑の方が外部の緑よりも通行者に与える影響は大きいと考えられるので、次は目線の高さにおける緑の中でもペデ内部の緑について考えてみる。
図4.2.2より、ペデ内部の緑の緑視率は不安感を抱く区間(20-50m)では不安感を抱かない区間(70-100m)に比べて高くなっている。これはペデ内部の緑が影響を与えていることを表している。そして、エキスポセンター前の不安を抱かない区間(70-100m)についてだが、ここでは目線の高さの緑視率は徐々に増加しているが、ペデ内部の緑は70-80mで減少して、それ以後は低い値を保っている。これは全体の緑視率が増加しても、人に近い緑視率が減少していれば、人は不安感を抱かないということを表している。つまり、人に最も大きな影響を与えているのは、目線の高さにおける緑で人の近くにある緑ということになる。その部分の緑が増加すると通行者は不安感を抱くということである。
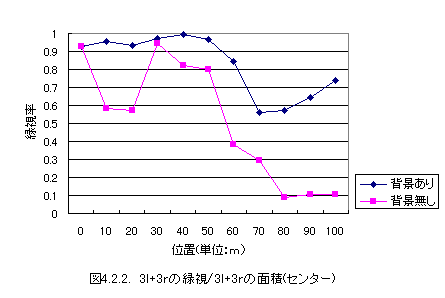
次に目線の高さにおける緑の緑視率とそれ以外の緑の緑視率とを図4.2.3で比べてみる。ゾーン2+ゾーン4と目線の高さであるゾーン3の緑視率を比べるとゾーン3の変化のほうが2+4に比べて大きく、不安感を抱く区間(20-50m)では高く、不安感を抱かない区間(70-100m)では低くなっている。 このことからも目線の高さの緑視率は人に大きな影響を与えていることが分かる。
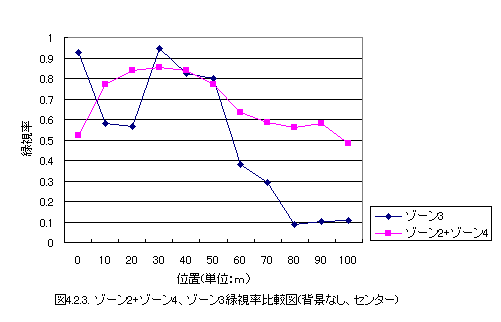
しかし、ペデ内部の目線の高さにおける緑でも説明がつかない地点がある。そこで、次は道幅について考えてみる。道幅はその地点のものではなく、10m先の目から見える場所のものを使うことにする。また、ここでの道幅とは道の両側にある木から木までの距離のことを意味する。
図4.2.4を見ると不安感を抱かない区間(70-100m)の道幅は広く、不安感を抱く区間(20-50m)の道幅は狭くなっている。0-10m区間は、目線の高さの道に接している緑視率が高かったにもかかわらず、不安を抱かない区間となっているが、これはその地点の道幅と前方の道幅が広いため、視界が広く、圧迫感をあまり感じないので、不安感を抱かない区間になったと考えられる。つまり、目線の高さの緑視率が高くても、道幅が広ければ、通行者は不安感を抱かないというこである。
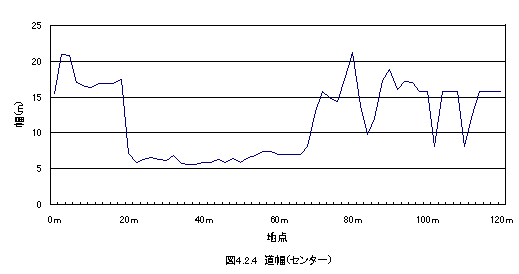
これらのことから、目線の高さで道に接している緑の緑視率が高いと人は不安感を抱くということ、もしその値が高くても道幅が広ければ人は不安感を抱かないということが予想される。
4-3 二の宮地区の分析
4.3 二の宮地区の分析
4.3.1 はじめに
この節では、二の宮地区の緑視率についての分析をする。
まずは、前提条件として、どの区間が不安を抱く区間なのかを説明する。二の宮地区では、実際に現地を歩いてみた結果、0m付近と、60〜80m区間が不安感を抱かない区間で、、0〜
60m区間が不安を抱く区間であるという結果になった。この節では私たちが不安感を抱いた区間と、各種緑視率の関係について分析する。
4
.3.2 全緑視率についての分析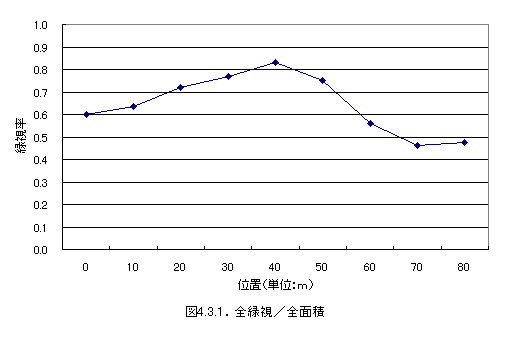
まずは、写真全体に占める緑の割合(全緑視率)について分析する。まずは、図
4.3.1を見ていただきたい。この図より分かることは、不安感を抱かない区間での緑視率が、不安感を抱く区間に比べて相対的に低いということである。いっぽうで、不安感を抱くような区間の緑視率は、不安感を抱かない区間の緑視率に比べて、相対的に高くなっている。このことより、視野全体に占める緑視率は、不安感と関係があるのではないかと推測できる。
4.3.3 目線レベルの緑視率についての分析
先の分析で、全緑視率が不安感と何らかの関係があることが分かった。そのため、次に特にどのエリアの緑視率が不安感と強い関係にあるのかを分析する。ここでは、目線レベルのゾーンでの緑視率をとりあげて分析していく。
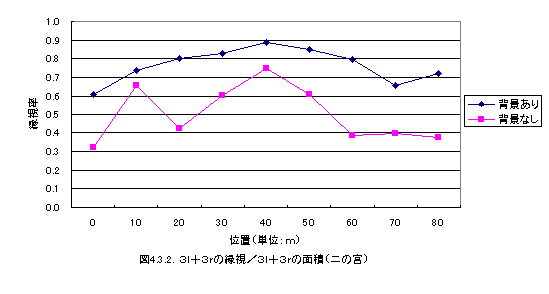
まずは、目線の高さで映っている全ての緑量が、目線の高さの面積に占める割合
(背景ありの緑視率)について分析する。図4.3.2を見ていただきたい。この図より分かることは、不安感を抱かない区間での緑視率が不安感を抱く間に比べて、相対的に低いということである。いっぽうで、不安感を抱く区間の緑視率は、不安感を抱かない区間の緑視率に比べて、相対的に高くなっている。しかし、図4.3.1の全緑視率と比較した場合、不安感を抱く間と、抱かない区間での緑視率の差は小さくなっているため、必ずしも目線レベルの緑視率が、不安感に大きな影響を与えているとはいえない。そのために次の段階として、目線の高さでのペデ外部の緑を除いた緑量が、目線の高さの面積に占める割合
(背景なしの緑視率)が、についての分析をする。再び、図4.3.2を見ていただきたい。20m地点の緑視率が低くなっており、折れ線はいびつな感じとなっている。しかし、一般的には不安感を抱く区間の緑視率は、不安感を抱かない区間の緑視率に比べて、相対的に高くなっている。また、その逆もいえる。背景なしの緑視率は背景ありの緑視率と比べて、特に不安感を抱かない区間での差が大きくなっている。不安感を抱かない区間では、ペデ内部(ペデ近く)の緑視率が低く、その結果ペデ外部の緑が多く見えてしまう。そのため、背景ありの緑視率と背景なしの緑視率の差が大きいと考えられる。いっぽうで、背景なしの緑視率が高い区間は、直前の緑で視線が遮られるため、背景ありの緑視率との差が小さくなっている。 このことより、背景なしの緑と背景ありの緑の差は、可視距離と何らかの関係がありそうだ。また、図4.3.1の全緑視率と比較した場合、不安感を抱く間と、抱かない区間での緑視率の差は大きくなっている。そのため、目線レベルでペデ外部の緑を控除した緑視率が、全力視率に比べ不安感に大きな影響を与えているといるのではないかと推測できる。
4.3.4 その他の緑とゾーン
3の緑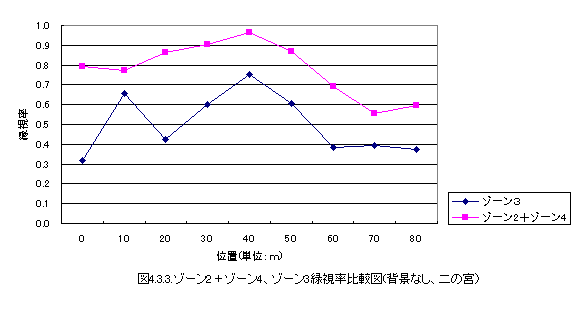
ここでは、背景部しの目線レベルでの緑視率、その他のゾーンで(ゾーン
2+ゾーン4)の背景なしの緑視率と比較する。図4.3.3を見ていただきたい。この図より、目線レベルもその他のゾーンも、一般的には不安感を抱く区間の緑視率は、不安感を抱かない区間の緑視率に比べて、相対的に高くなっている。また、その逆もいえる。目線レベルしの緑視率はその他のゾーンの緑視率と比べて、全体的に低い値になっている。さらに、不安感を抱かない区間(特に0m近辺)での差が大きくなっている。このことより、背景部分なしの目線の高さでの緑視率が、不安感により大きな影響を与えているといるのではないかと推測できる。
4.3.5 道幅について
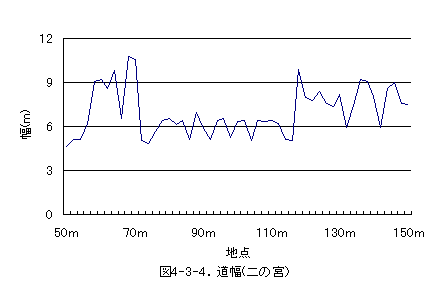
次に、道幅の変化が、不安感に影響を与えているかを検証する。図
4.3.4を見ていただきたい。人は、何mか先の道幅を見ているので、その地点の何mか先の道幅が不安感に関係があると思う。道幅は20m付近で、狭くなっている。不安感は10m付近から感じさせるので、ここでは10m先の道幅が不安感と関係あるといえる。いっぽうで、60m付近で不安感は解消するのですが、道幅は65m付近で広くなっている。ここでは、5m先の道幅が不安感と関係あるといえる。10m付近は、下り坂となっていてより先のほうに視線が向いていることが、より先のほうの道幅が不安感に関係する原因だと思われる。
4.3.6 二の宮地区の分析結果のまとめと改善の提言
二ノ宮地区では、上記の分析結果より、目線レベルでペデ外部の緑を控除した緑視率が、全力視率に比べ不安感に大きな影響を与えているといるのではないかと推測できた。
二の宮地区で不安感を解消するには、上記の結論より目線レベルの緑を減らせば(剪定すれば)いいということができる。しかし、二の宮地区はペデのすぐ近くに住宅がある。今回計測した区間では、幸いにも受託が接近している区間は、不安感を抱かない区間であった。だが、もしも剪定するときには彼らの意見にも耳を傾けるべきだろう。
4.4 緑視率についての分析のまとめ
前記の3地区の分析結果より、全緑視率が不安感と関係があることが分かりました。また、道幅についても、不安感と関係があることが分かりました。そして、目線レベルでのペデ内部の緑が、その他のゾーンの緑に比べ、不安感に大きな影響を与えているのではないかと推測されました。しかし、「今回の実習の結果から、目線レベルでのペデ内部の緑が、その他のゾーンの緑に比べ、不安感に大きな影響を与えている」ということについて、断言するには少し無理があると思うので、ここでは推測できるという表現にとどめておく。しかし、少なくとも目線レベルでのペデ内部の緑が、不安感と関係があることは確かだ。