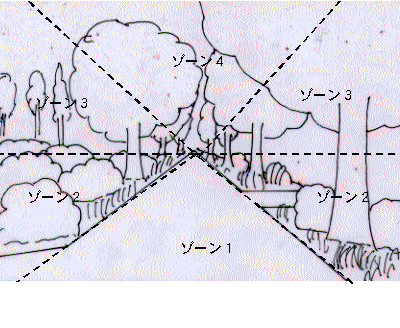 ゾーン1:道幅部分(道路の領域)
ゾーン1:道幅部分(道路の領域) *ペデの緑地景観が通行者に与える不安感の検証*
2-1調査の流れ
2.1.1調査のフローチャート
つくば市の緑視景観の把握
問題点の把握
指標の決定
問題点の検証
アンケートの実施
指標の再検討
緑視・道幅の計測
分析・結論
まとめ
2.1.2 調査の詳細
私たちは緑地環境というテーマのもとに実習を進めていく上で、まず、日頃感じている緑地環境に関する問題点をあげてみた。その結果、たくさんの公園があるのに十分に活用されていない、緑が生い茂りすぎている、ゴミが落ちている等の意見があげられた。そして、つくば市は公園やペデなどの緑地が豊富であるにもかかわらず、整備が行き届かず、快適さという面からみて問題があるように感じた。その問題の原因がどこにあるのかを具体的に考えるために、自分たちの目で実際に見て回ることにした。
見た場所は大学以南のペデストリアンウェイ、公園、周辺開発地区の緑地であり、さらに、三井ビルの最上階からつくば市のほぼ全景をとらえることもした。その感想として、
・高い木が多い
などの意見があげられた。そこで、これらの問題の原因を解明し、そして解決していくために、つくば市における緑地のうちで私たちにとって最も身近で、さらにつくば市の象徴的な存在であるペデを例として取り上げることにした。
その上で、ペデの環境が現状のままでいいのかという問題意識を持って、再度ペデの見学へ行った。そして、ペデの好きな部分・嫌いな部分という指標を基準として良いイメージ・悪いイメージをあげたところ、良いイメージでは、
などがあげられた。また、悪いイメージでは
などがあげられた。これらのイメージのうち、同じ原因からきていると考えられるものでまずグループ分けし、その後、何に起因しているのかを一つ一つ検討していったところ、
という言葉に集約され、これらを問題点とした。さらにこれらを一つの言葉にまとめると、最終的に不安感という言葉に行き着くのではないかと考えた。つまり、これらの問題点を明らかにすることによって、不安感の検証をすることができると考えた。そこで、囲まれ感などこれらの問題点の原因を明らかにするために、どのような指標を用いることが最も効果的かを検討したところ、
・{周辺土地利用、周辺建築物までの距離、可視領域}-周辺環境に関すること
という指標があげられた。
指標があげられた段階で、本当に不安感というテーマで今回の実習が進められるかということをもう一度考えてみることにした。ここまでは我々が実際にペデへ行き、それぞれの感想を話し合う中から、「ペデの不安感の検証」というところまで行き着いたが、今回の調査をより客観的にとらえるために、果たして他の人にも同じようにペデに不安感があると感じているかどうかを調査することにした。
まず、ペデを洞峰公園から大学以南まで自転車に乗ってビデオ撮影をし、そのビデオを我々以外の人に見てもらい不安感を感じるかどうか、また、どこに不安を感じるかを調査しようと考えた。しかし、ビデオの映像では我々が実際に見てきたときに感じた不安感は、全くと言っていいほど感じられなかった。実際に自分の目で見てみることと、映像を介した場合では随分とギャップがあることから、ビデオを用いた調査は断念することにした。
そこで、一般のペデ利用者に対してペデ全般のイメージを調査するアンケートを実施し、そこから本当に不安感を問題として意識しているのかどうかを探ることにした。このアンケートの結果より、実際に緑・道幅・視界の広さが問題視されていることが明らかになった。また、このアンケートと平行して「具体的にペデのどの場所に不安感を抱くか」ということについてもアンケートを実施した。また、このアンケート結果と比較するために事前に我々が不安感を抱く場所も何点かあげておいた。それによってあげられた場所とアンケート結果とを比較したところ、まず、ペデに不安感を感じる場所をエキスポセンターの北側と設定した。それからエキスポセンターの周辺の土地利用を考慮してそのほかに2地区、住宅地区と洞峰公園地区をあげた。(2種類のアンケート結果は第3章に掲載)
そして、ペデ全般のイメージを聴いたアンケート結果と自分たちの経験、さらに文献(日本造園学会編「ランドスケープデザイン」技法道出版株式会社 pp
218)より、『目線の高さの相対的な緑の量と通行者から緑の距離が不安を抱かせる要因となっている』という仮説を立て、実習を進めていくことに決定した。これは、通行者がとらえる緑は主に目線部分の緑であり、この部分の緑が相対的に密であれば通行者は不安感を抱くと考え、また、その緑までの距離が近ければ近いほど不安感を抱きやすいと考えた結果である。なお、今回の調査に関しては、大学キャンパス地区は利用者のほとんどが学生や大学関係者であることから、対象地域から除くことにした。また、期間はこの実習が行われている4月から6月までとした。そして、この調査では緑地自体の管理のあり方に注目して考えるという立場から、調査時刻は晴れた日の昼間としました。
測定場所と仮説が決定したところで、次に、再度計測指標の検討をした。前にあげた指標は、照度・樹高・緑視・樹種・ゴミ・通行量・犯罪・道幅・緑被・周辺土地利用・周辺建築物までの距離・可視領域であったが、これらの指標のうち、実習という限られた時間の中で計測可能であり、また、アンケートの集計結果から緑が与える不安感の原因として説明することができるもので、仮説に基づくものに絞った。その結果、連続シークエンス景観を前提として、①ゾーン緑視 ②道幅 を計測することになった。なぜ連続シークエンス景観として取り上げるかというと、文献(日本土木学会編
(1982)「新体系土木工学59土木景観計画」技報堂出版株式会社pp317、「シークエンス景観と連続シーン景観の評価構造分析」日本建築学会計画論文集 第475号)より、まず大きな前提として、ペデは視点を移動させながら連続したシーンを体験する方向性をもった空間であるといえる。そこで固定的な視点から得られる景観、つまり、写真的な眺めとしてとらえる「シーン景観」よりも、視点の移動を伴う景観である「シークエンス景観」でとらえる方がよいと考えられる。また、シークエンス景観の中でも、景観構成要素の変化によって景観が印象的に移り変わる場面を抽出した「連続シーン景観」を取り上げることによってシークエンス景観はある程度置き換えることが可能であるとされていることから、連続シーン景観を取り上げて連続性についても考慮することにしたのである。そしてこれらの指標を実際に計測し、分析を実行した。
2-2 計測方法
まず連続シーン景観という視点から連続性をとらえるために、3地点において不安を抱く場所と抱かない場所が含まれるようにそれぞれある一定の区間をとり、その区間をさらに10mおきに区切り写真を撮った。これにより連続シーン景観を考慮することができる。カメラの設定についてだが、文献(日本土木学会編
(1982)「新体系土木工学59土木景観計画」技報堂出版株式会社pp317)より、カメラは人が歩く部分ののほぼ中心におき、歩く人の視点が止まる場所に焦点を置いた。そして人の視線は約150cmであるとされていることから、カメラの高さは地上から約150cmに合わせた。さらに、人の視界の広さは左右60度ずつで、上下20度、10度であるとされていることから、28mmの広角レンズのカメラを使用した。また、ゾーン分けの基準をとるために、撮影地点から10m地点と20m地点の道幅に沿って計4本のポールを立てた写真と、ポール無しの写真の2種類を撮影した。次にこの写真を用いてゾーン緑視を計測した。方法はポ-ルありの写真より、
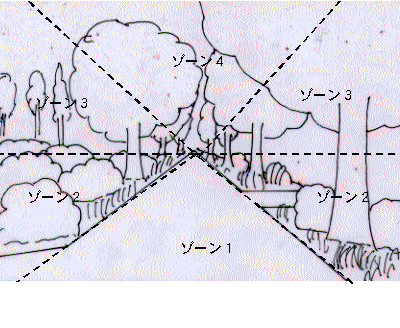 ゾーン1:道幅部分(道路の領域)
ゾーン1:道幅部分(道路の領域)
ゾーン2:道幅以上地上1.0以下(足下の領域)
ゾーン3:地上1.0m以上2.5m以下(目線の領域)
ゾーン4:地上2.5m以上(頭上の領域)
とする。1.0m、2.5mという基準は先ほどのカメラの設定で述べたように人の視界は左右60度ずつ、上下20度、10度であることと、道幅の平均xであることから三角関数を用いて計算したところ、人の視界に大きな影響を及ぼす領域は1.0m以上2.5m以下にはいるのでこのような数値 図
ゾーン分け説明図で分けられた。このようにゾ-ン分けすることによって、ゾーン3を目線の緑視ということができる。
実際の緑視を計測する段階では、まず、ポール無しの写真を写真一枚に約5500個分のプロットがされている点格子板に重ね、ゾーン毎に緑の上にあるドットを数えた。これを背景無しの緑視とし、次に、ゾーン毎の背景にある緑を除いた部分の緑の上にあるドットを数える。これを背景無しの緑視とする。このとき、この点格子版に対して写真はランダムにおく。また、背景の緑とは、基本的には道幅より1m以上ペデの外側に存在する緑のことを指し、視界に大きな影響を及ぼさない緑のことと定義する。つまり背景無しの緑視とは、ペデの内部の緑視ともいえる。なぜ背景ありの緑と背景無しの緑とにわけたかというと、遠くにある緑は一つの風景としてしか映らず、不安感の検証という視点で見たときそれほど大きな影響を及ぼすものではないと考えたからである。
また、それぞれの区間において一枚目の写真撮影地点より2mおきに道幅を測定した。ここでいう道幅は、人が通行している地点から最も近い位置にある木までの距離のことを指す。これは、存在する緑の量が多くて、かつ近くにあれば、同じ緑の量でも遠くにある場合に比べて感じる不安感は大きいのではないか、ということを明らかにするための指標である。これらをふまえた上で分析をした。
2-3 ペデの位置づけ
2.3.1つくば市のペデのマスタープラン
樹林樹木など既存植生の保全と新たな植栽計画を骨子としたオープンスペース系の計画と施設系の計画が一体となって、連続的で有機的かつ多様性を持ったランドスケープを構成する。
2.3.2ペデの位置づけ
・都市軸-新都市の計画における基本理念の表現
・自動車を全く排除した幹線歩行者専用道路を骨格として構成される連続的な都市空間
1.新都市のシンボル空間
都市における人間の復権をスローガンとした、都市の環境形成におけるシンボル、あるいは都市の一体化の
シンボル
2.新都市にわかりやすさを与える空間構成の主軸
-広大な都市の空間構成を人々に認識させ、わかりやすく親しみやすい町を計画する
3.新都市全体のリニヤーセンター
-大学・中心市街地・理工系研究機関のうち代表的な機関を都市軸に沿って配置し各地区内あるいは地区
間の連続性を確保する。
4.新都市のグリーン軸
-新都市は次の3つのグリーンから成り立っている。
a.郊外地区における既存樹林・集落林(面)
b.公園緑地・研究所・大学(面)
c.道路・歩行者専用道路(線)
線的なグリーンで面的なグリーンをつなぎ、環境・景観に調和と統一性をを与える。
2.3.3ペデの構成
・公園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95.3ha 3.0%
・緑地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.8ha 0.1%
・小計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99.1ha 3.7%
・歩行者専用道路・計画街路・・・356.0ha 13.2%
ペデストリアは大きく 研究所・公園地区、中心地区、大学地区 の3地区から構成されている。そしてそれらの地区はさらに次のように細かく分かれている。
①研究所・公園地区
②中心地区(都心部)
③大学キャンパス地区
これらの地区は、それぞれに特徴のある空間構成、施設、植栽構成を持っている。今回調査対象とした区間の構成は、次のようになっている。
①研究所・公園地区
・二の宮公園・洞峰公園・赤塚公園の
3つの公園、理工系研究団地、学校群のそれぞれをつなぎ、さらに都心部と連結。
・幅員
20mで担保される緑の量をはるかに上回る。・緑の深い静かな散策路としての役割。
・豊かな陰影・遊歩道・自転車道(基本要素)
・ベンチ・くず入れ・パーゴラ・道標(デザインされたものが設置)
・サクラ類を中心とした花木
・モミジなどの紅葉木
・四季折々の雰囲気が楽しめる様計画
・洞峰公園~南大通り線
民間住宅地の住民の都心部へ日常生活としての歩行軸。
都心部から二の宮公園・洞峰公園へのレクリェーション的要求に対応する動線軸。
移動行為としてのポテンシャルが高いことから幅員
10mで歩行者・自転車レーンを分離(サクラ・マツ中心として並木的配置)。
可能な限り両側の緑地帯を確保。
歩専道の両側に公園・研究施設などの緑量が期待される場合、両側を薄くし中央に植栽帯を設ける。
サクラ、ケヤキ・エゴノキ(落葉広葉樹林)
法面は芝張り・灌木植栽
・洞峰公園~赤塚公園
中心地区の“都市らしさ”と対比して“自然らしさ”を強調。
歩行者レーン(稲田石の切石舗装)と自転車レーン(アスファルト舗装)とに分離。
サイクリングを楽しむために曲線と直線を効果的に組み合わせ、縦断勾配にも変化をもたせた構成。
アカマツ林、サクラ類・アメリカハナミズキ・コブシ(花木)クロマツ・スギ(常緑樹)を紅葉樹が際だつように
背景に配植。
②中心地区
・竹園公園を中心として、自然的要素を盛り込んだデザインにより公園・広場・歩専道が一体となった空間構
成。
・南大通り線から1号広場までは中心地区までのゲートとして、直線的な桜並木。
・1号広場は国際色豊かな場を想定した日本的な雰囲気の疎林広場。(石の広場)
・竹園公園に接する歩専道には公園のデザインをにじみ出させた広場的空間。この雰囲気を連続させて隣
のブロックまで延長。
・学園センタービルを多様なコミュニティーづくりと文化の創造の拠点として位置づけ、歩専道及び中央広場
を複合的に設計することにより都市核を形成する象徴的空間として、格調高い空間構成と演出を目指す。
・地上と歩専道の2層の交通ネットワークを持つ都市において、広場のデザインを成立させるための視覚的な
骨格を形成。