小学校の自由選択制について
第3章 結論
次へ
目次へ
3-1 学区外通学容認モデル
まず,一つ目として学校外通学容認モデルを提案する.このモデルはより完全自由化に近いモデルとして考案した.各学校には限界収容人数(下図の€)というものがあり,その収容人数から現在その学校に通っている児童数( )を差し引いたものを,学区外からの通学を希望する児童の許容人数(¡)とする.他の学校への通学を希望する人数が¡以内なら,希望者は全員その学校へ移ることができる.
また希望人数が¡をオーバーした場合は,理由によって優先順位を決めそれに基づいて選ぶ.優先順位は以下のとおりである.
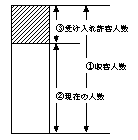
- Aランク
- 現在の指定された学校より近い学校がある
- 保護者が転勤したが子供は現在の学校に通わせたい
- いじめの問題があり現在の学区の学校には通いたくない
- Bランク
- Cランク
もし同ランク内で希望がオーバーしてしまった場合は,抽選などの方法で決定する.この抽選にもれたとしても,現在通っている学校には の分の収容量は確保されているので,少なくとも学区で指定されている現在の学校には通うことができる.つまり望んでもいない遠距離通学をする可能性はないということである.また,このモデルのメリット,デメリットとして次のようなものが挙げられる.
- メリット
- 許容量を超えない限り各家庭行きたい学校に行ける
- 学校同士が刺激剤となり,独自の校風が生まれ教師の質の向上にもつながる
- 学校に対する関心が高まる
- 例外的な遠距離通学希望者にも対応可
- いじめ回避につながる
- デメリット
- 教育委員会及び学校側の手間が非常にかかる
- 学校側に人気の差がでてくる
- 抽選で決定してしまう場合もある
3-2 特例地区設定モデル
このモデルは「指定学校変更地域が認められている地域を設ける」というもので,実際つくば市でも14の地域で実施されており,今回取り上げた7学区の中では「梅園2丁目」がそれに該当する.「指定学校変更地域」とは,「学校までの距離」や「通学上の安全面」などを考慮し学区で決められた学校とは別のところに通うことを認められた地域のことである.梅園2丁目の場合,本来「並木小学校」の学区であるが,「東小学校」に通うことが認められている.特例地区設定モデルとは,このような地域を他に設けていくというものである.
シミュレーションマップと現状の学区との違いを表した地図を作成した。色がついている部分は学区外の小学校への通学を希望する人たちの分布を表している。これをもとに具体的な特例地区を町丁目ごとに設定した.それぞれの地域について説明すると次の表1のようになる.
表3 特例地区が認められている地域
| 特例地域名 | 本来の学区 | 選択可能校名 |
|---|
| 小野崎 | 手代木南小 | 松代小,二の宮小 |
| 西大沼 | 手代木南小 | 二の宮小 |
| 千現2丁目 | 竹園西小 | 二の宮小 |
| 倉掛 | 竹園東小 | 並木小 |
| 二の宮1丁目 | 二の宮小 | 竹園西小 |
実際二の宮1丁目については,教育委員会でのヒアリングの際に,竹園西小への入学希望が多いので将来的には指定学校変更可能地区になる可能性がある,と言う話もお聞きした.この特例地区モデルでは,学区が現在よりも広がるので許容量の問題を考慮する必要がある.そこでシミュレーションマップのところで用いた学区内町丁目ごとの児童数を調べた表2を参考にすると,特例地域の児童全員が1校に集中したと仮定しても,現状においては許容量の問題は生じないということがわかる.また将来的には,児童数増加率から予測して,少なくとも2〜3年は許容量の問題は起こらないということがわかる.
表4 各学校の許容量
| 小学校 | プログラム人数 | MAX | 差 |
|---|
| 松代小学校 | 456 | 800 | +344 |
| 手代木南小学校 | 446 | 800 | +354 |
| 二の宮小学校 | 654 | 960 | +306 |
| 竹園西小学校 | 537 | 640 | +103 |
| 東小学校 | 601 | 800 | +199 |
| 竹園東小学校 | 530 | 800 | +270 |
| 並木小学校 | 401 | 1000 | +599 |
- メリット
- 一番近い学校及び通学上安全な学校を選べる
- 現状では学校のキャパシティーの問題はほぼ起こり得ない
- デメリット
- 特例地区に入らなかった住民の希望に対応できない
- 将来の特例地区の設定は難しい
以上のようにどちらのモデルにおいてもメリット・デメリットがあり,どちらが良いとは言いきれないが,どちらのモデルも少なくとも現状よりは保護者の要望に沿ったモデルだと言える.
次へ
目次へ