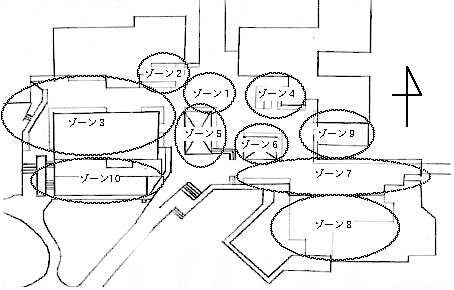
図4.3.1 実験のゾーニング
1:駐輪禁止場所にポールを置き、駐輪禁止ゾーンの周囲を黄色テープで囲い、さら
に駐輪禁止の立て看板を設置し、駐輪禁止ゾーンであることを明示して、駐輪し
にくくする。駐輪場ゾーンと通路の境界にポールとバリケードを設置し、黄色
テープを貼り、駐輪場 ゾーンと通路の区分をはっきりさせる。進行方向を示す
矢印を白テープで引くことなどにより、通路と駐輪場の区分を明示し、さらに自
転車の逆流走行を減少させる。
2:新しい駐輪場の場所を書いた立て看板を駐輪禁止ゾーンに設置し、新駐輪場入口
はここであるということを書いた立て看板を新駐輪場入口に設置し、新しい駐輪
場の場所を明示する。
3:通行の邪魔にならないところに、白テープで周囲を囲った駐輪場を新設し、迷惑
駐輪を減少させる。
以上の3点を行った。実験設置物が学生等に動かされると、実験の効果が薄れる
ので、実験設置物の調整を実験期間中、毎日1日3回行った。そして、実験前と実
験中においてどのような変化が見られるかを、駐輪場内外に分けての駐輪台数の測
定と、自転車通行状況や駐輪状況などの観察や、状況をデジタルカメラで撮影する
ことにより、比較してみた。さらに実験期間の5日間が終了後、実験で設置した物
を撤去してどのような変化が見られるかを調べるため、実験中の調査と同じ内容の
調査を1日分行った。
▼注意事項
駐輪違反をしないように学生に注意したりせずに、純粋に実験だけの効果を測定 した。
▼実験場所
第一学群棟周辺。駐輪台数のカウントは第一学群棟周辺を10個のゾーンに分け
て行った。ゾーンに分けた理由は、一学周辺全体で駐輪場内外の駐輪台数をカウン
トするより、特徴あるゾーンごとにカウントした方が、駐輪状況を的確にとらえる
ことができると判断したためである。
それでは、各ゾーンの紹介をする。詳しくは地図を参照のこと。
ゾーン1:一学D棟と一学B・C棟の間の駐輪場ではないスペース。バリケードが三角形状に置かれている部分。南北の進行方向別の通行が合流するところ。
ゾーン2:一学D棟北側部分の南東にある駐輪場スペース
ゾーン3:一学D棟の間とD棟東側と西側。
ゾーン4:一学B・C棟付近
ゾーン5:一学D棟東向いの吹抜けの周り。
ゾーン6:一学B・C棟南向いの吹抜けの周り。
ゾーン7:一学A棟北側
ゾーン8:一学A棟2階部分
ゾーン9:一学B・C棟南の新駐輪場(98年新設)
ゾーン10:一学D棟南の新駐輪場(98年新設)
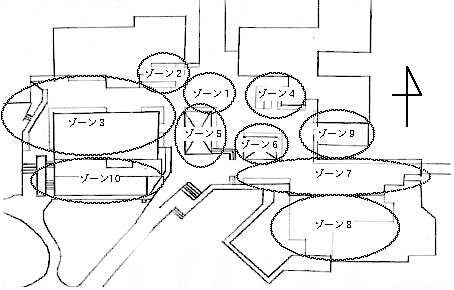
▼実験の日時
実験期間:1998年 6/8(月)〜6/12(金)
駐輪台数カウントと状況の観察、デジカメ撮影:6/8(月)、6/10(水)、6/12(金)
事後調査:6/15(月)
実験中調査、事後調査ともに調査時間は以下のとおり。
駐輪台数カウント:10:20、11:50、14:45
自転車通行状況などの観察やデジタルカメラで撮影:9:55~10:10、11:25~12:15、15:00~15:15
どうしてこのような調査曜日・時間にしたかは、予備調査や資料などでこの曜日・
時間の駐輪台数が比較的多く、混雑の程度もひどいと判断し、この曜日・時間なら
実験による状況の改善の度合いが大きいことが予想されたためである。事後調査に
関しては、実験終了後最初の平日であるため、6/15に調査した。事後調査をあ
と数日続けることも考えたが、一日だけでも変化が見られたことと、最終発表が迫
っていて日程的に余裕がなかったために、事後調査は6/15の1日のみとした。
実験設置物の調整:6/8(月)〜6/12(金)の実験期間中毎日8:15、11:20~11:35、13:20~13:45の1日3回
まず、第1学群周辺の駐輪容量がどれほどあるかを見ていきたい。各ゾーンごとの駐輪容 量と、各ゾーンの駐輪場内に駐輪している最大の時点の自転車台数をピックアップしてきた のを、図4.3.2に示す。各ゾーンの駐輪容量は『駐輪場実体調査』(1993)による。
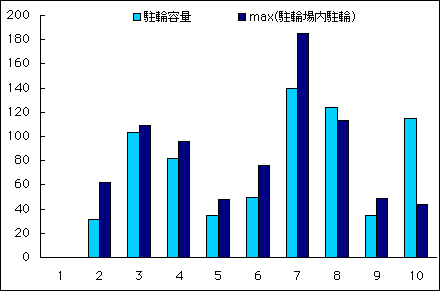
これにより、各ゾーンの駐輪容量より多い台数の駐輪もあるのが分かる。これは、駐輪
容量が「2m×0.5m」と定義されている理論上の数値だからである。よって、実際には
もっとたくさんの駐輪が可能であるといえる。
『駐輪場実態調査』(1993)によると、既存の駐輪場は565台、今年度からの新しい駐輪場
は150台で、第1学群周辺には理論上715台の駐輪容量がある。さらに今回の実験により駐輪
容量16台分を増設したので、実験中は理論上計731台になる。図4.3.3に実験前・中の全
駐輪台数を示す。これにより、駐輪台数が実験前の715台、実験中の731台を超えたのがそれ
ぞれ2回あるのが分かる。よって、理論上の数値を超えたのが2回しかないこと、実際には
理論上の数値を超える駐輪容量がありること、の2点より、第1学群周辺には、十分な駐輪
容量があるといえ、今回の実験には無理がない。
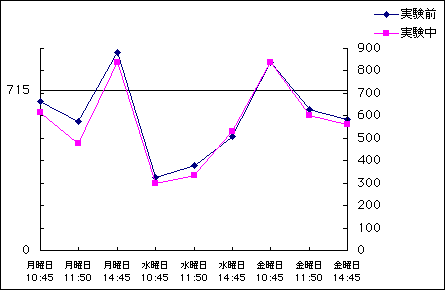
▼実験前・中の駐輪状況
実験前の駐輪台数を表4.3.4に示す。なお、項目の「内」は、駐輪場内の駐輪台数、 「外」は、駐輪場外の駐輪台数を表している。これにより、月曜日(6月1日)の14:45、 金曜日(6月5日)の10:20、11:50が駐輪台数が多いのが分かる。
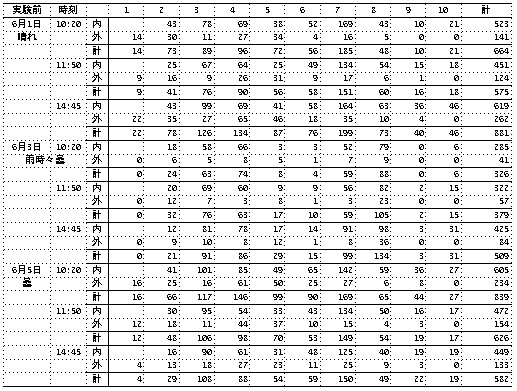
実験中の駐輪台数を表4.3.5に示す。なお、項目の「内」は、駐輪場内の駐輪台数、 「外」は、駐輪場外の駐輪台数を表している。これにより、月曜日(6月8日)の14:45、 金曜日(6月10日)の10:20、11:50が駐輪台数が多いのが分かる。また、実験前・中の各 時点ごとの全駐輪台数はあまり変わっていない。
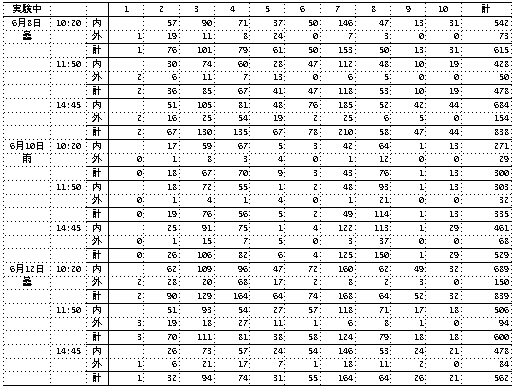
次に、実験前・中の駐輪場外における迷惑駐輪の変化をみる。
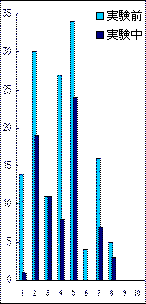
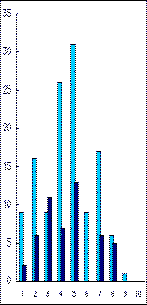
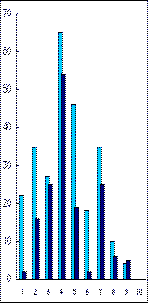
図4.3.6より、実験前に比べて、実験中のほとんどの時点において、迷惑駐輪が減っ ているのが分かる。 次に、実験前と実験中の写真を見比べてもらいたい。図4.3.7、図4.3.8より、 迷惑駐輪が減ったことにより、通行路がきちんと確保され、混雑の解消となっていること、 が分かる。




▼新しい駐輪場の状況


写真(図4.3.9)を見て分かるとおり、新しい駐輪場はまったく使用されていない。
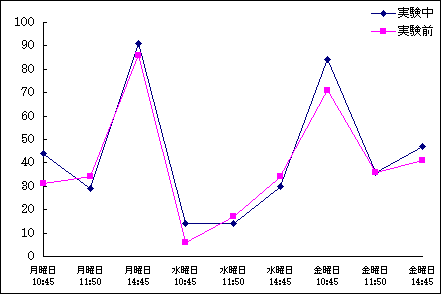
図4.3.10より、新しい駐輪場の駐輪台数は実験前・中によって、まったく変化が起こっ てないといえる。これは、写真(図4.3.11)を見て分かるように、新しい駐輪場の入口 の構造が入りにくくなっているからであり、建築構造上の問題である。よって、今回の実験 では改善できなかった。


▼実験後の状況
次に、実験後の状況をみてみる。


実験後、最初の登校日である月曜日の午前中には、写真(図4.3.12)のように、ペデ ストリアンは混雑していた。よって、誘導による実験は、誘導している間にだけ効果がある といえる。
