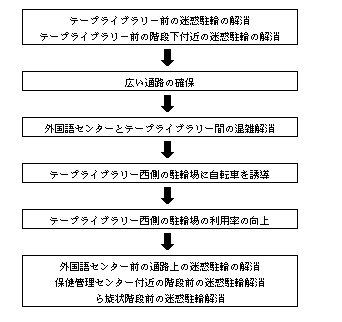
・外国語センター前の通路上の迷惑駐輪
・保健管理センター付近の階段前の迷惑駐輪
・テープライブラリ−前の迷惑駐輪
・テープライブラリ−前の階段下付近の迷惑駐輪
・ら旋状階段前の迷惑駐輪
・テープライブラリー西側の駐輪場の利用率の低さ
・外国語センターとテープライブラリー間の混雑
・路面の滑りやすさ
以上8個の問題がでてきたが、最後の「路面の滑りやすさ」という問題については、構造
上の問題であり、路面の質を変えていかなければならないので、今回の問題からは省くこと
とした。
次に2次的問題について。外国語センター前の通路上の迷惑駐輪、保健管理センター付近
の階段前の迷惑駐輪、ら旋状階段前の迷惑駐輪などの各種迷惑駐輪によって、特に休み時間
などには混雑が発生していた。またテープライブラリー西側の駐輪場の利用率の低さや外国
語センターとテープライブラリー間の混雑はテープライブラリ−前の迷惑駐輪やテープライ
ブラリ−前の階段下付近の迷惑駐輪が原因であると考えられる。
我々が今回の実験や調査を行う目的は先ほど挙げた8個の問題やそれによって発生する2
次的問題の解決策を考案していくことである。
まず実験、調査の方法として、テープライブラリ−前の迷惑駐輪やテープライブラリ−前
の階段下付近の迷惑駐輪をなくし、広い通路を確保して、テープライブラリー西側の駐輪場
に自転車を誘導する。これはテープライブラリー西側の駐輪場の利用率の低さはそこへ行く
ための通路が確保されていないためであると考えたからである。これにより、外国語センター
前の通路上の迷惑駐輪、保健管理センター付近の階段前の迷惑駐輪、ら旋状階段前の迷惑駐
輪、外国語センターとテープライブラリー間の混雑も同時に解決できるのではないか、と考
えた。
考えをまとめると次のようになる。
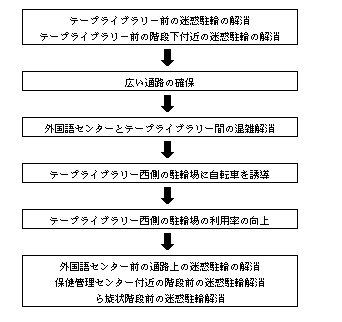
▼実験場所
外国語センター周辺
▼実験の日時と時間
・実験前
6/1(月):4−5限間
6/3(水):1−2限間
6/4(木):1−2限間
6/4(木):4−5限間
6/5(金):3−4限間
・実験中
6/8(月):4−5限間
6/10(水):1−2限間
6/11(木):1−2限間
6/11(木):4−5限間
6/12(金):3−4限間
・実験後
6/15(月):4−5限間
6/18(木):1−2限間
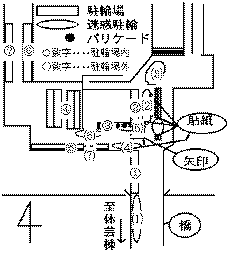
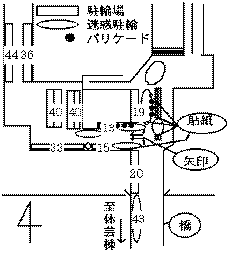
実験前の駐輪台数は表4.2.2のとおりである。実験前においては,駐輪場内における 駐輪が平均55.11%,最低で46.42%,最高で69.95%となっている。また,駐輪上外における 駐輪は平均44.89%,最低で30.05%,最高で53.58%となっている。日時によって差は大きい ことがわかる。また,半分以上の自転車が駐輪場外にとめている時間帯もあることがわかる。 また,特に通行と妨げる要因となっていると思われる駐輪場外2の部分の駐輪が平均27.8台, 最低14台,最高37台となっている。また,外国語センター奥の駐輪場内4は80台分の駐輪ス ペースを確保しているのにもかかわらず,平均11.6台,最低9台,最高14台となっている。実 験前はこのような状況である
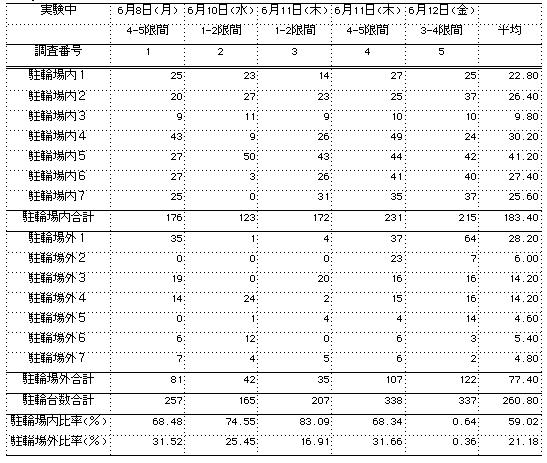
実験中の駐輪台数は表4.2.3のとおりである。実験中においては,駐輪場内における 駐輪が平均72.65%,最低68.34%,最高83.09%となっている。また,駐輪上外における駐輪 は平均27.35%,最低で16.91%,最高で31.66%となっている。また,特に通行と妨げる要因 となっていると思われる駐輪場外2の部分の駐輪が平均7.0台,最低0台,最高23台となって いる。また,外国語センター奥の駐輪場内4は平均33.8台,最低9台,最高49台となっている。 実験中はこのような状況である。
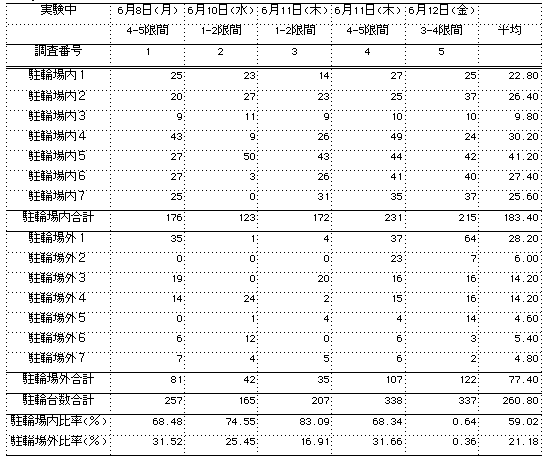
実験後の駐輪台数は表4.2.4のとおりである。実験後においては,駐輪場内における 駐輪が63.75%,51.52%となっている。また,駐輪上外における駐輪は平均27.35%,最低で 36.25%,最高で48.48%となっている。また,特に通行と妨げる要因となっていると思われ る駐輪場外2の部分の駐輪が13台,30台となっている。また,外国語センター奥の駐輪場内 4は23台,最高20台となっている。実験後はこのような状況である。
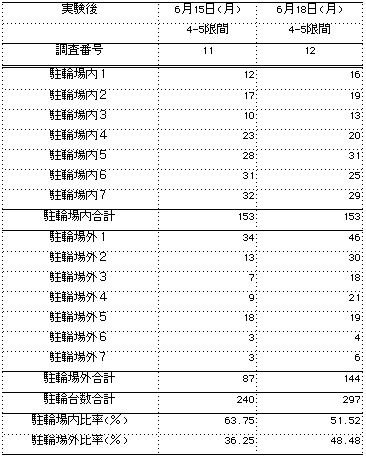
▼実験による変化
・駐輪場内への駐輪の比率の変化
駐輪場内への駐輪比率について考察する。実験前・実験中・実験後にかけて,駐 輪場内および駐輪場外駐輪の比率をグラフにしたものが図4.2.5である。この 図からわかるように,実験中は実験前・実験後くらべて駐輪場内に駐輪する台数の 割合が多くなっていることがわかる。このことにより,実験を行ったことにより, 駐輪場への駐輪を促すことができたのではないかといえる。
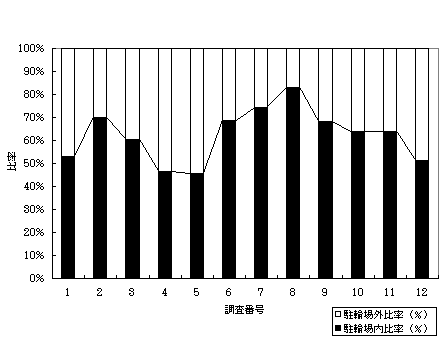
・奥の駐輪場(駐輪場内4)の利用状況の変化について
奥の駐輪場(駐輪場内4)の利用状況の変化について考察する。実験前・実験中・ 実験後にかけて,駐輪台数をグラフにしたものが図4.2.6である。実験中は実 験前・実験後に比べて利用台数が増加していることがわかる。また調査番号7の日 は雨天だったため,屋外にある駐輪場内4は使われていなかった。
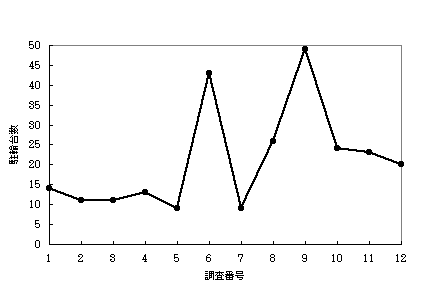
・通行の妨げになる部分(駐輪場外2)の状況の変化について
通行の妨げになる部分(駐輪場外2)の状況の変化について考察する。実験前・ 実験中・実験後にかけて,駐輪台数をグラフにしたものが図4.2.7である。実 験中は実験前・実験後に比べて駐輪台数が減少していることがわかる。しかし,調 査番号9の回が多くなっているがこれは理由付けが難しい。
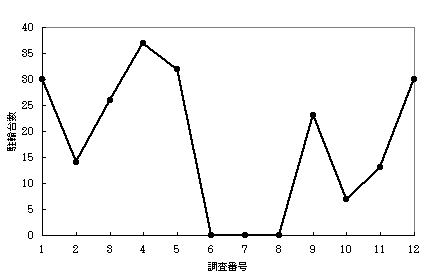
▼写真による変化の状況の考察




▼実験結果・分析 総括
実験前においては駐輪場外への駐輪が50%を越えていることもあり,通行をさまたげる部 分への駐輪も非常に多くみられた。また,利用されていない駐輪場もあった。実験中におい ては,掲示のみでの誘導であったが,駐輪場外への駐輪割合が減少し,通行をさまたげる部 分への駐輪も減少した。また,利用されていなかった駐輪場への誘導をすることができた。 実験後においては,実験前の状況と大きく変わらず,元に戻ってしまったと考えられる。よっ て,掲示による誘導は継続的に行わなければならないだろう。また,駐輪場内への駐輪の比 率は実験前にくらべ実験中は増加している。このことから,掲示による誘導であっても,効 果はみられると言える。写真によっても,この状況ははっきりと現れている。この実験から, 掲示による誘導,駐輪場部分と駐輪禁止部分のはっきりとした区分けにより,奥の利用され ていなかった駐輪場(駐輪場内¤)への誘導,通行をさまたげる部分(駐輪場外É)の駐輪 をなくすことができることがわかった。