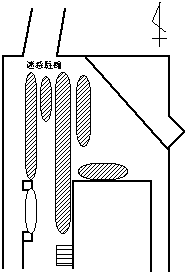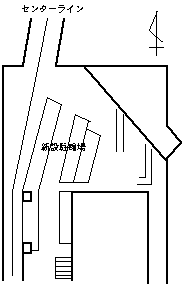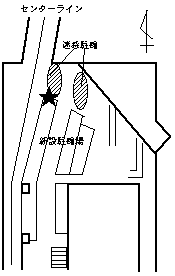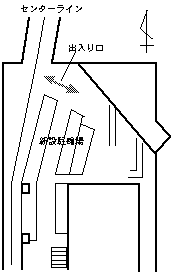筑波大学ペデストリアンにおける自転車交通
第4章 実験(大学会館)
次へ
目次へ
4-1-1 実験目的
大学会館では無秩序な駐輪によって、橋の手前など通路が狭くなってしまっている所があ
り、そこでの混雑が最も多くみうけられた。無秩序な駐輪をしてしまう理由として、キャッ
シュコーナー前には駐輪場のラインがなく、スペースが有効に使われていないという事が考
えられる。
そこで、我々は上述した問題点を改善するために、自転車の通路の確保をしてペデストリ
アンデッキの流れを止めないようにすること、駐輪スペースを明らかにすることによって効
率的なスペースの利用をさせる、の2点について実際に可能かどうか実験してみることにし
た。


図4.1.1 無秩序な駐輪
4-1-2 実験内容
まずペデストリアンデッキの通行を最優先とし、白線で通路と駐輪スペースを分離した。
そしてセンターラインと進行方向を示す矢印を描き左側通行を徹底してもらうと共に、通路
である事を意識させるようにした。
また、駐輪スペースが今までなかったので、白線で新しく指定した。その際、事前調査を
した時に得たデータとキャッシュ前のスペースを考え駐輪容量は79台とした。さらに、駐
輪スペース内では、歩行者のための通路へはみ出して自転車を止める人が多いということで
カラーコーンとポールを設置し、通路への駐輪禁止をうながす貼紙を貼る事と、「通路」と
いう文字を地面に描くことによって通路上への駐輪禁止をアピールすることにした。
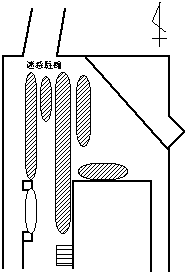
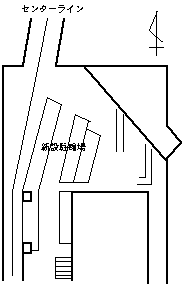
図4.1.2 実験前の駐輪状況(左)、誘導図(右)


図4.1.3 実験誘導の状況
4-1-3 実験の結果
調査は実験期間中の月曜、水曜、金曜日の各休み時間に行い、その結果は次のようになっ
た。まず、橋の手前で通路をふさいでいた自転車が完全になくなり、いままで無秩序な駐輪
によってひどいときには2mほどしかなかったペデの幅員が、橋と同じ幅、5mを必ず維持
できるようになり、幅員の減少による混雑がみられることは完全になくなった。そして、実
験中とその前とはほとんど駐輪台数に変わりがないのに、駐輪スペースの明示により整然と
駐輪されるようになったのでスペースの有効利用ができ、余裕を持って駐輪できるようにな
った。このことは、駐輪場を利用していた何人かの人へのインタビューでも分かった。


図4.1.4 実験前の状況


図4.1.5 実験中の状況


図4.1.6 北側からの視点:実験前(右)と実験中(左)
4-1-4 実験中の新たな問題
今回の実験ではペデストリアンデッキの通路の確保が一番の目的だったが、実験を始める
と新たな問題が発生した。それはペデストリアンデッキと駐輪場との出入口に駐輪する人が
絶えず、出入口をかなり狭くしてしまっているということである。一人が止めると皆がそこ
に止めてしまい、それによって奥の駐輪場へ行けなくなった人が手前の駐輪スペースではな
いところに止めてしまうという状況が生じてしまったのである。
この場所は出入口であるので広めに、4mほどとっていたのだが、その広さからか「一台
ぐらいいいだろう」という意識で止める人が多いようである。この点については、駐輪禁止
のアピールをもっとすると共に個人の意識を変えていかなければならないと感じた。
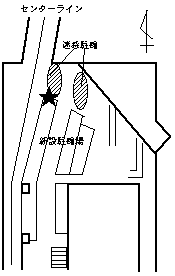
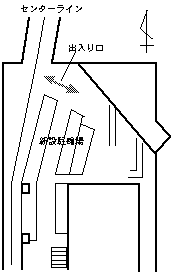
図4.1.7 理想の状態(右)と実験中の迷惑駐輪の状態(左)
4-1-5 実験中にしたことと実験後の状況
我々は金曜日に前述した迷惑駐輪の状況をを改善するために、奥の通路を確保していたコー
ンとポールを、自転車が最もひどく駐輪スペースの外にはみ出している所( 図4.1.7
の★) に移動させてみた。すると、コーンとポールを移動したところでは多少の改善がみら
れたが、それでもやはりはみ出して止める人はいて、完全な解消にはならなかった。
また、実験後(誘導を全て撤去した後)の月曜日に事後調査を行ったが、実験前の乱雑な
駐輪状況となんら変わりがなかった。


図4.1.8 実験後の状況
4-1-6 大学会館の実験結果の考察
大学会館の実験を通して分かったことは、誘導が全くない所に対するなんらかの誘導は非
常に効果があるということである。区切りのテープを貼るだけで目に見える効果がみられた
という結果が表われたことは、非常に重要である。利用者もキャッシュコーナー付近の混雑
はどうにかならないのかと感じていたと思われ、大学側が多少なりとも誘導をすれば解決で
きることであると思った。
次へ
目次へ