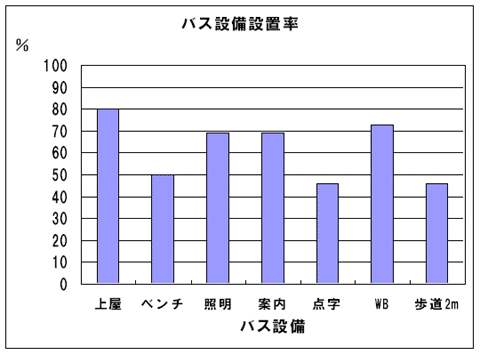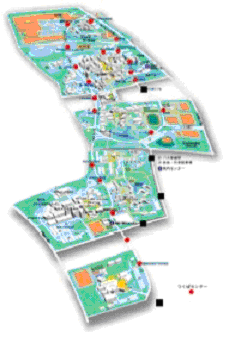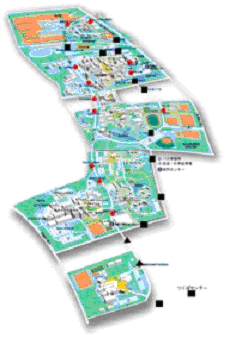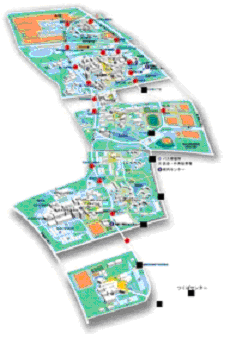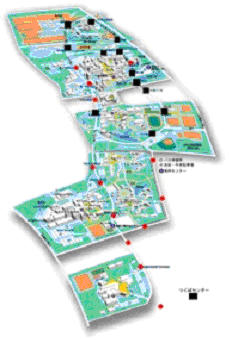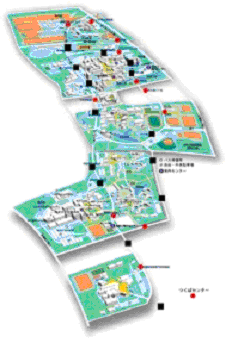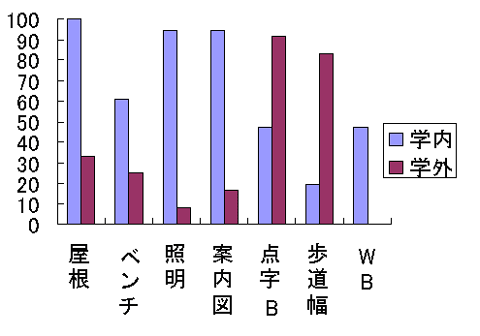第2章 調査2-1 設備・利用者の把握2-1-1 現地観察■観察概要■新学内交通システムが導入され、 バスの時刻や路線は新しく変更されたがバス停はそのまま流用されていた。 そこで、筑波大学循環バスのバス停には設備の不足や、 老朽化、破損など様々な問題があるのではないかと考えた。 まず、バス停の現状を把握するために、実際に全26箇所のバス停へ行き観察を行った。 観察項目は「バス米の形」「上屋」「ベンチ」「照明」「案内図」「点字ブロック」 「ウェルカムボード」の有無と「歩道の幅」「歩道の高さ」の計9つである。
写真2-1 バス停現地観察項目
■観察結果■筑波大学循環バスの全26箇所のバス停の設備の設置状況を実地観察した結果、 「上屋」=80%、「ベンチ」=50%、「照明」=69%、「案内」=69%、 「点字ブロック」=46%、「ウェルカムボード」=73%、「歩道の幅が2メートル以上」=46%であった。
図2-1 バス停全26箇所の設備設置率
*WB=ウェルカムボード
この結果から、筑波大学循環バスのバス停には設備が不足しているのではないかと考えた。 「ベンチ」の設置率が50%と「上屋」の設置率80%に比べて低くなっているので、 バス利用者がバス待ち時間座れないという問題が発生している可能性がある。 また、「点字ブロック」「幅員2m以上」の設置率が低いので、 目の不自由な人や、車椅子の人などがバス停を利用できない可能性もある。 そこで、各設備がどのバス停に不足しているかを調査した。 例えば、大学病院前のバス停は病院利用者が多く利用していると考えられるので、 点字ブロックやバリアフリーの歩道の設置が重要になると考えられる。 このように、バス停ごとに必要な設備は異なっていると考えられる。 そこで、理想として「バス停ごとの利用者層を調査し、 その利用者層に合わせたバス停設備を設置する」ことを目標とした。 以下、それぞれの設備の設置の有無をバス停ごとに示した。
各バス停設備設置状況
■考察■各設備の設置の有無をバス停ごとに示した結果、 設備の設置が学内と学外とで大きな差があることがわかった。 学内のバス停は学外のバス停に比べ、設備の設置率が高くなっている。 「上屋」がないバス停は、吾妻小学校・メディカルセンター病院・ 追越宿舎東・天久保二丁目・天久保三丁目と全て学外のバス停である。 つまり、学内のバス停は上屋設置率100%だと言える。 「照明」「案内図」も同様のことが言える。学内での設置率が極めて高い。 一方で、「点字ブロック」・「歩道幅2m」の設置状況は全体的に低いといえる。 特に、学内の北側、一の矢宿舎付近では整備がほとんどなされていないことがわかる。 また、天久保二丁目・追越宿舎東では点字ブロック以外の設備がまったく設置されていないことがわかった。 学生が多数利用すると見られるバス停で設備設置率が低い現状では、何かしらの問題があると考えられる。 以上の結果を踏まえ、学内と学外のバス停を区別して考えることとする。 まず、図1で示した筑波大学循環バス全26箇所の設備設置率を学内/学外に分けたグラフを示す(図2-8)。
図2-8 学内・学外ごとの設備設置率
図2-8から、学内のバス停はバス停設備の設置率が高いことがわかる。 「上屋」「照明」「案内図」に関してはほとんどのバス停に設置されているので、 問題はないといえる。 しかし、学外のバス停では反対に設置率が低く、問題があるかもしれない。 バス停の設備の設置率だけを考えると、 学内のバス停よりも学外のバス停に問題が多いと考えられる。 ただし、バス停の利用状況を考えると少し問題が変化する。 利用者の少ないバス停に設備を充実させるのは経済的に効率的ではないだろう。 利用者の数に応じて、必要な設備も変化していくと考えられる。 つまり、学内のバス停のほうが学外のバス停よりも利用者が多ければ、 設備設置率に差があって当然と言えるだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る || 目次 || 次へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2008 インフラ班, All rights reserved. |