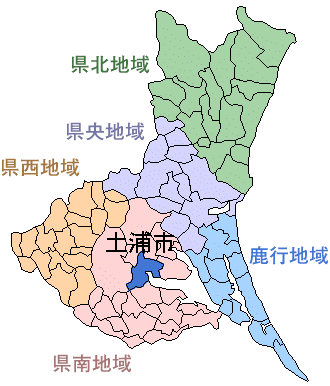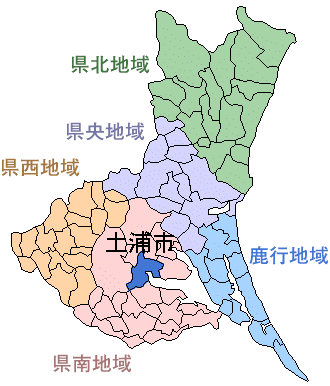序論
1.計画策定の趣旨
土浦市の霞ヶ浦湖岸周辺を中心とする豊かな自然環境と,古くからの歴史ある文化・伝統を活かし,生涯に渡る住み良い暮らしの提供を目標に,土浦市の現在の置かれている状況と,求められている役割を理解し,人の集まるまちづくりを進めるためにこの計画を策定する.
2.計画の役割
この計画は,土浦市の将来目標とそれを達成するための市政の基本的な方向を示し,計画的に市政を運営していくための指針とするものである.この計画から,市民・団体に対する理解・協力を求め,市民一体となったまちづくりへの積極的な参加を期待し,新たな土浦市の発展をはかる.
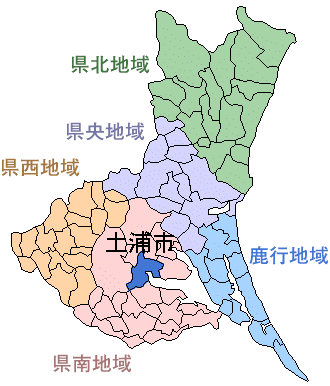
3.土浦市の現況と課題
1)土浦市の歴史
土浦は,豊かな自然環境と長い歴史・文化の中で発展してきたまちであり,土浦の歴史を理解することは,これから新たな発展を望むためにも欠くことのできないものである.
土浦は,江戸時代の水戸街道の開通から本格的なまちづくりが進み,城下町としての基盤が形成される.この頃は,霞ヶ浦・利根川の水運の発達による交通の要衝地,常総地方の商業の中心地として栄えていた.明治期に入ると土浦城周辺の整備が進み,政治・経済・文化の中心として発展した.大正期になり,鉄道・自動車等の陸上交通の発達や,それにともなう水運の衰退などから,土浦の都市構造は大きく変化していった.昭和36年の常磐線の電化や,38年の首都圏都市開発区域の指定により急速に近代化が進み,県南地域における中核都市としての地位を確立し,宅地開発の進んだ昭和49年には人口が10万人をこえる都市となった.
昭和60年に,筑波研究学園都市において国際科学技術博覧会が開催され,これを契機に都市基盤の整備が進み,それとともに,第四次首都圏基本計画において,土浦・筑波研究学園都市地域は業務核都市として位置付けられ,筑波研究学園都市と一体となった発展が期待された.
平成5年,「土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想」が国の承認を受け,県南の業務の中心地となることが期待されている.平成7年には,中心市街地活性化の中核を担う土浦駅前地区市街地再開発事業に着手した.
2)土浦市の基盤
土浦市は東京から60km圏に位置し,筑波研究学園都市に隣接し,新東京国際空港や鹿島港にも近接するなど,地理的な優位性を持つ.自然環境については,霞ヶ浦,宍塚大池,鶴沼,乙戸沼などの湖沼や,桜川,備前川,花室川,新川などの河川や,筑波山などに囲まれ,市の花である桜,丘陵地の平地林など,水と緑に恵まれた自然環境の豊かな地域である.交通条件は,常磐線が市内を縦断しており,土浦駅,神立駅,荒川沖駅の3駅がある.常磐線,常磐自動車道,国道6号,国道125号などにより,東京をはじめとする周辺の主要都市と連結されている.また,国道6号牛久・土浦バイパス,国道125号南バイパスや国道354号など広域幹線道路の整備,常磐新線の建設,首都圏中央連絡自動車道の建設は,県南地域における広域基幹交通網として重要な基盤となるものである.市内では,木田余地区や田村沖宿地区の土地区画整理事業,テクのパーク土浦北,都市計画道路の整備,土浦駅東口駐車場などの生活の基盤が整ってきている.また,土浦駅前地区市街地再開発事業の完成といった,市街地部における都心機能充実をはかった動きなど,新しい都市基盤が整備されつつある.
3)まちづくりの課題
現在,都市のあるべき姿が,従来のそれと大きく異なってきており,情報化,国際化,高齢化などの目紛しく変化する社会環境への的確な対応が望まれている.土浦市のまちづくりを進める際にも生活環境,自然環境に配慮し,市民の求めるまちづくりを推進していかなければならない.
基本構想へ→