部門別構想
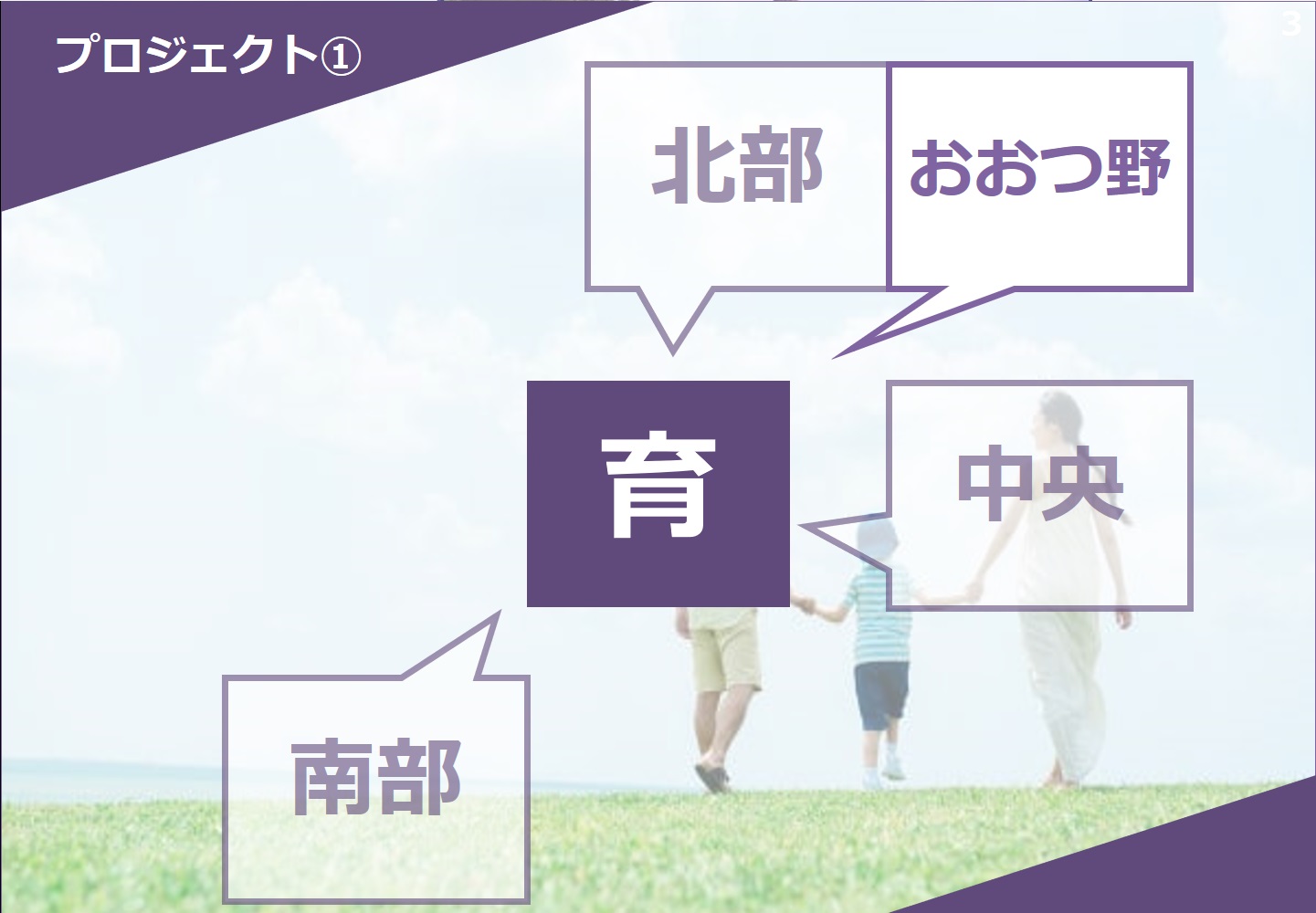
育
住みやすさを形成する上で女性の社会進出や地域コミュニティの希薄化といった社会的背景を踏まえ、働く親への子育て支援の充実や多世代コミュニティの形成を図る。
南部・中央地区に偏っている子育てサービスを今後、需要が見込める北部・おおつの地区においてもサービスを創造することで多世代にわたる市内循環を目指す。
プロジェクト一覧
病児保育・多世代コミュニティ
提案の背景
まず土浦市の課題・現状を考えた。数多く挙げられた中で、私たちのコンセプトである循環都市を考えたところ、・病児保育がない
・コミュニティ施設が南部地区、中央地区に集中している
・子育て環境が偏っている
これらの課題の改善を目指すことにした。課題を踏まえたうえで地区の特徴を考えた ところ、病院が移転され、ニュータウンがあることで需要のあるおおつ野地区でプロ ジェクトを行うことに決めた。
内容
土浦協同病院の既存スペース(2階講堂スペース)を保育スペースとして確保し、平日は病児保育として、休日は多世代コミュニティ施設として利用する。
| 病児保育 | 平日9時~19時 定員10人 年会費1000円 一日3000円 インターネットで予約 |
|---|---|
| 多世代コミュニティ | 休日10時~17時 季節ごとのイベント、高齢者との交流を活かした囲碁大会、中学生を誘致した勉強会などを実施。 呼び込み方 病児保育の会員案内とともにホームページで案内。 保育園、幼稚園の保護者説明会や小児科利用者にチラ シ配布。 保護者の病院利用時の預かりとしても利用。 |
費用・効果

職
若い世代が職を求め市外へ転出することで生産年齢人口が減少しているという土浦市の現状を踏まえ、土浦市だからこそできる「職」の環境を提供する。 主に、都市機能が集約されている中央地区と農業が盛んな新治地区において、それぞれの特色を生かした土浦らしい「職」の提供により、市外への転出抑制、Uターンの機会増加などの効果を期待し土浦市内での世代循環を目指す。
プロジェクト一覧
チャレンジショップ・農地バンク
①チャレンジショップ
提案の背景
平成 30 年度の土浦市では、中心市街地に 69 軒の空き店舗を抱えており、特にモール 505 は深刻なシャッター街化が進行している。しかし、モール 505 のレトロチックな空間と、近辺に立地する平成
29 年度開館の「新図書館」及び関東最大の古書店
「土浦古書倶楽部」は、大きなポテンシャルを持つ。このポテンシャルを最大限活かし、中心市街地の空洞化を解消するために、モール 505 に古書店街を形成する。本に触れ、ページをめくり、未知の世界との出会いを探す古書店固有のフィジカルな購買形態は、高度情報化社会による身体性を伴わない購買形態との差別化を図り、大きな価値を保持し続ける。また、古書店は体験を提供する場であるが故に、古書を取り巻く空間は大きな役割を担うが、モール 505 固有のノスタルジックな雰囲気は古書に強くマッチし、日光が当たりにくいデメリットは本が焼けないというメリットに転換する。
内容
モール 505 を古書店街にする手段として以下の複数のプロジェクトを実施する。
【チャレンジショップ】
チャレンジショップとは、開業希望者に対し開業支援によるお試し開業を提供することで終了後の独立出店による空き店舗減少を図る事業である。
本事業では、専門分野別に古書店開業者を募集、選定することで多世代対応と集積の利益を図る。
開業支援は、モール 505 の1階空き店舗での小規模ブースの提供、家賃の 2/3 援助及び、土浦古書倶楽部による経営セミナーとし、契約期間 6 ヶ月(更新限度 5 回)とする。
なお売上の 10%をロイヤリティとする。
独立の際には、「土浦市中心市街地開業支援事業」の利用によりモール 505 の空き店舗への独立を促す。(※現状では対象者要件を満たさないので改定が必要)
【新図書館との連携事業】
<としょかんのこしょてん>
新図書館内に古書店ブースを設け、月ごとに各店舗が入れ替わりながら、自店の紹介を兼ねたお勧め本の貸し出しを行うことで、古書店来店の敷居を下げる。
<古書の通帳サービス>
平成 30 年から新図書館で実施されている「本の通帳サービス(乳幼児から高校生までが読んだ本の履歴を銀行の通帳のような手帳に記録できるサービス)」と連携し、チャレンジショップにも記帳機を導入することで古本を買った際にも記帳できるようにし、若者の来店を促す。
【連携イベント】
古書と新図書館で蔵書として活用できなかった寄贈本を販売する古本市と土浦カレーフェスティバルを組み合わせたイベントをモール 505 前の広場で実施することで交流の場としての再建を図る。
費用・効果
費用
2,300,000(円)(既存の隣接した空き店舗 3 軒に 7 店舗開業し、契約限度を満たした場合)
効果
本に関連する既存ストックを最大限活用することで、空き店舗減少や開業者創出という商業の域に留まらない、本を介した人と空間の連続性の獲得により、中心市街地の求心力を取り戻す。
②農地バンク
提案の背景
現在、全国的にも、農業従事者の高齢化が進み、後継者不足が問題視されている。土浦しにおいても例外ではなく、特に新治地区には農地が多い。新治地区の農地活性化を期待して、農業の担い手不足を解消し、職業を通じて人とモノが世代を超え地域に根差しことで土浦の活性化を促す.
農地中間管理事業のメリット措置[1]といった動きに合わせ、耕作放棄地の整備を行い農地利用ができるようにする.
内容
1.特に耕作放棄地の多い新治地区の農業従事者の土地を、農地バンクに登録するよう説明する:通知・連絡に費用はかからないと仮定
2.農地整備:
新治地区の畑の面積:耕作放棄地 151ha(土浦市の耕作放棄地の面積の9割を畑が占めるという仮定)
費用・効果
費用
農地整備費用は農林水産省の農地整備課及び埼玉県の先行事例[2][3]を参考にした.
1haあたり2千万円として30.2億円
工期は7年
負担割合は10%(他:62.5%国 27.5%県)で土浦市の負担は3億200万円となる.
効果
便益として、耕作放棄地から新たに得られる所得を想定する.
耕地面積1~2haの農家の所得の都道府県平均が1719千円である[4]から10a/115千円所得が得られる.
経営費も圧縮される. 2/3と仮定すると、耕地が1~2haの農家の都道府県平均は10aで243千円のため年間約81千円/10aの便益が期待できる.
併せて年間196千円/10aとなる.これを151haに適用する.
よって年間で2億9600万円の便益が得られる.
費用効果便益は工期を7年とすると、一年で4億6千万円の費用がかかる.
社会的割引率を4%、供用期間を50年とするとB/Cは1.52>1であり、実施の妥当性が認められる.また総便益が総費用を上回るのは竣工後18年である.(事業開始より25年)
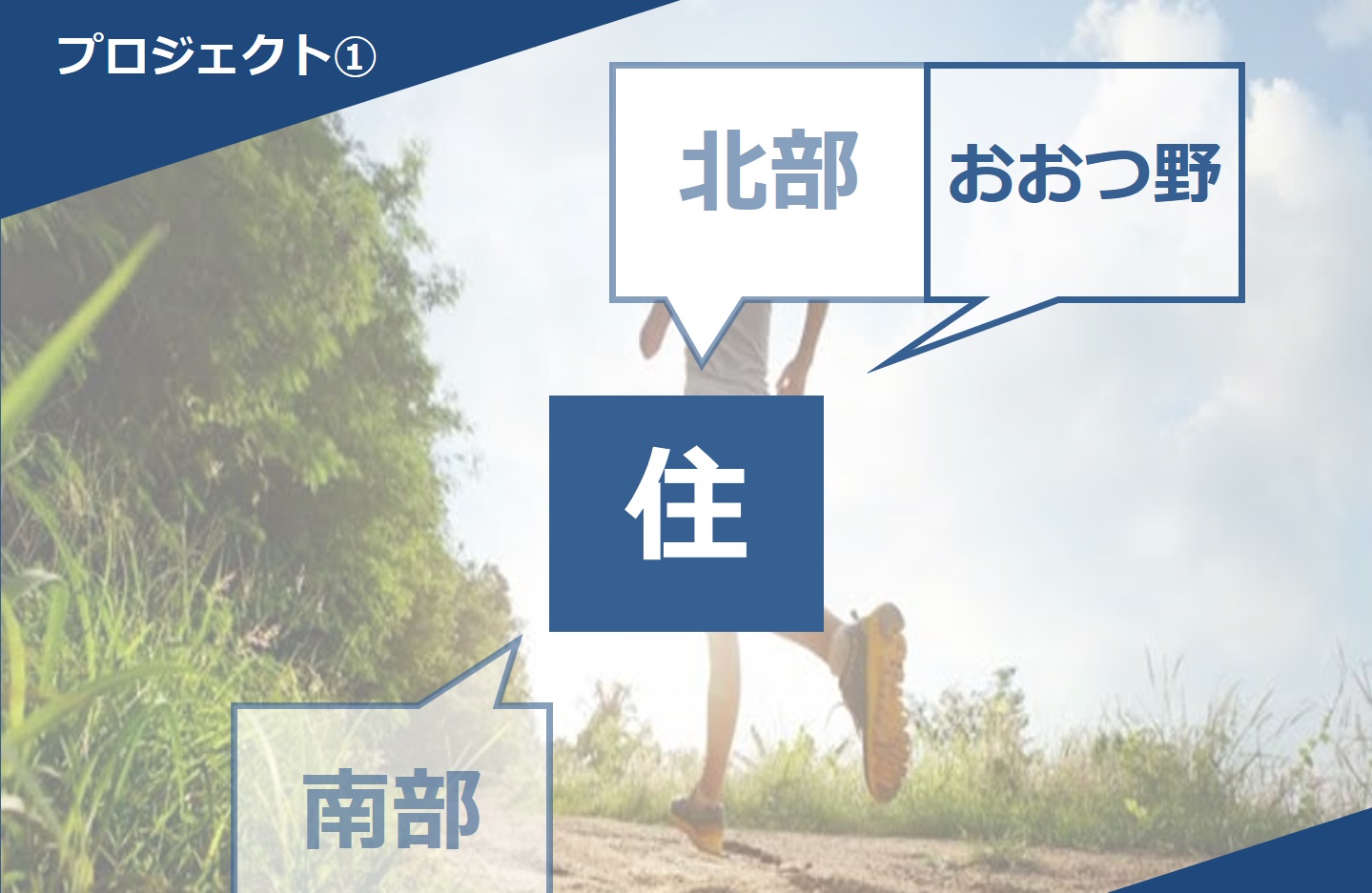
住
中心市街の災害リスクの高さや、犯罪率が高く治安が悪いといった土浦市の現状を踏まえ、 防災・防犯対策を行うことで、安心して暮らせる住環境を提供する。 主に、住宅が多く存在する北部・おおつ野・南部において、災害時の避難所の確保や防犯ソフト対策を行う。安心して暮らせる住環境を提供することで、市民の定住化を図り多世代にわたって暮らせる土浦市を目指す。
プロジェクト一覧
避難所認定・防犯ソフト対策
①避難所認定
提案の背景
現在、土浦市の指定する避難所は28か所あり、受け入れられる避難者数はおよそ12,944人である。一方で、茨城県南部直下地震が発生した際に予想される避難所生活者数はおよそ43,000人であり、現避難所のキャパシティを大きく上回っている。
内容
避難所のキャパシティ問題対策として、土浦市の「避難場所」のうちで屋内避難が可能な場所およびキャパシティが大きく非難の受け入れが可能であると考えられる「土浦市市民会館」「茨城県県南生涯学習センター」をはじめ、高校や利用可能と考えられる施設を避難所化し、かつ避難所においてプライバシーが確保される環境を整える事業を提案する。
費用・効果
費用
避難場所を避難所にすると、新たな設備が必要となる。高校や生涯学習センター、市民会館はエアコンが設置されているため新たに必要ではないが、既存建築はないため必要している。土浦市の報告では、エアコン、暖房機が整備されているのは指定避難場所41か所のうち0か所だった。約10坪でエアコン1台60~70万かかるため38施設それぞれ最低1台不足しているとしても最低でも2,280万以上かかる。
毛布、ベッドの確保も必要となる。防災用毛布は通信販売サイトのAmazonで10枚24,000円、エアーマットは通信販売サイトのBBnetで20枚36,000円だった。この費用を基準として考える。指定避難所のデータによると毛布29施設、ベッドは0施設に完備されている。さらに高校と避難場所ではない茨城県県南学習センターと土浦市民会館にも配布するとして、不足分の20施設に毛布を配布、48施設にエアーマットを配布する。
また、新たな避難所のキャパシティにおいて27,393人避難すると仮定する。これは2019年12月現在の避難所、避難場所と茨城県県南生涯学習センター、市民会館における収容人数である。これを新たな避難場所数で割ると一施設当たり548人として、毛布は2400*548*20=2630万円、エアーマットは1800*548*48=4734万円であり計7364万円となる。
よって、空調設備の配置、最低限の滞在用品にかかる費用は最低でも9644万円となる。
効果
キャパシティの効果
避難所を増やした場合の避難所分布が図2のようになる。赤い数字が、増加した避難所受け入れ人数となる。これにより、避難所受け入れ人数は14,449人増加し、市全体で合計27,393人となる。例えば土浦駅南西の地域では、常総学院高等学校や土浦日本大学高等学校の避難所化により、大きく避難受け入れ可能者数が増加している。
プライバシー保護の効果
プライバシー保護の効果はスフィア基準に基づき算定する。本文の基本行動の欄に、「影響を受けた世帯は、基本的な家庭活動を行うための適切な居住スペースを有している」と記されており、「居住者とその家族の「財産を守るため、必要最低限である屋根と四方の壁を提供し、身体的安全、尊厳、プライバシーおよび天候からの保護を得られるよう取り計らう」「最適な照明条件、換気、温度の快適さを提供する」と続いている。
これは四方の壁と屋根がある避難所にエアコンを配置して解決できると仮定する。
また、安全、健康的でかつ良質な睡眠をとるための十分な量と適切な質の物資を所有している基準として、一人当たり最低毛布1枚とベッドが挙げられている。これを支給し、滞在に適した環境が提供できるとする。
②防犯ソフト対策
提案の背景
刑法犯総数が茨城県で一位である土浦市において防犯対策は重要な課題となってい る。循環都市を目指すうえで住みやすさは一つの重要な要素であり、防犯の課題改善は欠かすことができない。
内容
犯罪が起こりやすい、大通りから外れた住宅街における防犯対策である『一戸一灯運動』。一戸一灯運動とは、地域の方々が連携し、夜間、自宅の門灯を一晩中点灯することで、夜間の犯罪発生を予防する環境をつくる運動である。
費用・効果
費用
一か月の電気使用料金は60円程度(一般的な15ワットの蛍光灯1個を1日6時間ほど転倒した場合)。18時から翌日8時まで点灯していたとしても、一か月150円程度である。(住民負担)チラシ代は36,542戸*10円=365,420円(市負担)
効果
夜間の通りを明るくすることで、地域住民が安心して歩くことができる。犯罪者が恐れているものは住民の視線であり、街を明るくすることで、犯罪者は見られることを恐れるとともに防犯意識の高まりを感じ、その地域に近づきにくくなる。一戸の小さな灯かりが地域の大きな安心感に変わるのです。

遊
市内広域に存在する自然環境や観光資源を活かし、土浦市ならではの遊べる場所を提供することで、周辺都市との差別化を図る。 主に、霞ケ浦に隣接した広大な公園を持つ南部地区とサイクリスト向けの観光資源「リンリンロード」が通る新治地区において、遊べる場所を提供する。 観光資源を活かした街づくりによる周辺都市からの人口の流入や地域に根ざした公園による魅力的だから持続的な多世代に愛される憩いの場による世代の循環を目指す。
プロジェクト一覧
霞ヶ浦総合公園・りんりんロード
①霞ヶ浦総合公園
提案の背景
「平成 27 年度土浦市市民満足度調査」における「“土浦ならでは”のもので、まだ生かしきれてないと思うものは?」という質問に対して、「霞ヶ浦」が 16.8%で一位、「霞ヶ浦総合公園」が 5.4%で五位となっており、市民も霞ヶ浦、霞ヶ浦総合公園に対し、多種多様な公園設備や美しい景観などのポテンシャルはあると考えているが、現状それらを生かせておらず、施策を行う必要があると考えた。また、平成 30 年度において、土浦市の霞ヶ浦総合公園整備事業費は1億 3758 万円となっており、公園の維持・管理費、運営費等のコストは小さいとは言えない。また、これに伴い、市の財政がさらに悪化することも想定され、将来の公園管理の不透明
性が問題だと考えた。
内容
今回の事業では、公募設置管理制度(Park-PFI)を活用する。Park-PFI とは、平成 29 年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利用者の利便性向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度である
プロジェクトの具体的な内容としては、「保育園の建設」・「駐輪場の建設」・「カフェの誘致」を行う(図 2)。「カフェの誘致」においては、現在、霞ヶ浦総合公園にレストハウスはあるが、軽食を取れて憩える場が少ない。そこで、Park-PFI 制度を活用し、カフェを誘致し、平日も休日も市民が憩える場を提供する。「保育園の建設」においては、老朽化した霞ヶ丘保育園の建て替え場所として提案する。これまで法的に可能でなかった保育園の建設を Park-PFI 制度を利用することで行う。公園内に保育園を設置することにより、子どもが自然の中で遊ぶことができ、親同士の交流の場や多世代コミュニティの形成を促すことが期待できる。「駐輪場の建設」に関しては、150 台規模の駐輪場を建設し、りんりんロードを利用するサイクリストのカフェの利用や現在園内にある入浴施設「霞浦の湯
(かほのゆ)」の利用を促す。
費用・効果
Park-PFI の性質として、新たな費用は必要としない。公園利用者のメリットとして、施設が充実することで享受できるサービスが向上する。また、老朽化し質が低下した施設の更新が期待できることで,公園の利便性,快適性及び安全性が高まる。公園管理者のメリットとしては、公園整備,管理運営にかかる財政負担が軽減される。土浦市のメリットとして、新たな施設設置により,集客力の向上が図られ,まちや地域の活力,にぎわいの創出など相乗効果が期待できる。
以上の施設を、収益施設を保育園とカフェとし、特定公園施設すなわち、公共部分を駐輪場とし、民間が設備・維持管理を行うのに加え、国の補助金(都市開発資金、社会資本整備総合交付金など)を活用することにより、市の歳出を減らす。
②りんりんロード
提案の背景
現在、土浦市の観光客の多くは土浦花火大会やキララ祭りを目的に訪れていて、イベント依存型の観光といえる。また、日帰り観光客もとても多いのが現状で、約90%を占めている。そして、土浦市は観光基本計画でサイクルツーリズムの推進を掲げていて、実際に市内におけるレンタサイクル貸出台数は右上がりに増えている。そこで、日帰りサイクルツーリスト者の経済効果上昇を目指す。
内容
現状のりんりんロードは道中に地域を味わえる店がなく、駅跡もただの休憩空間となっているため『駅跡にインスタバ映えは地域密着型移動販売車を』を提案する。駅跡に地域の農産物を使ったメニューを販売する移動販売車を誘致することによって、サイクリング中の味気ないコンビニ飯が地域を楽しめる食事となる。また、メニューの見た目を可愛らしくすることで、評判となり利用者も増えると考えられる。また、季節感のある花を周囲に置くことで、桜しか見ごたえのない道でもほかの季節の花を感じることができる。
費用・効果
費用
移動販売車の開業資金として約300万円とする。また、1日あたりの雑費を7000円とする。
効果
つくば・霞ヶ浦りんりんロードの年間利用者数は平成30年度で約8.1万人であり目標人数は約10万人である。このうち半数の5万人が土浦区間を利用すると仮定し藤沢休憩所に移動販売車を誘致することで年間約8万人が土浦区間を地用するようになると想定する。
式;(1個当たりの利益)×(年間購入者数)÷(年間土日数)=(1日の利益)
上記の式で計算すると1日当たり2,8500円の利益が得られ、開業資金等を差し引いた1日の純利益は2,1500とする。。年間の利益としては223,6000円であり、開業資金は約1年半で回収できる。

交通
モータリゼーションが進み、公共交通の利便性が低下する土浦交通の現状を踏まえ、渋滞解消、公共交通の利便性向上を目指す。モビリティの拠点を作り、自動車を誘導することで公共交通と自動車を連携させる土浦らしい交通を提供する。広域に広がる土浦市の人口分布にサービスを行き渡らせるべく、循環の基盤となるような交通を目指す。
プロジェクト一覧
バスターミナル・トランジットモール
提案の背景
現在の土浦市では、利用者減少から生じる公共交通の負の循環が大きな課題として挙げられる。
この課題によって、自動車の利用者増加による渋滞の発生や交通網の縮小を起因とした交通弱者の増加といった諸課題に派生している。
しかし、現在の土浦市の自動車利用率は非常に高く、自動車利用を無視することはできない。
よって、自動車と公共交通の連携がとれた交通網を目指すことで、交通全体の利便性を上げ、市内全域に交通サービスを供給できるような市内循環の基盤を形成する。
内容
自動車と公共交通の連携を実現するために
1.自動車と公共交通を結ぶ新たな拠点の整備
2.自動車の誘導
3.拠点間の公共交通機関の魅力向上
の3つののアプローチに対応したプロジェクトを実施する。
【パーク&バスライド】
バスターミナルという新たな拠点を設け、バスを集約することで稼働率をあげ、バスの定時性を確保します。
また、低価格の駐車場を設けることで、自動車での利用をしやすくします。
市街地環状道路沿い2箇所にバスターミナルと駐車場を建設(図3)し、朝夕の通勤時間帯にバス専用レーンを設けます。
【トランジットモール】
土浦駅西口駅前のエリア(図4)内で朝夕の通勤時間帯に自家用車の利用を規制します。
これにより、中心市街地への自動車利用の抑制を図ります。
バスとターミナル駐車場の利用料金を定額化した定期券を作成します(表 1)。
また、この定期を提示することで提携店での買物割引を受けることができます。
費用・効果
収入は 1 億 8 千円(ターミナル・駐車場・定期券使用料)、支出は 22 億 2 千万円(建設費など初期投資)であり回収に 12 年かかる。効果は JICASTRADA と CUE モデルで検証を行ったところ、公共交通の利用者が 1.8 倍に増え、4 億円の収入増加につながる。
この経済効果により、バスの路線増加や渋滞緩和など、波及的に多くの効果が見込め、交通全体に好循環が生まれる。
