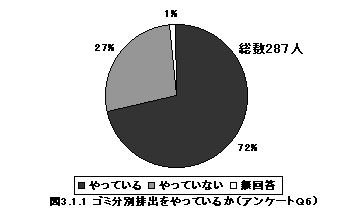
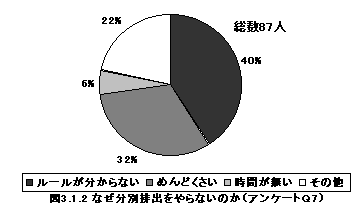
3.調査結果の分析および仮説の検証
3.1分析排出の現状調査の結果および考察
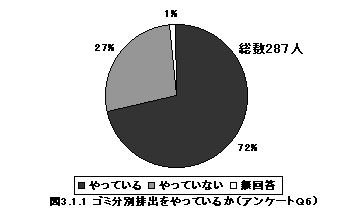
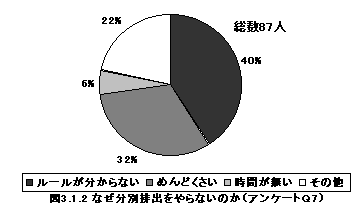
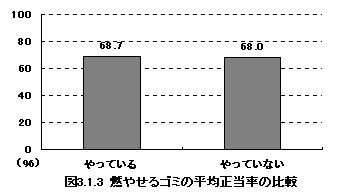
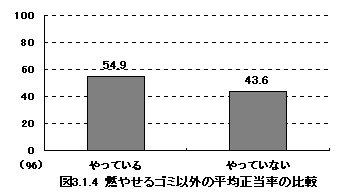
比較の対象として分別意識の違い、つまり「分別をやっている」と答えた人と「分別をやっていない」と答えた人に分けて、Q
5での具体的ゴミの排出場所の正当率を比較した。更に、傾向が良くわかるようにゴミの種類を燃やせるゴミと燃やせるゴミ以外(燃やせないゴミ、古紙・古布など)にわけて比較した。まず、図
3.1.3は燃やせるゴミの平均正当率の比較である。結果からわかるように、燃やせるゴミに関しては両者とも70%弱の数値でありそれほど差はないと言える。しかし、注目するのは図3.1.4の燃やせるゴミ以外での合計平均正当率である。「分別をやっている」と答えた人は54.9%であるのに対し、「やっていない」と答えた人は43.6%とその差は10%以上ある。「分別をやっている」と答えた人の正当率が高いのは予想できることであるが、燃やせるゴミに関しては両者の差が無いことから、分別をやっていない人は燃やせるゴミ以外のゴミも燃やせるゴミとまとめて出してしまっているのではないかと推測できる。その他、「分別をやっている」と答えた人も正当率が
70%に満たないことから、全員が正しい知識を持っているとは言えず情報の提供が必要である。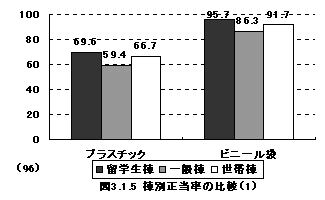
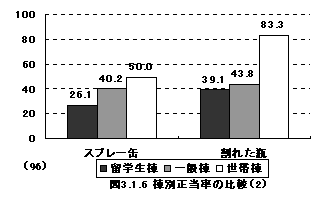
まず、図
3.1.5の結果から3者に多少の差はあるものの、ゴミの種類による正当率の差の傾向は特に見受けられない。しかし、図3.1.6の結果を見ると棟別の傾向がはっきり読み取ることができる。つまり、正当率が良い順番に世帯棟、一般棟、留学生棟である。ここで、なぜグラフを2種類に分けた理由は(1)の方は正解が燃やせるゴミであり、(2)は燃やせるゴミ以外のものである。つまり、燃やせるゴミに対しては3者の傾向は見られず、燃やせるゴミ以外に対しては先ほどのような傾向があると言える。12項目の具体的なゴミの排出場所を質問したのだが、燃やせるゴミとそれ以外に分けた場合、ほぼ同じような傾向が見られた。このことは、最後の付録を参照していただきたい。ここで、考えられるのは【2】で結論つけたように燃やせるゴミの正当率というものは分別意識があってもなくても比較的変化が出ないので、3者の差を本当に比較するのならば(2)の燃やせるゴミ以外の正当率で比較すのが良いということである。よって、分別状況は世帯棟、一般棟、留学生棟の順で良いのではないかという推測ができる。このことはゴミ組成分析で実際に検証することができると考える。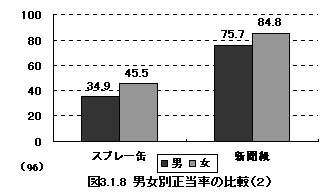
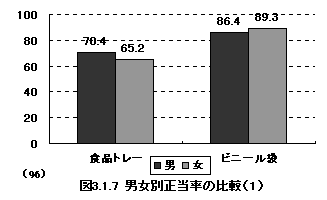
棟別の正当率の比較に続いて、男女別の比較を行なう。棟別の時と同じように図
3.1.7に燃やせるゴミの正当率の比較、図3.1.8に燃やせるゴミ以外の正当率の比較を載せた。(1)については、男女の差がそれほど無く、グラフには載っていないがプラスチック:男性58.0%・女性64.3%、また発泡スチロール:男性61.5%・女性56.3%と燃やせるゴミについては一貫した傾向はない。実際の傾向が見られると考えられる(2)の結果を見ると、男性より女性の方が良いという傾向が見られる。この傾向は段ボール:男性47.3%・女性58.9%、電池:男性62.7%・女性69.6%と燃やせるゴミ以外のゴミに関して一貫している。【5】その他の特徴・傾向
電池、蛍光灯などの危険物は特に正しい排出場所に処理されなければならないのだが正当率がそれそれ
65.9%、59.9%とそれほど高くなく、専用回収ボックスが共用棟にあることを伝える必要性がある。また、最も正当率が悪かったペットボトル(8.0%)については「調査結果の分析及び仮説の検証3.3」を参照していただきたい。【6】推測される傾向のまとめ
●組成分析より得られた結果と考察
【1】組成分析の結果
ごみの組成分析から得られた全体の傾向としては,休日後の排出日(例,土・日後の月曜日にある排出日)のゴミ排出量が,その他の排出日の排出量よりも大きいことが挙げられる.
これは,一般学生棟,留学生棟,世帯棟いずれにも言える.また全体の分別状況について,棟ごとの分別状況についてみてみる.
図3.1.9はゴミの総量に対する混入率(分別されていないゴミの比率)を示したものである.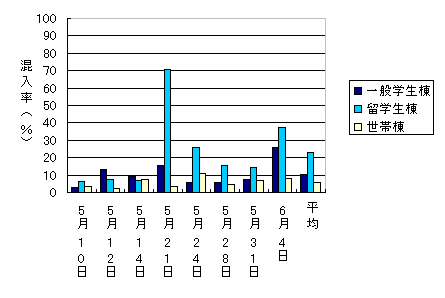 この数値が高い程,ゴミ分別が出来ていないことを示す.その結果,留学生棟の混入率が,一番高いことが分かった.
この数値が高い程,ゴミ分別が出来ていないことを示す.その結果,留学生棟の混入率が,一番高いことが分かった.
図3.1.9 全ゴミ総量に対する混入率
次にゴミのボックスごと,種類別ごとの分析についてである.図3.1.10は,ボックスごとの混入率(指定以外のゴミの比率)を示したものである。これを見ると「燃えるゴミ」のボックスでの混入率が低く,「燃えないゴミ」「缶・ビン」のボックスでの混入率が高いことが分かる.
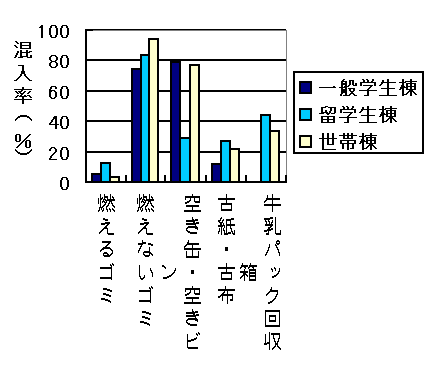
図3.1.10 各ボックスごとの混入率
図3.1.11は,種類別のゴミ分別度を表わしたグラフである.ゴミ分別度は,数値が大きいほど,その種類のゴミは分別されている(指定の場所に排出されている)ことをあらわしている.
これを見ると,燃えるゴミ,燃えないゴミは比較的分別されていることが分かる.またペットボトルの分別率が極めて低いことが分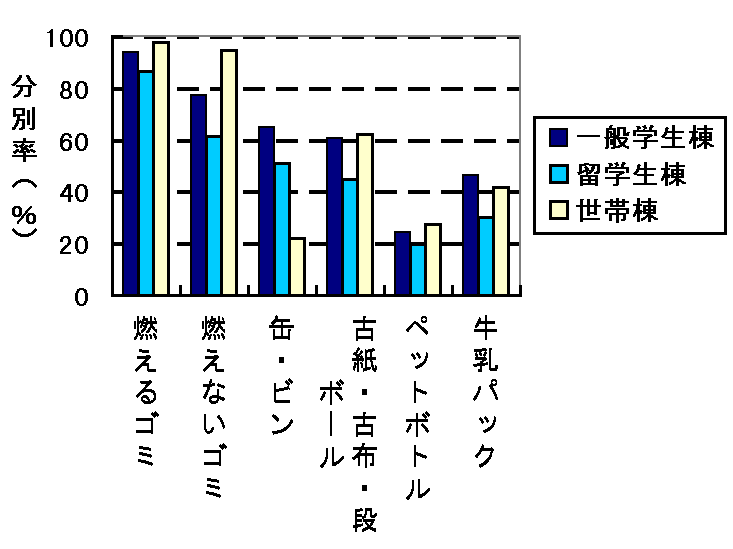 かる.
かる.
図3.1.11 種類別のゴミ分別率
【2】考察
全体の分析において分かることに,留学生棟での混入率の高さがあったが,この理由としては,留学生場合生活習慣,言語の違いが原因でゴミ分別がうまく行われていない可能性が考えられる.
燃えるゴミと燃えないゴミの分別の状況については,以下の様に理由が考えられる.燃えるゴミの分別の成績が高いのは,燃えるゴミの捨て場所が明確であることに加え,ゴミ全体に占める燃えるゴミの比率が大きいために,他のゴミの混入による影響が小さくなることが理由と考えられる.また「燃えないゴミ」のボックスの分別の悪さは,燃えないゴミ自体の排出量が少ないため,燃えないゴミ以外のゴミの混入による影響を受けやすいことにある.
しかし「缶・ビン」のボックスの場合は、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」のボックスと同様に,そのボックスに他のゴミの混入することからだけでは,その状況を説明できない.そこで缶・ビンが、他のゴミの回収ボックスに排出されている状況も同時に踏まえて考えなければならない.
まず,「缶・ビン」のボックスに混入してくるゴミを見てみると,その中で多いものとしては,燃えるごみ,ペットボトルが挙げられる.逆に缶・ビンが混入しているボックスとしては,「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「古紙・古布」が挙げられる.
燃えるゴミの場合,「燃えるゴミ」のボックスと「缶・ビン」のボックスが離れていることを考えると,缶・ビンを燃えるゴミとまとめて捨てた,あるいは,燃えるゴミと缶・ビンを捨てたという、「ついで捨て」の状況が考えられる.
「燃えないゴミ」「古紙・古布」に捨てられる状況は,これらのボックスと「缶・ビン」のボックスが隣り合っていることを考えると,分別したにもかかわらず,排出場所を間違ったという「排出ミス」が考えられる.ペットボトルの混入もこの「排出ミス」で一部は,説明がつくがペットボトルの場合,それ自体が分別状況が悪いこともあるので,ペットボトルの分別排出状況が良くない理由を別に考える必要がある.
ペットボトルの場合は,「ついで捨て」「排出ミス」以外の理由も考えられる.第1に考えられる理由としては,ペットボトルの分別に対する認識が低いことである.これは,アンケートの分析結果から推察される.
第2の理由として考えられるのは,ステーション内での掲示の問題である.これは,他の種類のゴミと異なりボックスにある掲示がなく,その代わりにステーションの入り口付近に貼ってある,ボックスの掲示よりも見にくいゴミ分別表のみが,ペットボトルの排出先を示しているという,現状からその様に推察される.
【3】組成分析のまとめ
組成分析の結果をまとめると次の様になる.
・休日・祝日後のゴミ回収日のゴミ排出量は,他の回収日の排出量に比べて大きい.
さらに考察の結果をまとめると次の様になる.
ある.
3.2.牛乳パックに関する仮説検証
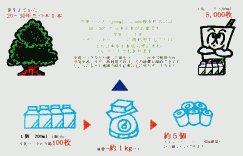
図3.2.1 牛乳パックの資源的価値
これは、丸富製紙株式会社のホームページ(http://www2.shizuokanet.ne.jp/usr/marutomi/reccycle2.html)から抜粋した図である。1Lの牛乳パックを1000枚作るには、20〜30年経つ立木が1本必要になる。しかし、その牛乳パック8枚からトイレットペーパー1個ができる。牛乳パックからトイレットペーパーを作ることで、トイレットペーパーを作るための木を切らなくてすむようになることから、牛乳パックの資源的価値は大いにあるといえる。
【2】仮説
仮説:宿舎に牛乳パック回収ボックスを設置すれば、居住者は牛乳パックの分別回収に協力し
てくれるだろう
【3】牛乳パックに関するアンケート結果
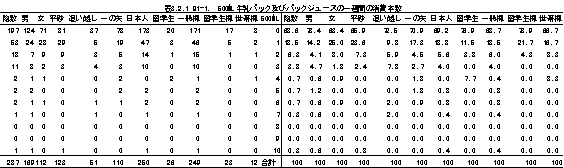
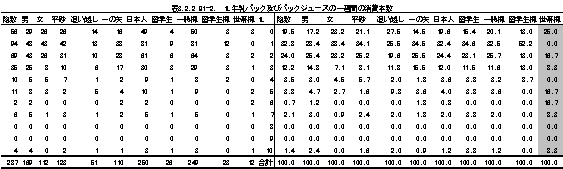
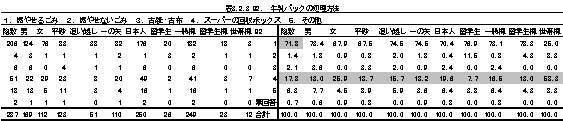
これは、アンケートQ2「牛乳パックをどこに排出しているか」という質問の回答結果である。総数の比率を見ると、70%を超える人が「燃えるごみ」と回答している。このことから、多くの人が牛乳パックをリサイクルに出さず、燃えるごみとして廃棄してしまっていることがわかる。次に、「スーパーの回収ボックス」と回答した人の比率を見てみると、男女別では女性方が多く、日本人留学生別では日本人の方が多く、棟別では圧倒的に世帯棟が多く、宿舎別ではあまり差異ないという結果になっている。つまり、男性よりも女性、留学生よりも日本人、一般棟や留学生棟よりも世帯棟が「スーパーの回収ボックス」を利用していることになる。
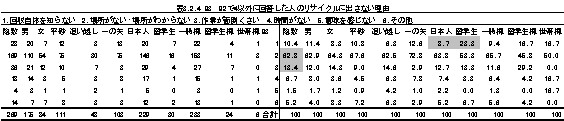
これは、アンケートQ3「牛乳パックをリサイクルしない理由」という質問の回答結果である。
総数の比率を見ると、「場所がない・場所がわからない」「回収自体を知らない」と回答した人が全体の76.2%を占めている。このことから、宿舎に回収ボックスをおいて回収していることを浸透させれば、リサイクルに協力してくれるかもしれないという期待が持てる。
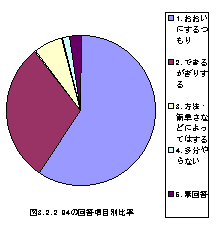
これは、アンケートQ4「牛乳パックの回収ボックスを宿舎に設置したらリサイクルに協力するか」という質問の回答結果をグラフで表したものである。総数の比率は「おおいにするつもり」「できるかぎりする」と回答している人が全体の90%近くを占めている。このことから、宿舎に回収ボックスををおいて牛乳パック回収を行えば、それなりの結果が期待できると考えられる。
【4】牛乳パック回収実験

これは回収ボックスを設置した場所の地図である。回収ボックスは共用棟及び、北6・北8・北9の各ごみステーション内に設置した。なお、北6は一般学生棟、北8は留学生棟、北9は世帯棟前の各ごみステーションのことである。
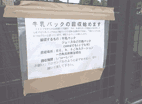
これは、牛乳パック回収実験をすることを告知したものである。掲示した場所は、共用棟の掲示板と各回収ボックスの前および各個人のメールボックスである。回収期間は2週間で、牛乳パックの処理の仕方を知らない人のために、告知文のにサンプルをつけた。また、留学生棟前(北8)ごみステーションには英語による告知もした。

これは、ごみステーションに置かれた回収ボックスの様子である。
【5】牛乳パックに関する組成分析結果
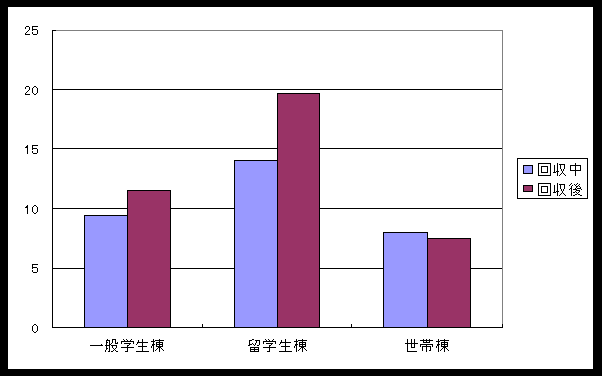
図3.2.4 実験中実験後の比較
これは、回収ボックス以外に出された牛乳パックの本数を実験中と実験後で比較したものである。本数は1Lと500MLを区別せず1本としている。まず、一般学生棟と留学生棟を見ると、実験中と実験後で本数が増加している。これは、普段回収に協力していない人が、たまたま近くに回収ボックスかできたので、実験中は回収に協力してくれたが、実験後は回収ボックスがなくなったので牛乳パックをごみとして捨てるようにたため増えたと考えられる。このことから、近くに回収ボックスがあれば回収に協力してくれる人がいるといえる。次に、世帯棟を見ると、実験中と実験後で余り変化が見られない。
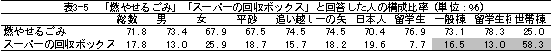
これは、アンケートQ2「牛乳パックをどこに排出しているか」という質問の回答結果の抜粋である。「スーパーの回収ボックス」と回答している人が、棟別で見ると世帯棟で58.3%にものぼっている。このことから、世帯棟の人は普段から回収ボックスに出しているため、宿舎に回収ボックスがあろうがなかろうが、牛乳パックリサイクルに協力しているため変化が見られなかったと考えられる。
以上のことから宿舎に回収ボックスをおくことは有効であるといえる。
【6】 牛乳パック回収実験の結果
まず
, 確認のためこれまでの事柄をまとめると, 以下のようになる.
実験期間:平成
11年5月14日から28日までの2週間実験場所:一ノ矢宿舎共用棟および一ノ矢宿舎ゴミ集積所 北6 北8 北9
告知方法:回収実験開始1日前に告知文を各実験場所に貼るとともに
, メースボックスに同様の告知文を配付することで
, 一ノ矢宿舎に住む全学生に対し告知をおこなう.牛乳パックの処理方法については
, 実物を各回収ボックスに置くという方法をとっている
. また, 実験開始1週間後にあたる22日(土)から, 必要性を感じたため
, 英文による告知も行っている.実験内容:回収ボックスに出された牛乳パックを1日置きに回収し
, 各回収場所に出された牛乳パックの本数
, 状態(きちんと処理されているどうか 付録5.3参照)のほかに
, ゴミが混入していないかを調べる. また, これらの変化を分析することで
, 回収ボックスの設置の意義があるか, どのような回収状況が望ましいかについて検討する
.
写真3
.2.3 回収結果
牛乳パックの回収実験の結果は以上のようになった
. 回収率11%という数字は, 現在のペットボトルの全国平均回収率が9%であることを考えると, 今回の回収には十分な数量が集まったと言える
. しかし, アンケート(Q4)の結果と比較すると, かなり低い数値に留まってしまったといえる.なお
, 回収率を算出するに当たり用いた総需要量は以下の式によって求めた. 式でつかわれている数値のうち, 1週間当たりの平均消費本数はアンケート(Q1)より, また, 現在の一ノ矢宿舎総入居人数は厚生課から得た6月1日現在での入居人数を使用している
.
・計算式
期間中総需要量=1週間当たりの平均消費本数×現在の一ノ矢宿舎総入居人数×2週間
=
2.46本×1684人×2週間=
8285本
・回収状況
牛乳パックの回収状況を以下の図3
.2.5, 3.2.6, 3.2.7で示した. 各回収ボックスでのより詳しい回収状況については, 付録7.3を参照していただきたい.
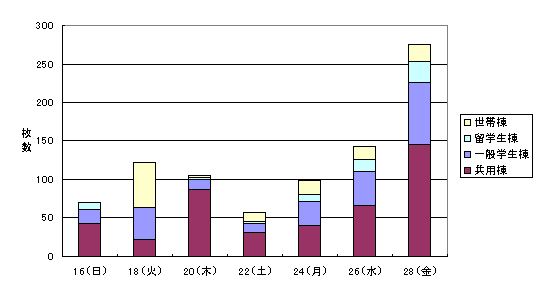
図
3.2.5 回収状況
図3
.2.5から回収数の変化を見てみると, 土, 日, 月曜日の回収数が少ないことがわかる. また, 24日以降, それまでほとんど回収されていなかった留学生棟での牛乳パック回収数が, 徐々に増加していることから, 英文による告知の効果が見られたといえる. 28日(金)の回収数が非常に多くなっているが, これは回収最終日であるため枚数が増えたと考えられる.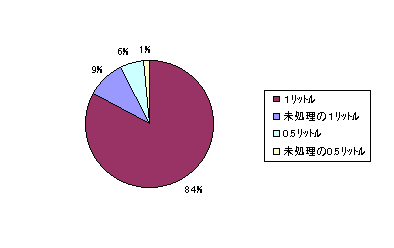
図
3.2.6 回収数の内訳つづいて回収数の内訳についての分析にはいる
. 図3.2.6から, 回収数に占める0.5リットルの牛乳パックの回収率は約7%(66枚)である. しかし, これをアンケート(Q1)での平均消費本数における0.5リットルの牛乳パックの構成比率(約23%)と比較すると, 0.5リットルの牛乳パックの回収率は1リットルでの回収率に比べ, 良くないといえる. また, 未処理率は約10%(92本)にものぼっており, 回収ボックスへのゴミの混入率は, 付録7.3からもわかるように, 40%以上となっている. これらのことから, 筑波大生のゴミ問題に関する意識の低さ, モラルの低さがうかがわれる.未処理の牛乳パックが問題であるのは
, 異物が牛乳パックに付着することで, 牛乳パックの資源的価値がなくなり(リサイクルができなくなる), また異物による悪臭が, 各リサイクル行程での回収作業員の作業効率を, 著しく低下させることが懸念されるためである.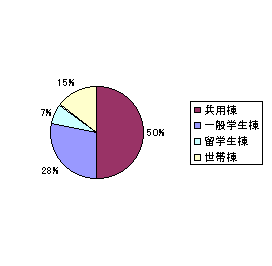
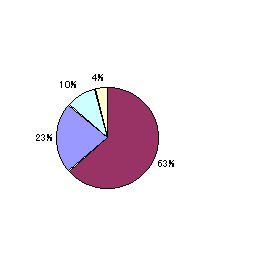
図
3.2.7 各回収ボックスでの回収効率の比較
次に
, 各回収ボックスでの回収効率比較を行う. 図3.2.7の2つの円グラフは, それぞれ各回収ボックスで回収された牛乳パックの総量に対する割合および, 各回収ボックスを利用すると思われる人数の総量に対する割合を示したものである.この
2つの円グラフを比較してみると, 一般学生棟, 世帯棟では利用予想人数の割に, 牛乳パックの回収数が多いのに対し, 共用棟では回収数が少ないといえる. このことから, 回収数をあげるには, 回収ボックスをより近くに, つまり各ゴミ回収場所に設置するほうが望ましいと考えられる.
【7】 回収状況への対策
今までの分析結果から
, 今後の牛乳パック回収方法としては 1. 告知の徹底, 2. 各ゴミ回収場所に回収ボックスの設置, 3. 回収ボックスはポスト式のものを用いる, の3点が重要であると思われる. ポスト式の回収ボックスとは, 未処理の牛乳パックが混入することへの対策として考えたもので, カスミの回収ボックス(写真参照)のように投入口を広く設けるのではなく, ポストのように投入口の高さを低くすることにより, 切り開いていない牛乳パックやゴミの混入を防ごういうものである.
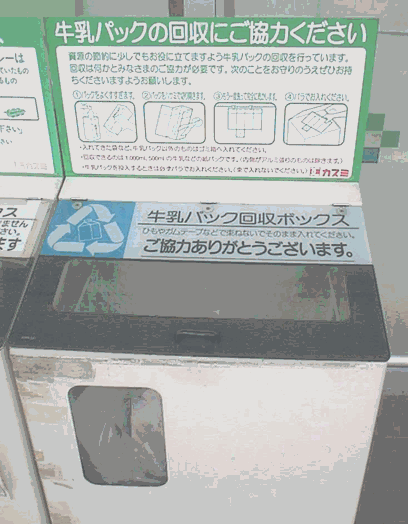
【8】 回収システムの提案
ここで提案する回収システムは
, 企業の生産・販売責任を明確にすべきとする立場から,吉池を回収システムの核として位置づけている
.これまでの分析結果から
, 牛乳パックの回収システムとしては, 回収システムについての情報の告知を徹底した後, 各ゴミ回収場所にポスト式の回収ボックスを設置し, 販売責任のある吉池が, 清掃員が回収した牛乳パックを取りまとめるのが理想である. しかし, このシステムでは, 回収ボックスを設置するスペースが十分にとれない可能性があるほか, 吉池にと清掃員には, 連係作業にともなう調整によけいな負担がかかることになる. そのため, 各ゴミ回収場所での牛乳パックの回収は行わず, 吉池の店頭でのみ回収を行う方法を, 現実的なシステムとして提案したい. この回収システムでは, 回収数は分析結果からも予想されるように, 減少すると思われるが, 吉池が単独で作業を行なえるため, 作業調整が必要ではなくなる. また, 吉池は一ノ矢の他, 平砂, 追越宿舎にも出店しているため, 宿舎全体での同一システムによる回収が可能であるという, 大きなメリットがある.
最後に
, 回収された牛乳パックを製紙工場へ輸送している業者の一例として, 「紙叶」を紹介したいと思う. 紙叶は, カスミで回収している牛乳パックを静岡の製紙工場へ輸送している業者である. 写真は回収された牛乳パックを保管している状況を撮影したものである.一枚の木の板に積まれている牛乳パックが
, 約2日分の回収量に相当するそうである.
写真3.2.5 紙叶
3.3 ペットボトルに関する実験と仮説の検証
現在の宿舎におけるゴミ分別システムにおいて「ペットボトル」はリサイクル資源として「古紙・古布」で回収することになっている。しかし、ゴミの組成調査を始めると、図3.3.1から見て明らかなようにペットボトルの分別回収状況が非常に悪いことがわかった。ほとんどのペットボトルは燃えるゴミとして捨てられているという現状であった。これは、現在のゴミ回収場所に「ペットボトル」の明確な表示がないのが原因であると考え、ペットボトルの回収率を上げる為の以下の仮説をたて、ペットボトルの回収実験を行った。
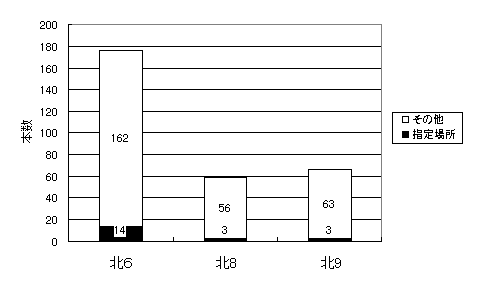
『現在のペットボトルの回収率が悪いのは、ゴミ回収場所に「ペットボトル」の明確な表示がなされていないためであり、「ペットボトル」の表示があれば、分別回収率は上がる。』
3.3.3 実験内容
実験の概要:ゴミ回収場所の「古紙・古布」の表示の下に「ペットボトル」の表示を取り付け、
その前後におけるペットボトルの回収状況を調査する。
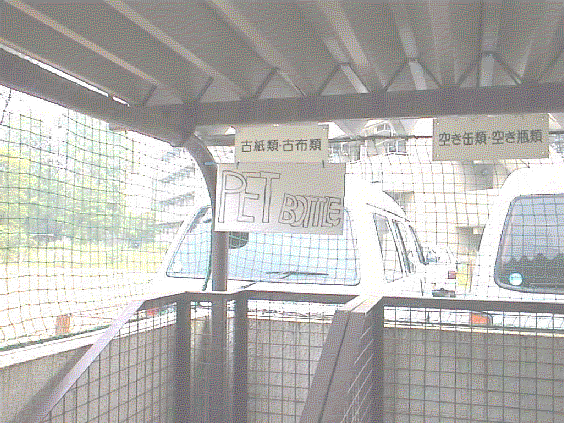
期間:5月6日〜6月4日(表示は6月21日から)
図3.3.3 北9での表示の様子
3.3.4 実験結果
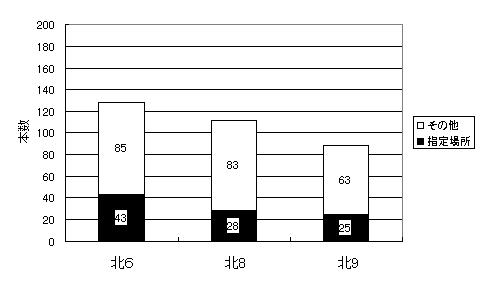
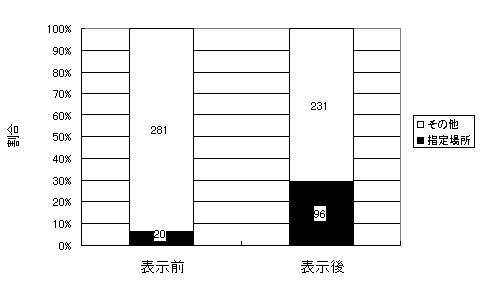
図3.3.4.2表示前後の回収率の変化
図3.3.4.1から見て取れるように、ペットボトルの表示後は各ゴミ回収場所でペットボトルの回収量は増加した。
図3.3.4.2から表示前後を比較すると、表示前回収率6.6%だったペットボトルは表示後短期間で28.7%にあがった。
実験結果から、明らかにペットボトルの表示後はペットボトルの回収率ると言えることがわかった。このことから実験の仮説が正しいと言え、現在、ペットボトルの回収率が極めて低いのは、ゴミ回収場所にペットボトルの明確な表示がないためであると言える。
現在のゴミ分別回収システムにおいて、ペットボトルの分別回収率を上げるために次の改善策を提案する。
・ゴミ回収場所の「古紙・古布」の表示の下に新たに「ペットボトル」の表示を設置する。
ペットボトルの回収率の低さは3年前の実習から問題に取り上げられ、回収率を上げるための実験が行われ、同様の提言が繰り返されてきた。最近の傾向として、缶やビンのゴミよりもペットボトルの排出量の方が多いということが言え、資源リサイクルという観点からは、ペットボトルの分別回収率を上げることは、非常に有意なことであるといえるはずである。
にもかかわらず、未だ改善されないのは、学校側のゴミに関する意識が低い、または、この実習の結果に全く興味を示さず目を通していない、または、縦割り行政の弊害でなかなか、動けないのいずれかであると考えざるを得ない。理由はともかく、この簡単な改善を今回は早急に対応して欲しい。