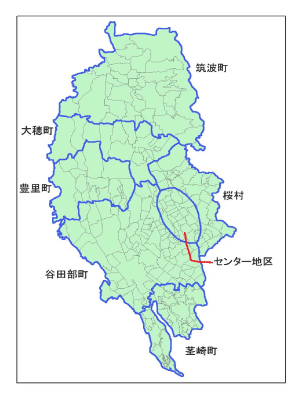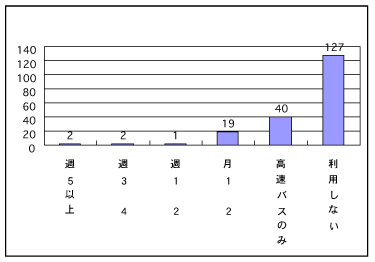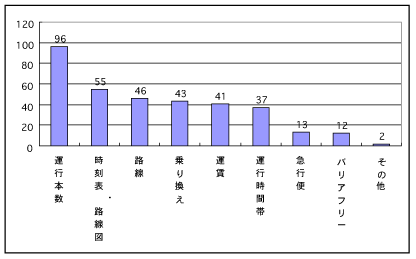1.研究の流れ
2.地区割りセンター・オブ・センター構想に基づき、つくば市全体をいくつかの地区に区分することにした。 各地区には地区ターミナルが設置される。 その地区ターミナルはコミュニティバスと関鉄バスの結節点となるので、 人が集まり、認知されやすい場所でなければならない。よって次の2つの調査を行った。 € 商業施設・公共施設の立地調査 現在の関鉄バス路線、のりのりバス路線の調査 調査の結果、商業施設・公共施設はつくば市合併前の旧6か町村に程よく分散していることが分かった。 また、のりのりバスも旧6か町村の中を広範囲にわたって、各集落をくまなく巡回している。 よって、旧町村の境界線を基準に地区割りをした。 しかし、つくばセンター地域については旧町村の境界線で説明できない。 つくばセンター地域は商業施設や公共施設が立地していて、 さらに、のりのりバスや関鉄バスの結節点となっており、つくば市の中心的な地域となっている。 そこで、つくばセンター地域も1つの地区と考えることにした。
3.地区選択つくば市全体では対象が広すぎるため、研究を進めるにあたり1つの地区を選択した。その際、 などの理由から大穂地区を選択した。 4.現状把握大穂地区におけるのりのりバス利用の現状を把握するため、以下のようなバス利用実態調査を行った。€現地調査
 問題点 利用者が少ない(1人) 所要時間が長い(100分) ダイヤに無理がある。 アンケート調査
 調査の結果 総数201、有効数191(うち男性79、女性122)
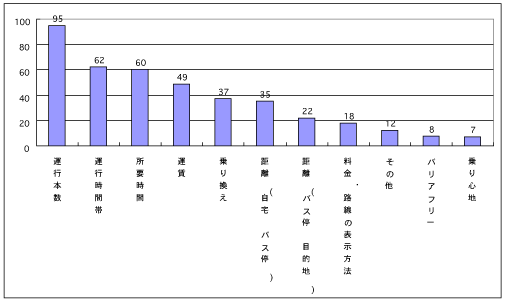 利用しない人の不満点として運行本数、運行時間帯、所要時間が挙げられた。 これら3つが上位を占めたのである。4番目には運賃が挙げられたが、今回運賃について私たちは問題としない。 関鉄バスのヒアリングにより、バス会社としては、運賃は決して高くないということであった。 バスの運賃には燃料代、整備代、保険代が含まれているからである。
5.考察まず、要望の多い運行本数と所要時間についての改善策を述べる。 本研究では現在ある資源を基に考えたため、 運行時間帯については議論しないことにした。 現在の大穂地区内ののりのりバス(下図)について説明すると、 すると、 各集落をくまなく回っていると言える。 さらに、一般の路線バスが通らないような細い道路を走るため、あまりスピードを出せない。 これらの理由により、路線距離が長く、コースを1周するのに100分ほどかかってしまっている。 このため運行本数と所要時間に問題が出ている。 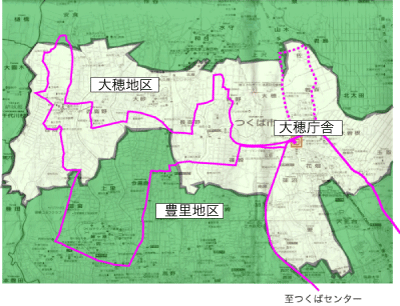 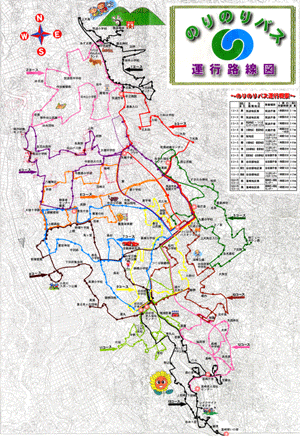 そこで、路線距離を短くすれば短時間で周ることができ、運行本数も増やすことができるのではないかと考えた。 現在のりのりバスはつくば市全体で13台ある。 センター・オブ・センター構想に基づき市内7地区に13台を配分するとして、 各地区に約2台は配置できることになる。つまり、大穂地区においてものりのりバスを2台配置できる。 これらを大穂地区の東西2地区で1台ずつ回すことを考えた。 改善策として、西地区ではより短時間で多くの本数を走らせるために、 主要な幹線道路だけを走行することにする。このおかげで距離も所要時間も短くなり、 本数も倍の12本に増える。このコースを効率性重視路線と位置付ける。 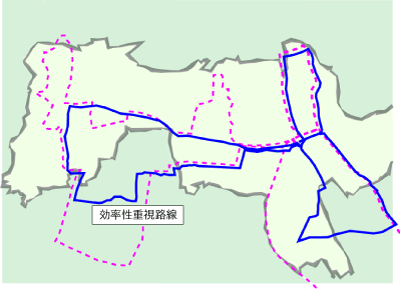 現在の4コースでは豊里地区を回っている6コースと路線が重複するので、ここは省く。 この考え方はセンター・オブ・センター構想によるものである。 東地区を回る路線は基本的に現在の4コースを重視するが、つくばセンターは経由しない。 その代わりに今までのりのりバスは走っていてもバス停のなかった要、大穂、筑穂地区を回ることとする。 現在、要地区を通る4コースは西大通りを走行している。しかし、関鉄バスと路線の重複を避けるため、 大通り上にはのりのりバスのバス停を配置しないことになっている。 以上から効率性という観点では、この効率性重視路線の利便性は大幅に向上する。 ただ、路線を変更することによって自宅からバス停への距離が遠くなる住民が生じる。 そのためにバスを利用しにくくなる可能性も出てくる。図12よりバスしか交通手段がない人や、 バス停が近いからという理由で利用している人が実際に存在することが分かる。 そこで、今までの路線を重視した改善策も考えることにした。 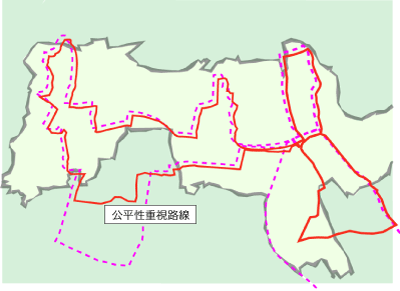 多くの集落を回っている現在路線を重視したものを、公平性重視路線と位置付ける。 この路線では、現在の4コースから豊里地区を回る6コースと重複する部分を削減する。 それ以外は現在の4コースと同じである。この路線も東西地区にコースを分ける。 東地区を回るコースは効率性重視路線と変わらない。 このコースに関して、距離はこれまでと変わらないが、 バスを東西に分けて走らせることにより現在より本数を増やすことが出来る。 現在の路線と効率性重視路線、公平性重視路線との比較は表1のとおりである。
4コースの運転手への聞き取り調査により、現在のダイヤには時間的に無理があるとのことである。 これは、バスの走行時速が30kmとしてダイヤが組まれているからだ。 路線バスの理想的な速度は時速20kmから時速25kmである。 そこで今回は時速25kmとして計算をする。 東地区のコースは効率性重視路線の場合、所要時間が同じになるようにダイヤを組んだ。 その理由は、次の関鉄バスとの連携により示す。 センター・オブ・センター構想に基づき、大穂庁舎がコミュニティバスと関鉄バスの結節点になることは説明した。 だが、現在ののりのりバスのバス停は大穂庁舎内に設置されているのに対して、 関鉄バスのバス停は東大通り沿いに設置されている。 利用者がバスの乗り換えを円滑に行えるようにするために、 コミュニティバスと関鉄バスのバス停は一体的に整備すべきだ。 バスを利用しない人の不満点、バス利用者が改善を望む点として 「乗り換え」が多数挙がっていることも事実である。 さらに、コミュニティバスの東西路線の発着時間と関鉄バスの発着時間を同じにすると、 乗換えが非常に便利になる。これが東西路線の所要時間を同じにした理由である。 これにより各地域からつくばセンターまで、スムーズに往復が出来るようになる。 バスの路線については効率性重視路線と公平性重視路線の2つを提案した。 どちらの路線が適当であるかは、今後の住民の判断に委ねるべきだと考えている。 |