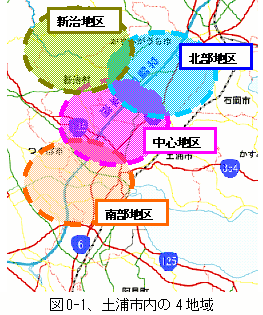
搚塝巗偼丄嶗愳掅抧偲夃儢塝偲偑愙偡傞屛摢偵敪払偟偨屛摢廤棊偱丄搶嫗偐傜60噏寳偵埵抲偡傞堬忛導撿抧堟偺拞妀搒巗偱偡丅
椬愙偡傞偮偔偽巗丒媿媣巗偲偲傕偵嬈柋妀搒巗偵巜掕偝傟偰偄傑偡丅
搚塝巗偺楌巎偼屆偔丄撽暥偐傜幒挰帪戙偵傢偨傞崙巜掕偺巎愓傗暥壔嵿傕懡偔巆偝傟偰偄傑偡丅
峕屗帪戙偵偼忛壓挰偺崪奿偑宍惉偝傟傑偟偨丅
偙偺崰偐傜搚塝偼悈屗奨摴偲嶗愳丄夃儢塝偺悈塣傪曐桳偟丄岎捠偺嫆揰丄暔帒偺廤嶶抧偲偟偰悈屗偵師偖忢棨崙戞擇偺搒巗偲偟偰斏塰偟傑偟偨丅
柧帯埲崀傕敪揥傪懕偗丄導偺弌愭婡娭傗媽惂拞妛傕抲偐傟傑偟偨丅
徍榓弶婜偵偼奀孯峲嬻戉梊壢楙偑愝抲偝傟傑偟偨丅
偦偟偰丄徍榓49擭偵偼恖岥偑10枩恖傪挻偊丄導撿抧堟偺拞妀搒巗偲偟偰偺抧埵傪妋屌偨傞傕偺偵偟傑偟偨丅
偟偐偟丄嬤擭偱偼拞怱巗奨抧偱偺憡師偖戝宆揦偺揚戅傗峹奜揦偺棫抧偵傛傝丄拞怱巗奨抧偺嬻摯壔偑恑傫偱偍傝丄壛偊偰椬愙偡傞拀攇尋媶妛墍搒巗偺敪揥丄偮偔偽僄僋僗僾儗僗偺奐捠側偳偺塭嬁偐傜丄偦偺抧埵偑備傜偓偮偮偁傝傑偡丅
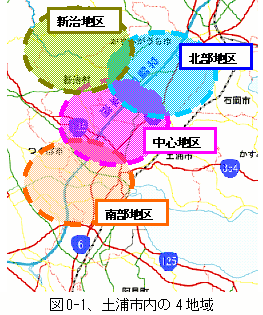
巗撪偼丄忛壓挰丒彜搒偲偟偰塰偊偨拞怱抧嬫丄尋媶妛墍搒巗偵嬤愙偟峳愳壂墂傪拞怱偲偟偨撿晹抧嬫丄恄棫岺嬈抍抧傪拞怱偲偟偨杒晹抧嬫偺3抧嬫偵暘妱偝傟傑偡丅
傑偨丄暯惉18擭2寧20擔偵偼拀攇嶳榌偺怴帯孲怴帯懞偲崌暪偟丄怴搚塝巗偲偟偰怴偨側僗僞乕僩傪愗傝傑偟偨丅
乮侾乯恖岥
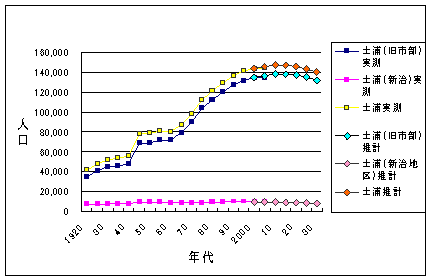
恾0-2丄搚塝巗彨棃恖岥梊應
搚塝巗偺恖岥偼144,433恖乮暯惉17擭11寧1擔丄媽搚塝巗媦傃媽怴帯懞挷傋乯偱丄椉巗懞偺憤崌寁夋傪嶲徠偡傞偲彨棃恖岥偼20枩恖偲憐掕偝傟偰偄傑偡丅
偟偐偟丄暯惉14擭偺崙棫幮夛曐忈丒恖岥栤戣尋媶強偺帋嶼偱偼暯惉27擭乮2015擭乯偺147,173恖傪僺乕僋偵尭彮偵揮偠丄尰嵼偐傜20擭屻偵摉偨傞暯惉37擭乮2025擭乯偵偼143,475恖偲尰嵼偺悈弨傪壓夞傞梊應偑棫偰傜傟偰偄傑偡丅(恾0-2)
傑偨丄2005擭偺幚應抣偼梊應抣傪1600恖掱搙壓夞偭偰偍傝丄幚嵺偵偼偙偺梊應傛傝傕憗偔恖岥尭彮偑恑傓壜擻惈偑偁傝傑偡丅
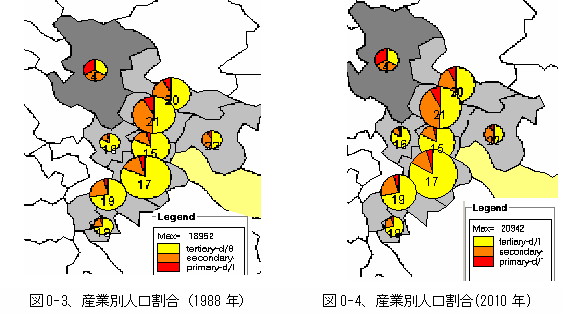
恾0-3偲恾0-係偼JICASTRADA傪梡偄偰嶻嬈暿恖岥妱崌傪媮傔偨寢壥偱偡丅
1988擭偐傜2010擭偺22擭娫偵偍偄偰丄嶻嬈暿恖岥暘晍偺栚棫偭偨曄壔偼妋擣偝傟傑偣傫丅
zone20,zone21偱偼丄恖岥偺栺敿悢偑戞擇師嶻嬈偵廬帠偟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅
偙偺偙偲偐傜傕丄搚塝巗杒晹抧堟偵偼岺嬈抍抧偑懡偄偙偲偑傢偐傝傑偡丅
堦曽偱丄zone15乣zone19偵拲栚偡傞偲丄僝乕儞恖岥偺敿悢埲忋偑戞嶰師嶻嬈偵廬帠偟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅
巗撪慡懱揑偵戞堦師嶻嬈偵廬帠偟偰偄傞恖偺妱崌偼彮側偔丄儗儞僐儞嵧攟偑惙傫側zone22偵拝栚偟偰傕丄堄奜偵擾嬈廬帠幰偼彮側偄偙偲偑妋擣偝傟傑偡丅
乮2乯廧娐嫬
嘆丂廧戭抧
愴嵭偺旐奞偑彮側偐偭偨偨傔搚塝巗拞怱晹偼屆偔偐傜偺壠乆傗奨楬偑巆偭偰偍傝丄摴楬偑嫹偔丄旕忢偵枾廤偟偰偄傑偡丅偙偺偨傔丄搚塝墂慜傗峳愳壂偱偼巗奨抧嵞奐敪帠嬈偑峴傢傟丄抧堟偺嵞惗偲搚抧偺崅搙棙梡偑恾傜傟偰偄傑偡丅
崅搙惉挿婜埲崀丄恖岥憹壛偲巗撪偺搚抧偺崅摣偵崌傢偣偰峹奜偺塱崙傗拞懞惣崻丄栘揷梋側偳偱偼搚抧嬫夋惍棟帠嬈偵傛傝僯儏乕僞僂儞偑憿惉偝傟傑偟偨丅(恾0-5)傑偨丄杒晹恄棫抧嬫偱偼搚塝愮戙揷岺嬈抍抧偲崌傢偣偰戝婯柾側僯儏乕僞僂儞偑嶌傜傟傑偟偨丅
堦曽丄揷懞壂廻傗戨揷摍偺搚抧嬫夋惍棟帠嬈偱偼僶僽儖曵夡摍偺塭嬁偱廧戭傗嬈柋巤愝偺棫抧偑恑傑偢丄戝偒側晧嵚偲側偭偰偄傑偡丅

嘇丂椢抧丒岞墍
拀攇嶳榌偐傜夃儢塝傑偱峀偑傞搚塝巗偼怷椦傗嶗愳摍偺壨愳晘側偳椢抧偑朙晉偱偡丅
傑偨丄愳岥塣摦岞墍傗夃儢塝憤崌岞墍側偳戝彫43僇強偺搒巗岞墍傕偁傝傑偡丅
偟偐偟丄恖岥堦恖摉偨傝偺岞墍柺愊抣偱尒傟偽丄尰搚塝巗偑5.74噓丄尰怴帯懞偑8.28噓偲丄崙搚岎捠徣偺乽椢偺惌嶔戝峧乿(暯惉6
擭)偱栚昗悈弨偲偡傞廧柉堦恖摉傝柺愊20噓偺4暘偺1掱搙偲側偭偰偄傑偡丅
|
乮俁乯僀儞僼儔 丂嘊丂岎捠 搚塝巗偺摴楬栐偼媽悈屗奨摴傪宲彸偡傞傛偆偵崙摴6崋丄JR忢斨慄丄忢斨帺摦幵摴偑惍旛偝傟丄搶嫗丄悈屗傊偺峀堟岎捠傪扴偭偰偄傑偡丅搶惣曽岦偵偼崙摴125崋丄354崋偑憱偭偰偍傝丄堫晘丄幁搱丄偮偔偽曽柺偲偺岎捠傪扴偭偰偄傑偡丅拞怱巗奨抧偼忛壓挰帪戙偺摴楬栐偑偦偺傑傑宲彸偝傟偰偄傞偨傔丄嫹偄摴楬偑懡偔巆偭偰偄傑偡丅 嵟怴偺恖岥僨乕僞傪梡偄偰JICA-STRADA偲CUET偱岎捠検偺暘愅傪峴偭偨寢壥丄搚塝巗偼偮偔偽巗偲偺寢傃偮偒偑傕偭偲傕嫮偔丄懕偄偰垻尒挰丄偐偡傒偑偆傜巗愮戙揷抧嬫丒夃儢塝抧嬫偺弴偵側偭偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅(恾0-6) 傑偨丄偮偔偽巗傊偺摴偼丄惍旛偝傟偨摴楬偑悢懡偔懚嵼偡傞偺偱崿嶨偼栚棫偨側偄偺偱偡偑丄撿杒偵憱傞崙摴6崋慄偼丄搚塝巗撪偺傎傏慡慄偵搉偭偰傂偳偄崿嶨忬嫷偲側偭偰偍傝丄垻尒傊偲偮側偑傞崙摴125崋丄偐偡傒偑偆傜巗夃儢塝抧嬫傊偲偮側偑傞崙摴354崋丄偝傜偵偼搚塝墂慜傕崿嶨偑栚棫偮忬嫷偵側偭偰偄傑偡丅(恾0-7) 巗撪偺岞嫟岎捠偼娭搶揝摴偺楬慄僶僗偑拞怱偱偡偑丄摨幮偺擭娫桝憲検偼1999擭乣2003擭偺5擭娫偱32亾尭彮偟偰偄傑偡丅尰嵼丄拞怱巗奨抧偺妶惈壔栤戣偲儕儞僋偟丄僶僗棙梡晄曋抧堟偺娚榓丄岞嫟岎捠棙梡偺懀恑傪栚揑偵丄僉儔儔偪傖傫偲屇偽傟傞僐儈僯儏僥傿乕僶僗偑塣峴偝傟偰偄傑偡丅 嘇丂忋壓悈摴 搚塝巗偺忋悈摴晛媦棪偼暯惉16擭3寧枛偱尰搚塝巗偑94.40亾丄尰怴帯懞偼88.68亾偱傎傏9妱嬤偔偺悽懷偵嫙媼偝傟偰偄傑偡丅堦曽丄壓悈摴晛媦棪偼偦傟偧傟81.78亾乮晛媦棪導撪4埵乯丄71.95亾乮摨10埵乯偱丄偄偢傟傕悈屗巗傛傝傕崅偄抣偱偡丅 嘊丂忣曬丒捠怣 搚塝働乕僽儖僥儗價姅幃夛幮乮J-COM Broadband堬忛乯偑慡堟偱偼側偄傕偺偺尰搚塝巗偲媿媣丄偐偡傒偑偆傜椉巗丄垻尒挰傪僇僶乕偟偰偄傑偡丅 |
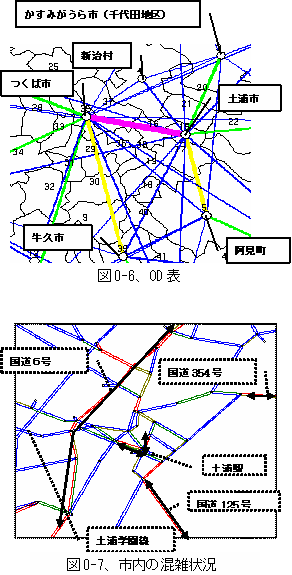 |
乮係乯彜嬈
偐偮偰搚塝巗偼導撿堦偺彜搒偩偭偨偑丄偦偺擭娫彜昳斕攧妟偺懳導僔僃傾偼擭乆尭彮偟偰偄傑偡丅
嘆丂拞怱巗奨抧
拞怱晹偵偼戝彫懡偔偺彜揦偑棫抧偟偰偄傑偟偨偑丄儌乕僞儕僛乕僔儑儞傗恖岥偺峹奜恑弌偵傛傝丄偐偮偰偺妶婥傪幐偄丄嬤擭偱偼戝宆揦偺憡師偖揚戅傗憹壛偡傞嬻偒揦曑偑栤戣偲側偭偰偄傑偡丅
暯惉9擭丄嵞奐敪帠嬈偺僾儘僕僃僋僩偲偟偰丄URALA偑寶愝偝傟偨偑丄埶慠偲偟偰戝宆揦偺暵揦丄彜揦奨偺悐戅偼懕偄偰偄傑偡丅
傑偨丄曕峴幰摦慄傕墂偲URALA偺娫偽偐傝偑懢偔丄偦偺懠偺抧揰偺摫慄偼庛偄栰偑尰忬偱偡丅
嘇丂偦偺懠偺抧堟
撿晹抧嬫偱偼崙摴6崋偲妛墍搶戝捠偺岎嵎揰傪拞怱偵峹奜宆偺戝宆揦偑棫抧偟偰偄傞懠丄峳愳壂墂搶岥偵乽偝傫傁傞乿偲偄偆墂捈寢偺僔儑僢僺儞僌僙儞僞乕偑偁傝傑偡丅
杒晹抧嬫偺恄棫墂廃曈偱偼栚棫偭偨彜嬈巤愝偼側偄偑丄椬愙偡傞偐偡傒偑偆傜巗偵愮戙揷僔儑僢僺儞僌僙儞僞乕偑偁傝傑偡丅
怴帯抧堟偵偼僄僐僗傪妀僥僫儞僩偲偡傞乽偝傫丒偁傄偍乿偑偁傞懠丄椬愙偡傞偮偔偽巗偵偼懡偔偺彜嬈巤愝偑偁傝傑偡丅
乮係乯擾嬈
夃儢塝偵柺偡傞搚塝巗偼掅幖惈悈揷抧懷偵埵抲偟偰偍傝丄儗儞僐儞偺惗嶻偑惙傫偱偡丅
傑偨丄壴櫫嵧攟偵傕椡傪擖傟偰偄傞懠丄怴帯抧堟偱偼壥庽嵧攟偑惙傫偱偡丅
丂嘆丂儗儞僐儞
搚塝巗偺儗儞僐儞惗嶻検偼慡崙堦偱丄摿偵夃儢塝屛娸偺壂廻丄揷懞丄庤栰丄栘揷梋抧嬫偲嶗愳廃曈偺拵妡抧嬫側偳偵懡偔嵧攟偝傟偰偍傝丄庡偵嫗昹曽柺偵弌壸偝傟偰偄傞丅傑偨丄儗儞僐儞査側偳儗儞僐儞偺壛岺昳偺斕攧偵傕椡傪擖傟偰偄傑偡丅
| 昞0-1丄儗儞僐儞惗嶻検 | |||
| 弴埵 | 巗挰懞柤 | 嶌晅柺愊乮ha乯 | 廂妌検乮t乯 |
| 1埵 | 搚塝巗 | 496 | 7640 |
| 2埵 | 夃儢塝挰 | 340 | 5100 |
| 3埵 | 摽搰導柭栧巗 | 331 | 4620 |
| 4埵 | 垽抦導棫揷懞 | 240 | 3270 |
| 5埵 | 嶳岥導娾崙巗 | 195 | 3010 |
| 6埵 | 嬍棦懞 | 147 | 2070 |
| 7埵 | 嵅夑導暉晉挰 | 132 | 2000 |
嘇丂壴櫫
慡崙桳悢偺惗嶻検傪屩傞僌儔僕僆儔僗偼丄導偺柫暱惗嶻偺巜掕傪庴偗偰偍傝丄傾儖僗僩儘儊儕傾偵偮偄偰傕導巜掕柫暱悇恑嶻抧偲側偭偰偄傑偡丅
嘊丂壥庽
怴帯抧嬫偵偍偄偰偼壥庽墍偑懡偔丄乽怴帯僼儖乕僣儔僀儞乿偲屇偽傟偰偄傞傎偳偱偡丅摿偵丄傒偐傫偺嵧攟偺杒尷丄傝傫偛嵧攟偺撿尷偱偁傝丄懠偵傕僫僔丄僽僪僂丄僋儕丄僇僉偑摿嶻偲側偭偰偄傑偡丅
乮俆乯悈嶻嬈
夃儢塝偼220倠噓偺屛柺愊傪屩傞擔杮戞2埵偺屛偱偁傝丄條乆側嫑偑惗懅偟偰偄傑偡丅
搚塝巗偱偼壂廻嫏峘傪嫆揰偲偟偰儚僇僒僊側偳偺嫏嬈偑惙傫偱偡偑丄嬤擭丄夃儢塝偺悈幙埆壔偱嫏妉崅偑尭彮偟偰偄傑偡丅
偦偺偨傔帒尮妋曐偲嫏妉崅憹壛偵岦偗偰丄抰嫑曻棳傗梴怋側偳偵傕庢傝慻傫偱偄傑偡丅
捪幭側偳偺悈嶻壛岺嬈傕惙傫偱偡偑丄夃儢塝偺嫏妉崅尭彮偑塭嬁偟丄尨椏偺妋曐偑擄偟偔側偭偰偄傑偡丅
乮俇乯岺嬈
岺嬈偼杒晹抧堟偑拞怱偱丄偐偡傒偑偆傜巗偲偺嫬奅偵偁傞搚塝愮戙揷岺嬈抍抧偵偼擔棫僌儖乕僾偺婇嬈側偳41幮偑棫抧偟偰偄傑偡丅
傑偨丄忢斨摴搚塝杒IC偵嬤愙偡傞僥僋僲僷乕僋搚塝杒偵偼7幮丄搶拀攇怴帯岺嬈抍抧偵偼1幮偑棫抧偟偰偍傝丄偙傟傜偺抧堟傊偺婇嬈桿抳傪懀恑偟偰偄傑偡丅(恾0-8)
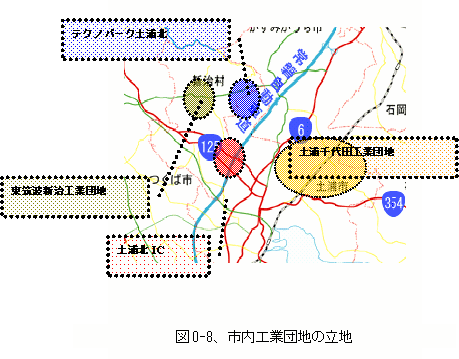
乮俈乯娤岝
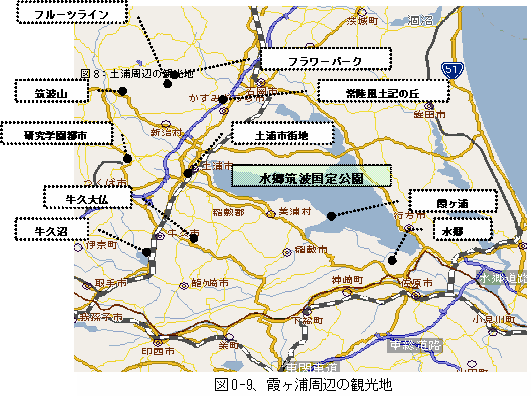
搚塝巗偼屆偔偐傜偺忛壓挰偱偁傞偲摨帪偵悈嫿拀攇崙掕岞墍偺堦晹傪宍惉偟偰偍傝丄夃儢塝傗拀攇嶳側偳偺娤岝帒尮偑朙晉偱偡丅
傑偨丄廃曈抧堟偵偼愇壀巗偺忢棨栰晽搚婰偺媢丄僼儔儚乕僷乕僋丄偮偔偽巗偺楈曯拀攇嶳傗拀攇嶳壏愹偑偁傝丄峀堟娤岝偺億僥儞僔儍儖偺崅偄抧堟偲側偭偰偄傑偡丅
嘆丂楌巎偁傞奨暲傒
忛愓丄帥幮傪偼偠傔丄摴昗丄堦棦捤傗壠暲傒摍偑巆偝傟偰偄傞懠丄楌巎揑搒巗宨娤惍旛帠嬈偲偟偰憼傗愇忯側偳偺曐懚丒夵廋傕峴傢傟偰偄傑偡丅
嘇丂夃儢塝偲嶗
悈嫿拀攇崙掕岞墍偵巜掕偝傟偰偄傞夃儢塝偼擔杮戞2埵偺屛偱丄搚塝巗偺娤岝帒尮偺堦偮偱傕偁傞丅
夃儢塝偱偼儓僢僩傗僼傿僢僔儞僌側偳偺僂僅乕僞乕僗億乕僣偑惙傫偱偁傝丄梀棗慏傕塣峲偟偰偄傑偡丅
拀攇嶳撿榌偵埵抲偡傞怴帯抧嬫偱偼丄僗僇僀僗億乕僣偑惙傫偱偁傝丄傑偨僼儖乕僣儔僀儞偲屇偽傟傞壥庽墍孮偑偁傝傑偡丅
偦偺懠丄嶗愳増娸傗巗撪奺強偵偼嶗偺柤強偑懡偔偁傝傑偡丅
嘊丂擔杮堦偺壴壩嫞媄戝夛
枅擭10寧偺戞1搚梛擔偵嶗愳斎乮妛墍戝嫶晅嬤乯偱奐嵜偝傟丄擔杮嶰戝壴壩戝夛偺堦偮偲偝傟偰偄傑偡丅
擔杮偺戙昞揑側壴壩巘偑奺抧偱1擭偺壴壩戝夛傪廔傢傝丄偦傟傑偱偵摼偨尋媶柇媄偱擔杮堦傪栚巜偡偲嫟偵丄壴壩巘払偺媄弍廋楙偺応偲偟偰嵟傕尃埿偁傞戝夛偲奿晅偗偝傟偰偍傝丄枅擭栺65枩恖偺娤媞偑朘傟傑偡丅