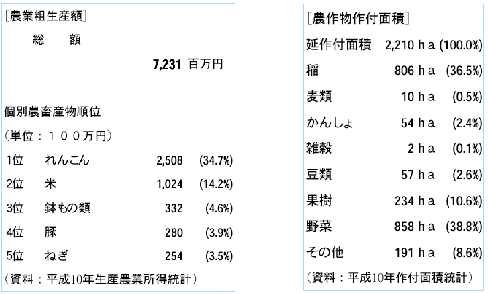
表1 表2
3−5.福祉計画
土浦生き生きプラン
高齢者や障害者は多くの不安を抱えながら日々生活をしている。これらの不安は
どれ一つをとってみても高齢者や障害者個人の努力の努力や、家族の扶助だけでは
解決できないものばかりである。その解決には国や地方公共団体の協力が必要と思
われる。そこで、この土浦生き生きプランは高齢者や障害者の不安を解消するために
作成されたプランである。以下、高齢者や障害者の不安に対する行政側の取り組みを
あげる。
○ 経済に関する不安
仕事や職業をやめたこと(もしくは就労していないこと)によって、収入が減少
し、それによって現在の生活水準を維持することができない。
取り組み
・空きビルや空き店舗を利用した新規の職場の創出、高齢者や障害者の働く場
所の拡大
○ 生活の場の不安
高齢者だけの世帯や一人暮らし世帯が増加し、高齢者だけで衣食や住居を整える
のは困難である。
取り組み
・高齢者や障害者が自立して暮らせるための住宅の供給
・生活に必要な施設の住宅との一体的整備
○ 身の回りの世話(介助・介護)の不安
一人暮らしの高齢者は、身の回りの世話をする介護者のいないことこらくる不安
に絶えず脅かされている。また、介護する家族にかなりの負担がかかる。
取り組み
・ホームヘルパーの養成と労働条件の整備
・介護NPOへの支援
○ 生命・身体に関する不安
病気に対する不安。不慮の事故に対する不安。
取り組み
・医療施設の充実
・公共機関や歩道のバリアフリーの環境整備
○ 精神的な不安
社会的な地位の低下や役割の喪失にともなって人間関係が希薄になり、孤立を深
め、孤独な生活になりがちである。
取り組み
・生涯活動・文化活動の推進
3−6.農業振興計画
「新時代近郊農業都市、土浦」の提唱
日本では今後、少子化によう人口減少が予想され、国内の内部需要は大幅に拡大
する見込みは少ないものと、工業・商業の更なる発展は厳しいものがあると考えら
れる。一方で、農業については自給率が30%台という低さであり、国産の農産物を
求める志向も強まっていることから、農業は、今後日本で成長する産業の一つであ
ると考えられる。その中で、土浦は、都心から車・電車で1時間程度の所にありな
がら、多くの農地を有しており、近郊農業を行う場所として優れている。この優れ
た立地条件を活かし、周辺の、千代田、霞ケ浦、八郷、つくば、牛久を含めた、「こ
れからの近郊農業」を提唱するような街作りを行う。
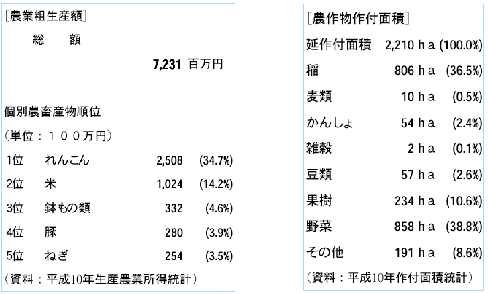
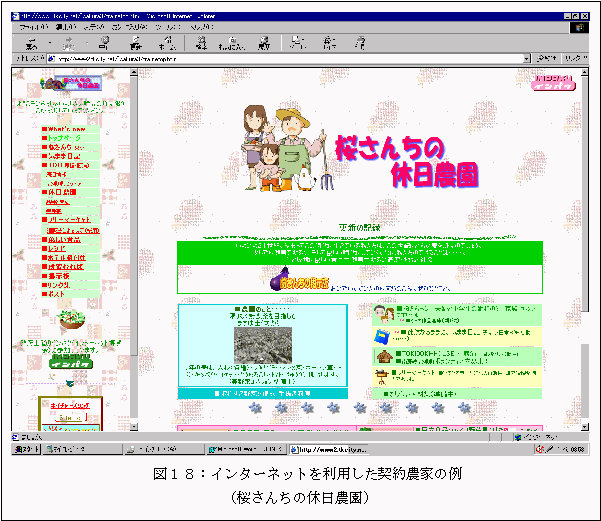
日本は現在、「農業=格好悪い」といったイメージが定着しているが、将来の農業
人口は必ず増加し、農業に対するイメージもアップするものと思われる。その際に、
土浦が「都市近郊の農業の代表」となれるような都市になるような街作りを目指す。
3−7.計画人口
141,000人
コーホート分析によると土浦市の人口はピーク時におよそ142,000人まで増加す
る。そのため、この結果と土地利用計画における住宅整備を考慮して、現在の人口
136,000人に+5,000人の141,000人に計画人口を設定する。
5,000人の内訳:荒川沖駅 500人
瀧田 2,000人
蓮河原 2,500人